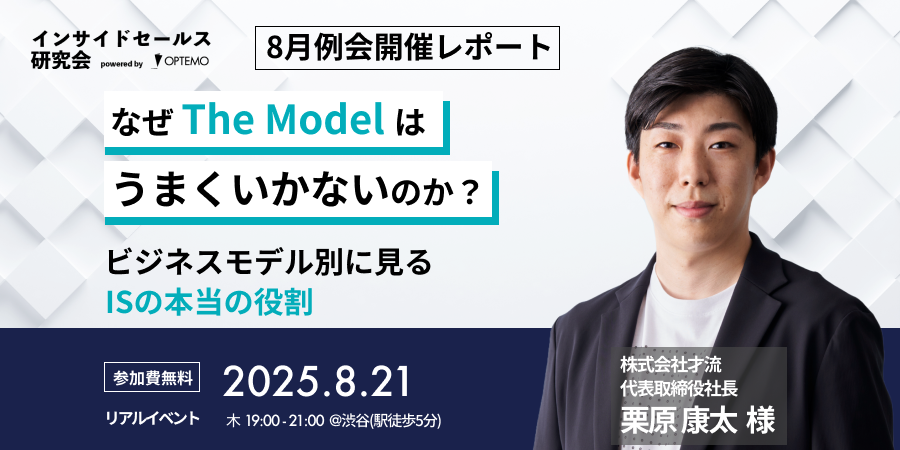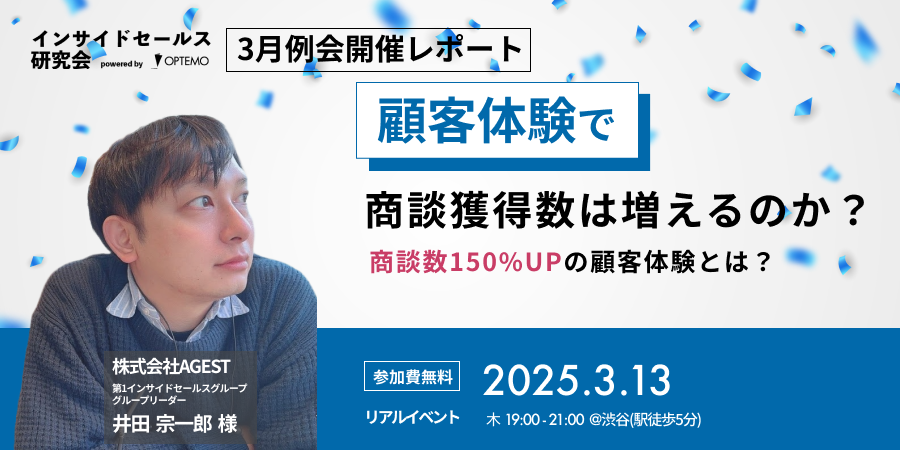インサイドセールス研究会2025年6月例会レポート
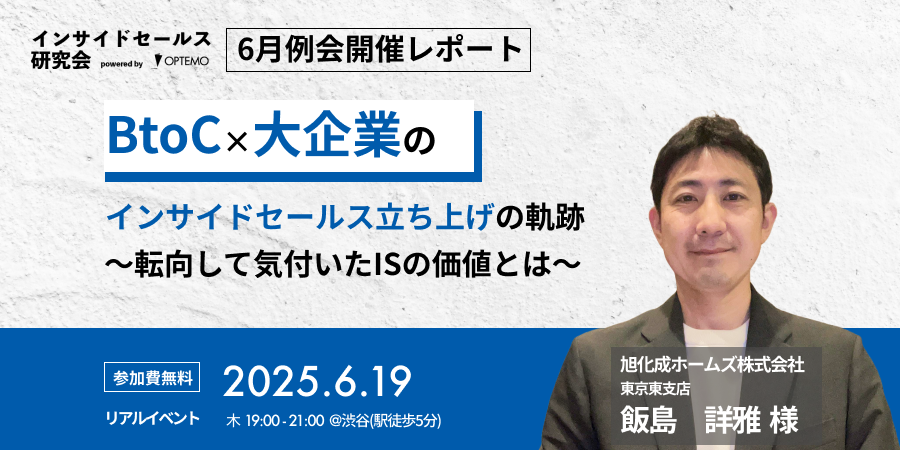
株式会社OPTEMOが運営しているインサイドセールス研究会というコミュニティでは、毎月オフラインイベントを開催しております。6月に開催されたイベントの内容について、より多くの皆様に知っていただく機会となることを願い、イベントレポートを作成しました。
今回のレポートでは、2025年6月19日(木)に渋谷に位置する千葉道場コミュニティスペースで開催されたインサイドセールス研究会の内容をまとめております。ぜひご覧ください。
目次
インサイドセールス研究会について
インサイドセールス研究会は、『会社を超えてインサイドセールス同士がつながり「師と友」を作れる場』として株式会社OPTEMOが運営しているコミュニティです。
インサイドセールスという業務の性質上、社外での横のつながりが少ないという声を受け、2023年3月からこのコミュニティの運営を始めました。毎月特別なゲストを迎えて実践的なノウハウを提供しています。また、Facebookのグループで情報発信もしており、誰でも無料で参加できます。
https://optemo.co.jp//lp/is_ken
今回のテーマ
今回のイベントでは、旭化成ホームズ株式会社の飯島 詳雅様をゲストにお迎えしました。「BtoC×大企業のインサイドセールス立ち上げの軌跡 ~転向して気付いたISの価値とは~」というテーマで登壇していただきました。モデレーターはOPTEMO代表の小池桃太郎(@MomotaroKOIKE)が務めました。
また、OPTEMOのBPaaS事業責任者兼、インサイドセールスマネージャーを務める袖崎徹也もイベントに登壇しました。
飯島様ご講演
飯島様は2003年に旭化成ホームズ株式会社に入社して以来、20年以上にわたりフィールドセールスの経験を積んできました。2024年10月からインサイドセールスに転向され、BtoCの住宅販売(ヘーベルハウス、ヘーベルメゾン、ヘーベルビルズなど)における新たな営業手法の開拓に取り組まれています。
これまでフィールドセールスとして成果を出すため様々な資格を取得し、お客様の趣味への共感を重視した営業スタイルで社内でも高い評価を獲得。「お客様を理解しなければ住宅のご注文はいただけない」という強い信念のもと、確かな営業実績を積み上げてきました。
当日のイベントでは、以下のトピックについてお話しいただきました。
・BtoC×大企業でのインサイドセールス立ち上げ
・1日のスケジュール設計で成果を最大化
・メール戦略の最適化で通電率を劇的に改善
・顧客理解と個別対応【3分調査による効果的アプローチ】
・郵送戦略で競合他社と差別化
・正しい言葉遣いとマナーで信頼関係を構築
BtoC×大企業でのインサイドセールス立ち上げ
フィールドセールスが中心だった住宅業界において、大企業がインサイドセールスを導入するのは珍しい取り組みです。コロナ以降の市場環境変化への対応とダイバーシティ&インクルージョン推進の一環としてインサイドセールスを検討し始めた背景があります。。旭化成ホームズでは、コロナ禍による市場環境の激変を背景に、新たな営業手法としてインサイドセールスの導入を決断しました。
市場環境の変化と組織的課題の顕在化
旭化成グループの営業スタイルは、住宅展示場への来場から商談へ発展して受注へと進むBtoC営業が強みでした。しかしコロナ以降は住宅展示場への来場者数が激減し、それに伴い受注数も大幅に減少する一方で、資料請求数は大幅に増加。その結果、展示場集客数を上回る逆転現象が発生しました。
この状況下で、接客から竣工まで一貫して対応する従来のフィールドセールスだけでは、膨大な資料請求に対する適切なフォローが困難となってきました。
また、時短勤務や在宅勤務を希望する社員への新しい働き方を提供する必要性も高まっていました。その一環としてインサイドセールスという働き方を導入するに至ったとのことでした。
インサイドセールス導入から拡大までの軌跡
住宅業界でのインサイドセールス導入は参考事例が極めて少なく、国内では株式会社スウェーデンハウスと三井ホーム株式会社などの一部の会社だけのようです。当時の本部長が提唱した「ジョブ型への転換」「何かに特化して力をつける」という方針のもと、1,300人の中から飯島様を含む2名が選抜されてスタートを切りました。
当時は社内でインサイドセールスの概念が浸透しておらず、「ISに詳しい人が誰もいない」という状況だったそうです。東京本部内の飯島さま含む2名の IS が着実に成果を積み重ねた結果、埼玉・北関東・関西まで対象エリアが拡大。現在は7名体制に成⾧しました。
飯島氏に課せられたKPIと達成実績
社内初のインサイドセールス担当となった飯島様には、以下のようなKPIが設定されました。
・7日以内に5回架電する
・7日以内に通電率50%を達成する
・カタログ請求の方に展示場へお越しいただき、アポイント率15%を達成する
ホワイトペーパーの集客レベルの見込み客が混在する中での営業活動となり、「BtoC営業ならではの難しさがあった」と飯島様は振り返ります。蓋を開けてみると、7日以内の通電率は61%、アポイントの獲得率は18%だったとのこと。これらはBtoB営業と比較しても遜色のない数値です。
1日のスケジュール設計で成果を最大化
インサイドセールスで成果を出すためには、架電に加えて戦略的な時間配分と感情のマネジメントが不可欠です。展示場での顔が見える営業と電話営業では根本的な違いがあり、飯島様は「お客様の感情を作ること」と「自分の感情を整えること」という2つの重要要素を軸に、1日のスケジュールを綿密に設計されています。とりわけ10時から12時を「ゴールデンタイム」として、9時から18時の間で最大の効果を生み出すための戦略的アプローチを立てています。
朝の準備とゴールデンタイムの活用
飯島様の1日は、前日の通話録音を聞き返すことから始まります。多くの人が嫌がる自分の録音分析を継続的に実践し、第三者目線で音声の振り返りをしています。自分の声を聴いて「今日はテンション高めに行こう」「ゆっくり話そう」といった調整を行い、その日のコンディションを最適化しているとのこと。
10時から12時のゴールデンタイムには完全集中できる環境を構築するため、他業務を事前に完了させ、外部からの電話が入らないように対策しています。おかげで20%の通電率を実現しており、Salesforceを活用して通話と入力の同時進行を可能にしています。
折り返し電話戦略で通電率100%を実現
架電数を少なくするため、飯島様が導入したのは「折り返しの電話を頂けるようにする戦略」です。外食から弁当へ切り替えることで昼休みに待機できる体制を整え、Salesforceの画面を閲覧できる状態で折り返し対応を行うとのこと。
BtoC営業特有の「午前中に電話すると昼休みに折り返しがある」というパターンを活用し、折り返し電話では100%の通電率を達成しています。お客様から電話する際は都合のよい時間を選ぶため、通話時間が長くなっても気兼ねなく話せるメリットがあるのです。
午後の架電による折り返し受電では帰宅後の対応になるため、基本的には職種を問わず10時~12時の間に電話をかけると連絡がつきやすいそうです。
メール戦略の最適化で通電率を劇的に改善
現代のBtoCインサイドセールスにおいて、メール戦略は通電率の向上に直結します。飯島様は留守電を使わない独自のメール戦略を確立し、開封率を左右する要因を分析しました。
あえて会社名を隠さないことで同じ文面でも開封率が劇的に伸び、1ヵ月という短期間でのPDCAサイクルの運用を通じてさらに磨きをかけています。またお客様がスマホでメールを読むことを考慮したファーストビューの最適化により、従来のアプローチを大きく上回る成果を生み出しました。
留守電回避とメール活用による関係構築
架電した際につながらない場合は留守電を残すのではなく、「ご確認いただけないでしょうか」という件名でメールを送信するのが有効です。飯島様によると「先ほどのお電話の件」というタイトルが最も読まれるとのことでした。
こちらから連絡した痕跡を残さないと、先方から「迷惑電話では?」と疑われる危険があります。お客様が電話番号を検索して口コミを調べるのはよくあるケースです。ご自身の電話番号を検索して、悪い口コミがないかどうか、確認をされることをお勧めします。もし書いてあるようでしたら、検索されない工夫や、口コミを消せないか相談をされても良いかもしれません。
顔が見えなくても、相手は感情を持つ人間である。その意識を常に持ち、気持ちよく電話を切ってもらうことが重要なのです。
ギブファーストによる価値提供戦略
飯島様はインテリアのカタログ請求の事例を挙げ、インテリア実例集を追加で送付した際のエピソードを披露。お客様から「ありがとう」と感謝され、お礼のメールをいただいたのがきっかけで商談のアポイントにつながったそうです。
その他にも架電後の自己紹介メールについて触れられ、IS側から先行して価値を提供すれば通電率の向上につながる可能性を示唆しました。テイクよりもギブを優先してお客様との信頼関係を構築することで、「ありがとう」を引き出すサービス設計がおのずと出来上がるのです。
件名最適化による開封率向上と内容設計
お客様にメールを送っても、読んでもらえなければ意味がありません。そこで飯島様はタイトルを工夫して開封率の向上を図っています。
たとえば緊急性のある表現を模索して開封率を分析し、「新春キャンペーン」「間もなく終了」「本日もうすぐ終了」といった表現の違いによる反応率の変化をチェック。有益性・具体性・独自性・共感性を組み合わせた件名設計に加え、会社名と個人名を併記することで信頼感を担保しているそうです。
送信元と件名はメールの開封率を左右する要素であり、それぞれ「30%・40%ほどの割合でお客様から判断される」とおっしゃっていました。
顧客理解と個別対応【3分調査による効果的アプローチ】
インサイドセールスが売上を出すためには、限られた時間内での効率的な顧客理解が不可欠です。BtoBの詳細調査に対し、BtoCでは3分程度の効率的下調べで十分な効果を発揮できることを飯島様は実証されています。
実際にメールアドレスからお客様のキャラクターを読み取ったり、事前に先方のホームページにアクセスして企業の理念をチェックしたり、地道な努力をしているそうです。
メールアドレス分析による顧客特性把握
飯島様は例として文字列から「ミス日本の方かもしれない」と推測したケースを紹介し、メールアドレスに隠された情報を最大限に活用すると述べました。別の事例では動物の名前が入っているアドレスを挙げ、「きっと動物が好きなんだろう」と推測して話題につなげるともおっしゃっています。会社名入りアドレスからは職業や立場を推測し、大学の教授のような社会的立場のある方に対しては控えめな表現を心がけています。
企業理念共感と効果的な話法
商談のアポが入ったら、事前にお客様のリサーチをすることも欠かせません。企業のホームページを閲覧して理念や経営方針を確認し、会社の情報を見ていることをさりげなくアピールして業界特性に合わせた話題提供を行っています。
会社情報を見ていることをさりげなくアピールして業界特性に合わせた話題提供を行っています。
会社の大事にしていることを、私も大事にしているように伝わるように話をしています。
スピードが理念でかいてあったとすると、私は営業において、お役に立つ情報を誰よりも早く提供したいと思っておりまして・・・とお客様の理念と自分の活動をリンクするようにお伝えしています。
事前のリサーチを踏まえたうえで、自社との共通点を伝えて“共感ポイント”を生み出す。このような工夫をすると、商談相手の感情に訴えかけやすいと飯島様はおっしゃっていました。
郵送物へのひと工夫による競合他社との差別化
デジタル時代においても、郵送物が持つ物理的な影響力は依然として見過ごせません。住宅メーカーとの競合というより、塾の DM や健康食品、通販などの郵送物などとの開封競争、競合がありますので。同時期に届く様々な郵送物との明確な差別化を図るために、飯島様は細部まで徹底的にこだわっています。
手書きの宛名・インクの色・文字の向き・郵送物の厚みによる心理効果に加え、シールによる特別感の演出まであらゆる要素を計算し尽くした郵送戦略を展開。これらの工夫により開封率と反応率の向上につなげているそうです。
手書きの宛名で心を伝えて開封率を向上させる
最近は封筒に宛名を印刷する場合が多いですが、飯島様は手書きで宛名をしたためるよう心がけています。
太いペンでていねいに宛名を書くことで“心がこもっている感じ”を強調しているとのこと。これにより開封率の向上が期待でき、「会ってみよう」「電話してみよう」という行動喚起につながっているのです。
また封筒の綴じ目に四つ葉のクローバーやフクロウのシールを貼るのも工夫のひとつです。きっかけはシールを見たある社長から「会いましょう」と言われたことでした。
郵便物を見るのは受け取った相手だけとは限りません。その方の家族が開封して、展示場に足を運んでくださる可能性もあります。そのチャンスを活用すべく、家族ぐるみでの好印象獲得を目指しているそうです。
インクの色にも気を配って心理的な効果を狙う
飯島様によると、「封筒の表書きには『カタログ在中』と書き添えるのですが、その際に赤いペンを使わないようにしています」とのこと。経営者や営業担当者のなかには赤字を好ましく思わない方もいるため、青字で印象を良くするためです。さらに封筒に文字を書く際は右肩下がりになるのを回避して、水平・右肩上がりになるよう注意を払っています。
飯島様の工夫はそれだけに留まりません。薄い郵送物は開封前に捨てられてしまうこともあるために、ノベルティとしてジップロックを同封して厚みを出したり、箱に入れて郵送をされることもあるようです。すぐに捨てられがちなDMだからこそ、他社との違いを打ち出すことが大切なのです。
正しい言葉遣いとマナーによる信頼関係の構築
言葉の持つ印象は非常に強く、些細な一言が相手の心証を損ねることもあるでしょう。飯島様はネガティブな表現をポジティブに転換し、目に見えない減点要素を事前に回避しています。言葉選びが営業成果に直結するため、細部まで計算し尽くされたコミュニケーション戦略を駆使しているそうです。
ポジティブな表現へ転換して気持ちから前向きに
ビジネスの現場ではつい「忙しい」という言葉を使いがちです。「忙しい」は「心を亡くす」と書くため、飯島様は避けているとのこと。
代わりに「ご多用のところ」といった表現に置き換えています。その他にも「申し訳ありません」を「ありがとうございます」に変換し、相手も自分も心地よくやり取りできる配慮が行き届いているそう。
ときには大変なご要望を承ることもありますが、飯島様は「やりがいがあって楽しみです」と伝えるように心がけていると述べました。
正しい敬語と呼称を用いて減点要素を減らす
「知らないうちに減点されているかもしれない」と飯島様が指摘したのは、役職が複数ある場合の正しい肩書きの呼び方です。最高位役職での呼称(例:常務・執行役員兼本部長→常務)を徹底し、役職が長い場合は「○○様」と名前でお呼びすれば角が立ちません。
役職と関連して、飯島様は金融機関別の敬称を紹介。銀行は「御行」、信託銀行・証券会社は「御社」、信用金庫は「御金庫」、信用組合は「御組合」などと使い分けています。人物に関しては前株企業(銀行)では「頭取」、後株企業では「社長」という使い分けになっているとのこと。
これらの知識を理解しておけば「きちんと分かっている人」という印象を相手に与えられ、無意識のうちに減点される可能性は低くなるでしょう。
交流会の様子
講演後の交流会では、住宅業界でのインサイドセールス導入事例に対する高い関心が寄せられました。名刺交換の際には「BtoCでこれほど体系化された手法は初めて聞いた」「自社でも応用できそう」といった声が多く聞かれ、参加者がBtoC特有の課題とその解決策に驚きと共感を示していました。
特に関心が集まったのは、飯島様の1日のスケジュール管理と感情コントロールの具体的手法です。「10時からのゴールデンタイム設定」や「毎朝の録音分析」について詳しく質問される方が多く、継続実践の秘訣について活発な議論が交わされました。また、メール開封率向上のアプローチや郵送物での心理的工夫、折り返し電話の活用法など、即座に実践できるテクニックへの質問も相次ぎました。
インサイドセールス研究会の交流会では、毎回「新しい体験を提供する」というテーマのもと、参加者に特典としてちょっとした品物やサービスをプレゼントしています。
今回は参加者の皆さまへのお土産として、Lindt(リンツ)の「Dubai Style Chocolate」をご用意しました。「パッケージからして高級感がある」「チョコレート好きにはたまらない」など、参加者の皆様から好評でした。
最後に
今回のインサイドセールス研究会では、BtoC×大企業という珍しい組み合わせでのインサイドセールス立ち上げ事例を通じて、業界を問わず応用できる普遍的な営業スキルと、BtoC特有の課題解決手法の両方を学ぶことができました。
飯島様の「お客様の感情を作ること」「自分の感情をコントロールすること」という2つの軸を中心とした体系的なアプローチ、そして毎日の録音分析や1ヶ月単位でのPDCAサイクルといった継続的改善の姿勢は、多くの参加者にとって目から鱗の内容だったようです。
本イベントの内容が、ご参加いただいた皆様のこれからの活動に少しでもお役に立てば幸いです。
次回のインサイドセールス研究会は、株式会社hacomonoの樋口堅太郎様・萩原真由様をゲストに迎え、2025年7月22日(火)19:00-21:00に渋谷で「事業成長のドライバーとなる強いインサイドセールスとは? ~戦略と実践の具体事例を大公開~」というテーマで開催いたします。
▼参加申し込みはこちらから
https://share.hsforms.com/1OQvosd4-QZuIlolMg_qKrQcqns4?utm_seminar=optemo_eventpage
次回のインサイドセールス研究会で、多くの参
加者とお会いできることを楽しみにしております。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから