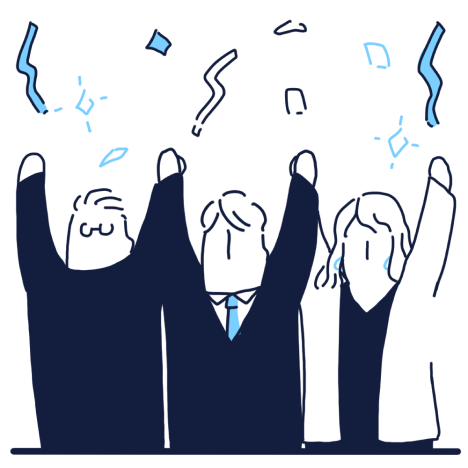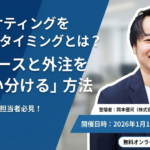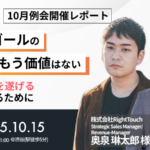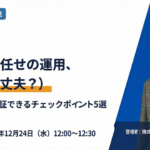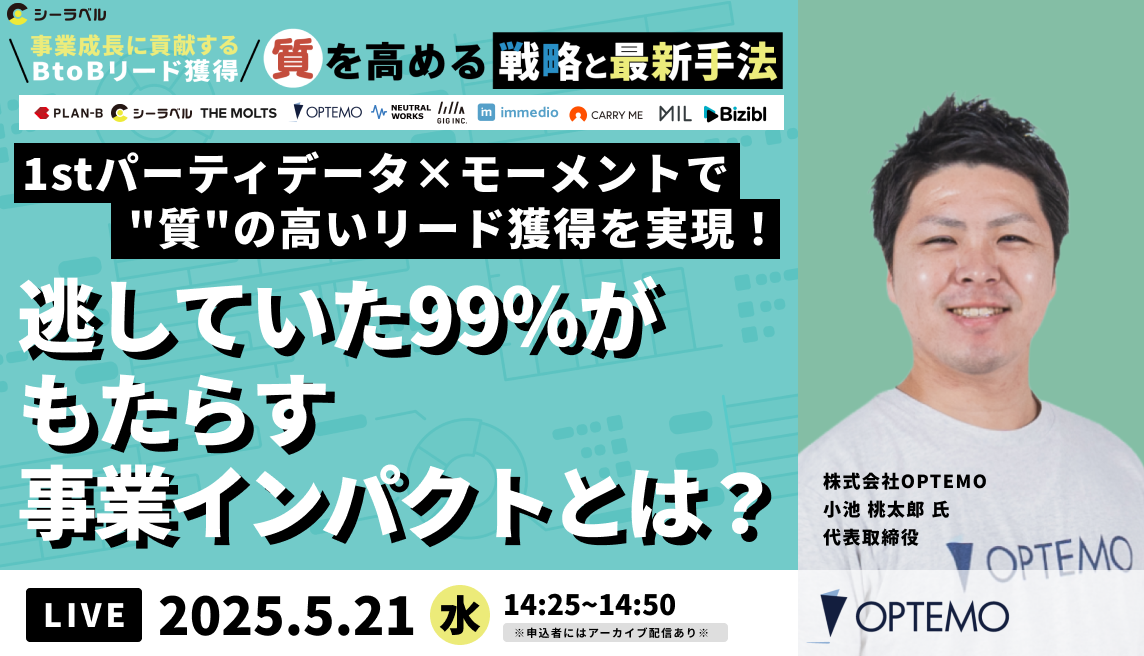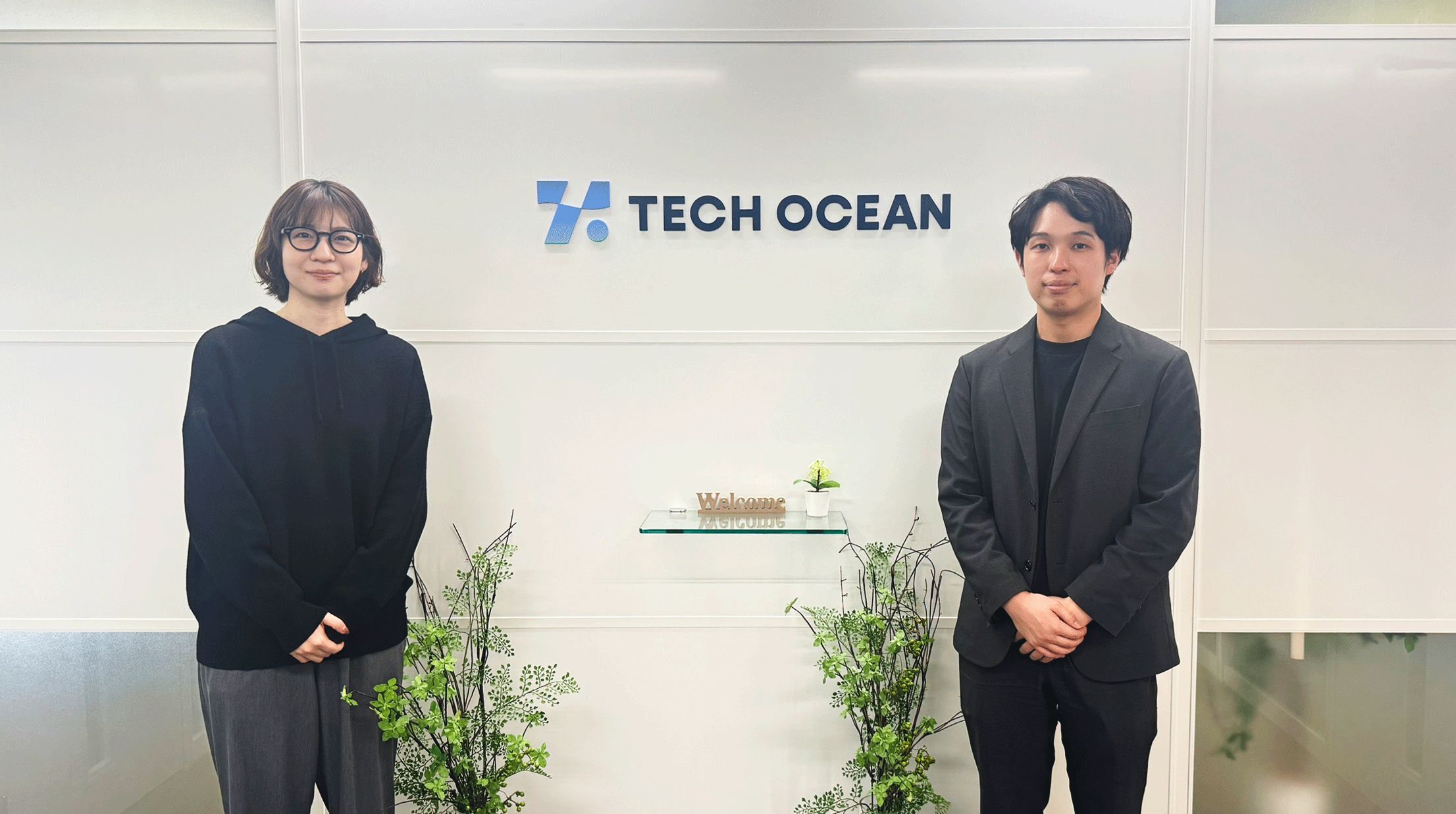BtoBマーケティングにおいて、CPAの高騰は多くの企業が直面している課題です。コロナ前には1万〜2万円で獲得できていたリードの取得単価が大幅に上昇し、従来の手法では成果を出すことが困難になっています。
そこで株式会社OPTEMOと株式会社FREE WEB HOPE(フリーウェブホープ)の2社は、BtoB向けのマーケターを対象とした実践的な交流会を開催しました。本レポートでは、6月12日(木)に渋谷にて開催されたセミナーの内容をお伝えします。
登壇者の紹介
【竹田 翔様】
株式会社FREE WEB HOPE セールスコンサルタント
LP制作に強みを持つデジタルマーケティングの支援会社。BtoB・BtoC問わず、幅広い業種でCVR向上のサポートをしており、広告運用やデータサイエンスにも精通している。LPO伴走サービス「マジック」、ノーコードLP量産サービス「クリック」などを提供。
【小池 桃太郎】
株式会社OPTEMO 代表取締役
Webサイト訪問者の99%にアプローチするサービス「OPTEMO」を提供する、インサイドセールスの会社。リアルタイム訪問者可視化、チャット・音声通話機能、MA連携による最適タイミング通知、訪問者の社名・氏名自動特定などが可能。
【竹田 卓生】
株式会社OPTEMO マーケティング担当
※フリーウェブホープの竹田氏は「竹田様」、OPTEMOの竹田は「竹田(敬称略)」と表記して区別しています
CPAが高騰する3つの構造的要因
クリック単価は確実に上がった
セミナーの冒頭、小池は一つ目のテーマとして「BtoBマーケティングの現状」を挙げました。
コロナの流行前と比べるとCPAは高くなっており、「リスティング広告の場合、以前は1万円~2万円くらいが目安だった」と数年前を振り返ります。小池がマーケティングに注力していた時期では、「リスティングのクリック単価でどうすれば100円台に収まるか」が課題でした。しかし「今(2025年現在)は200円~300円になっていたり、CPAの高いキーワードでは1500円だったりする」という状況です。
小池は竹田・竹田様の両名に、最近のCPAの傾向をどう捉えているか尋ねました。竹田様は「おっしゃる通り、本当に高くなっている」と回答。続いて竹田も「弊社のCPAが高いのかと考えていたが、他社も同じような感覚のようだ」と述べました。
参加者に対して実施したアンケートでは、「高くなった」という回答が大多数を占め、現在の水準は1万円から3万円がボリュームゾーンという結果でした。中には「変わらない」と答える参加者もいましたが、「オウンドメディアを活用していないゆえの結果かもしれない」と分析しています。
“人口減×競合増×AIの普及”がGoogle検索の減少をもたらした
CPA高騰の背景について、竹田様は構造的な要因を指摘。「日本は人口が減少傾向にある。すると検索をする方も減るというシンプルな話です」と述べ、人口減による検索ユーザーの先細りを挙げました。さらに情報を得る手段が多様化し、YouTubeやSNSなどが新たな検索ツールになりつつあることも影響していると付け加えています。
さらに「コロナ以降、特にBtoB領域のプレイヤーが増えている」と競合の増加を指摘。竹田様は「THE MODEL(ザ・モデル)の影響は大きく、各企業のマーケティングに対する意識が高まっている」と分析しています。
小池は別の角度から、「もうGoogleに新たな発見がない。AIが進歩した分、Google検索で目新しさを感じなくなった」とGoogle検索自体の価値変化について言及しました。
CPA高騰の要因について議論が深まる中、小池はさらにCookie(クッキー)の規制にも話題を広げ、どのくらい影響があったかと質問を投げかけました。竹田様は「ゼロとは言わないがほぼなかった」、竹田からも「あまり影響は感じない」という回答がありました。
CPA至上主義の罠【成果測定の基準とは】
CPAと受注数は必ずしも比例しない
続いては、CPAという指標の限界について具体的な事例を交えつつ議論が行われました。竹田はスライドで施策の一覧表を映し、CPA5,000円の施策Aで受注が1件、CPA20,000円の施策Cで受注が5件という例を提示しました(いずれも予算は100万円)。
この場合、CPA単価だけで判断すると施策Aが最優秀に見えます。しかし実際の受注数で評価すると、CPA20,000円の施策Cが5件受注と最も成果を上げており、ROIの観点では施策Cが最適解となります。
さらに竹田は判断の難しさについて「リードタイムが最低3ヶ月かかる中、マーケティング部門は既に次の施策に着手しており、振り返り評価のタイミングが難しい」と現実的な課題を指摘しています。
小池は会場にアンケートを取り、各社のCPAがどの程度かを質問。それからとある調査結果を踏まえて「10,000円~15,000円が最も多いらしい」と述べました。
その数字を受けて竹田様は、「CPAが3万円とか5万円の現状を受けて、マーケターが自己防衛のためにアクションのハードルを下げて、実は資料請求をしている状態で1万円なのでは」と業界の実情を明かしました。
マーケターとセールスは対立しやすい
実際の数値を用いた事例として、竹田様は自社の動画広告の結果を紹介しました。「CPA2,000円以下で100件ぐらい取れたが、2週間ぐらいかかって商談が4件程度、商談率が4%くらい」と説明。
一方で「リスティングの時は3件中2件が商談につながり、そこから1件受注につながることもある」と比較し、「その状態で予算を上げようとはなかなか決断できない」と判断の困難さを語りました。
小池氏は「商談率が上がらないと予算アップの相談は難しい」と同調し、組織間の対立リスクについて「ややもすると“マーケター対セールス”の構造になってしまう。マーケ部門からは『こんなにいいリードを取っているのに、なぜ受注につながらないのか?』と不満の声が上がりかねない」と警鐘を鳴らしました。
顧客を起点とするマーケティングの実践
「顧客の声が正解」という考え方
二つ目のテーマとして、小池は「CPAが高いなかで成果を最大化するにはどうしたらいいのか」という質問を会場に投げかけました。
成果を最大化するためのアプローチとして、竹田は「正解とはお客さんが考えていること」と顧客起点の重要性を強調。具体的な取り組みとして、「交流会の展示会でお客様にヒアリングして、得られた情報を施策に落とし込む」ことを実践していると紹介しました。
竹田様によると、「商談のリマインドのご連絡をする際に弊社の動画のURLを送るのですが、事前に確認してくださる方は受注率が高い」とのこと。また、顧客の前提知識向上についても「生成AIに質問すれば、Webサイトに載っている情報を引っ張ってこられる。問題は情報が正しいかどうかですが、サービスに関する知識を知っている前提で話を聞かれる」と現在の環境変化を指摘しています。
小池氏は「マーケティングの現場では“ターゲットとリード”は分けて考えがちですけど、実はそこの掛け算で、温度感や興味の度合いをちゃんと見ていかないといけない」と総合的な視点の必要性を述べました。これに対して竹田は「それだけでは足りないかもしれない」と更なる深掘りの必要性を示唆しています。
5つの質問で分かる「顧客起点度」診断
続いて竹田は、顧客起点のマーケティングを実践するためのチェックリストを紹介。おもな確認項目として、商談同席の有無・導入後顧客との接触・失注理由のフィードバック・営業とマーケティングの連携体制・顧客の生の声を収集する機会の設定という5つを挙げました。
その場で小池が会場にアンケートを取ったところ、参加者の中で失注理由のフィードバックを実践している企業は1社のみでした。つまり多くの企業において、マーケティング施策を改善する余地があることを示しています。
竹田様は商談に同席する価値について「商談でのいわゆるキラーフレーズ、キラートークを学べる。これらを活用できれば成果が出やすい」と説明し、「実はマーケとセールスのペルソナは若干ずれている」という課題についても指摘しました。
ライトコンバージョンと購入意欲の関係性
セミナー中に行われた実証実験では、参加者の実際の温度感が明らかになりました。「今日ここに来るまでに、オプテモかフリーウェブホープか、どちらかの会社を調べて『このサービスの説明をぜひ聞きたい、購入検討を前提で聞きたい』と思って来られた方はいらっしゃいますか?」と竹田様が問いかけたところ、該当者はゼロでした。
一方で「どちらかの会社のウェブサイトをすでに見た」という参加者は多く、竹田様は「これがリアルな温度感ですよね。まさにライトコンバージョン(契約に至る前の成果)の好事例で、情報を見ていただいてはいるけど、この場での購入はまずない。だからこそナーチャリングしつつ第一想起をどれくらい取れるかが重要」とまとめました。
セミナーに参加する動機はさまざまですが、購入検討以外の動機(情報収集、ネットワークの形成など)が大多数であるケースはよくあるといえます。
【質疑応答】セールス・マーケの連携とKPI設計の課題とは
質疑応答では、参加者から「リード数だけでマーケターを評価すると、とりあえず数を稼ぐために質の良くないリードも集めてしまいますよね。営業とマーケが共通のゴールを目指すために、どんなKPI設計をされていますか?」という質問が寄せられました。
竹田はより端的に「受注や売り上げなど、リードだけ見てもおそらく全然評価されない。基本的にリード数は見ていない」と自身のKPI設計について説明しました。
竹田様は「弊社では変な数字は取ってきていない。受注率とかCVRとか、おそらく共通の要素を見ている」と回答。「リードの温度感、いわゆる質の部分」を重視しているとのことでした。また、組織間の認識統一について「同じ言葉を使っていても、部署間や個人によっても捉え方が若干ずれる」という課題を指摘し、共通言語の認識をそろえる重要性についても言及しました。
まとめ
このセミナーを通じて、以下のポイントが明らかになりました。
・CPAの高騰は一時的な現象ではなく、人口減少や競争激化による構造的問題である
・評価指標もCPAから受注率・売上まで含めた総合評価が必須になってきている
・顧客起点思考の重要性、つまりマーケターの仮説より顧客の実際のニーズを重視する姿勢が大切である
・営業連携の価値、失注理由のフィードバックや商談同席による学習効果を体感すべき

本イベントレポートの内容が、マーケティングの業務に役立てば幸いです。ぜひご活用ください。