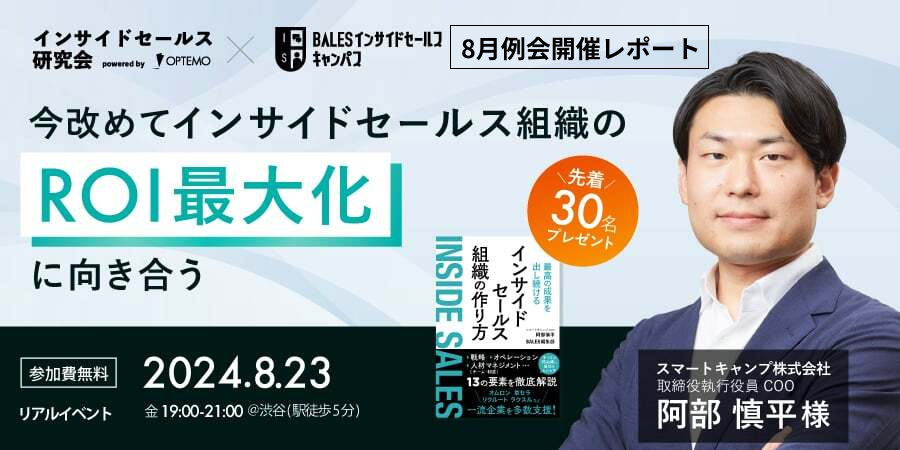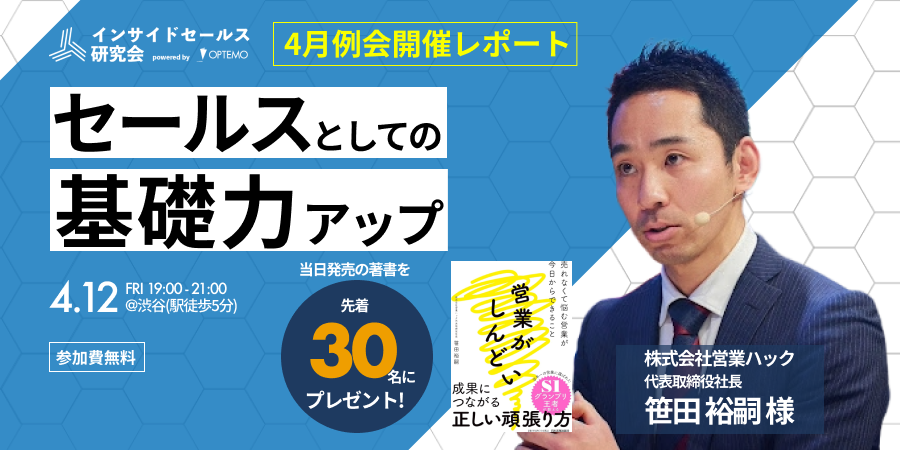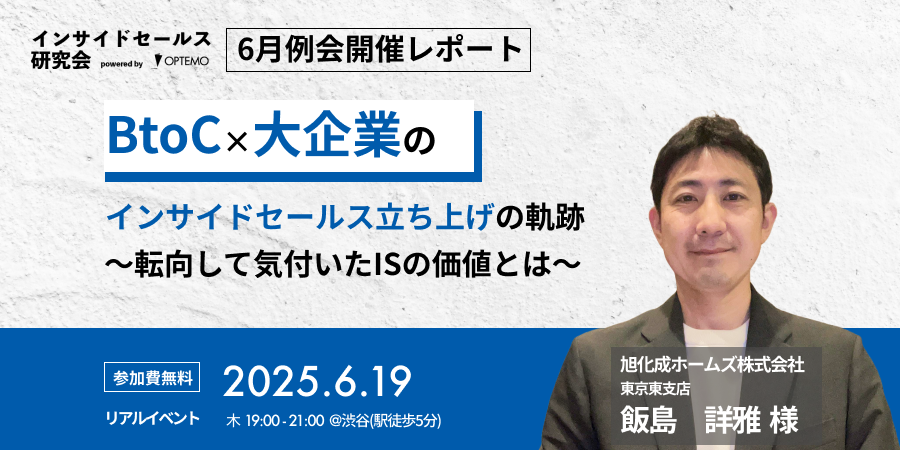インサイドセールス研究会2025年7月例会レポート
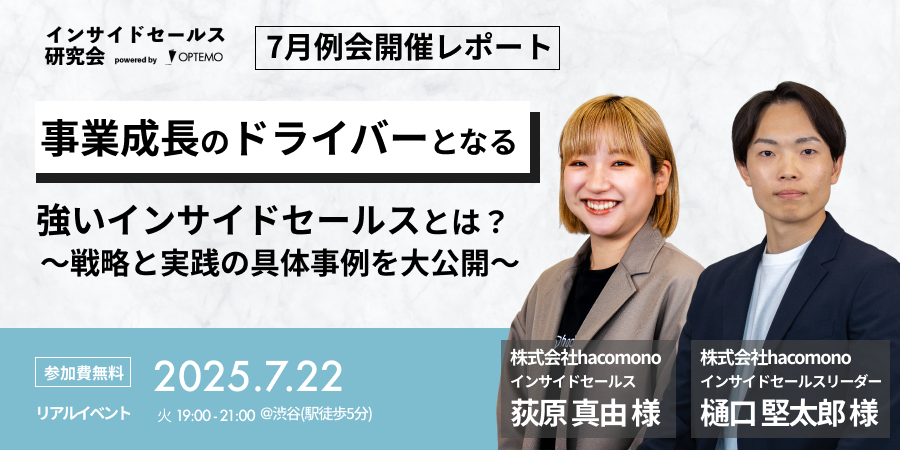
目次
インサイドセールス研究会について
インサイドセールス研究会は、『会社を超えてインサイドセールス同士がつながり「師と友」を作れる場』として株式会社OPTEMOが運営しているコミュニティです。
インサイドセールスという業務の性質上、社外での横のつながりが少ないという声を受け、2023年3月からこのコミュニティの運営を始めました。毎月特別なゲストを迎えて実践的なノウハウを提供しています。また、Facebookのグループで情報発信もしており、誰でも無料で参加できます。
https://optemo.co.jp//lp/is_ken
今回のテーマ
今回のイベントでは、株式会社hacomonoの樋口堅太郎様・荻原真由様をゲストにお迎えしました。「事業成長のドライバーとなる強いインサイドセールスとは?戦略と実践の具体事例を大公開」というテーマで登壇していただきました。
モデレーターはOPTEMO代表の小池桃太郎(@MomotaroKOIKE)が務めました。
樋口様・荻原様ご講演

樋口様は株式会社hacomonoのインサイドセールス部のリーダーであり、MMBとエンタープライズのお客様を担当されています。新卒で光通信系の会社に入社し、美容室と飲食店向けのPOSレジやCRMシステムの新規営業を経験。hacomono入社後は一貫してインサイドセールスに従事し、直近ではスイミングスクール、英会話スクールなどへのGTM(GoToMarket)推進も担当されています。

荻原様は株式会社hacomonoのインサイドセールス担当で、前職では初のISとしてチームの立ち上げに携わってこられました。リファラル経由でhacomonoに入社し、現在はIS以外の様々な業務にも取り組まれています。
当日のイベントでは、以下のトピックについてお話しいただきました。
・hacomonoの成長軌跡とキャズムの壁
・現場課題から事業課題への訴求転換
・従来のBDR手法を超える多様なアプローチ
・限られたリソースで最大成果を生む仕組み
hacomonoの成長と立ちはだかるキャズムの壁
急成長するSaaS企業が必ず直面するといっても過言ではないのが、「キャズムの壁」です。新規事業を推進するにあたって顧客層が変化するのは必然であり、その変化に対応するには一筋縄ではいかない工夫が必要です。

hacomonoはウェルネス産業(フィットネス、スクール業界など)に特化したバーティカルSaaSに強みがあります。「人がより楽しく、元気に、幸せに生きていく」をウェルネスと定義し、BtoBtoCのサービスを通じて事業者向け管理サイトとエンドユーザー向けメンバーサイトの両方を提供しています。
3年前のサービス導入店舗数は1500店ほどでしたが、2025年7月現在では1万店舗近くまで規模が拡大。大手企業やJリーグクラブ、Bリーグクラブ、NPB球団も導入しています。店舗運営に必要な入会手続き、予約システム、月会費決済、QRコード入退館システムなどを一元的に提供しているのが特徴です。
ホリゾンタルSaaSとの違いとして、特定業界に深く特化することで事業経営まで踏み込んだ提案が可能である一方、顧客数が限られる課題も存在します。
樋口様は2022年5月の入社当時について、「当時はPMF(プロダクトマーケットフィット)状態で問い合わせによる流入が多数ありました。5分以内にアプローチすれば高い商談化率を実現できる状態でした」と振り返ります。
しかし顧客層の変化に伴い、従来手法の限界が徐々に顕在化してきました。
「インバウンドリードが頭打ちとなり、アウトバウンド手法での商談化率も低下してきました。これまでの手法では、新しい顧客層にアプローチできないことが明確になったといえます」と樋口様は当時の課題を説明しました。
現場課題から事業課題への訴求転換
キャズム突破のために、hacomonoが行った最も重要な対策は訴求内容の変更でした。従来は現場の実務課題に対するソリューション提案を行っていましたが、事業課題への訴求に転換したことで変化が生じました。
訴求内容の抜本的な見直し
従来の現場課題への訴求では、複数システムの一元管理やミス削減といった、実務レベルの困りごとにフォーカスしていました。しかし変更後は、事業課題として大手チェーンとの差別化や継続率向上といった、より戦略的な課題へと訴求内容を変更したのです。

樋口様は具体例として地方のフィットネスクラブの事例を紹介し、「大手に負けない継続率の実現」をあるべき姿として訴求するようになったと述べました。問題解決に有効とされるフォーマットを活用して、「問題=あるべき姿と現状のギャップ」として定義したうえで、顧客のあるべき姿を積極的に訴求する手法を導入したのです。
「従来のアプローチでは、お客様の関心を十分に引くことができませんでした。しかし事業課題に切り替えることで、経営者レベルの方々にも響く提案ができるようになったのです」とも樋口様は語っています。
徹底した顧客分析とアプローチ
事業課題への訴求転換と合わせて、hacomonoでは顧客理解の深化にも力を入れました。自社から提案した内容への共感度を高めるために業界の分析を徹底的に行い、自社の事業との親和性を感じられる訴求を提案しています。

競合分析と立地分析の実施では、Googleマップを活用した商圏分析により競合店舗の配置を把握します。さらに業界別の市場環境の変化についてもリサーチして、24時間営業のジムの増加やコロナの影響など、業界動向の理解を深めました。
樋口様は「すべてのお客様に対してこれだけ深く調べることで、説得力のある提案ができるようになりました。表面的な課題解決提案から、本質的な事業成長支援への転換が実現できたのです」とその効果を強調しています。
従来のBDR手法を超える多様なアプローチ
電話営業だけでは接触困難な顧客との関係構築は、多くのインサイドセールスチームが抱える共通の課題です。hacomonoでは、この課題を解決するために従来のBDR手法にとどまらない多様なアプローチを模索しました。リストの大胆な絞り込みや接触回数の増加など、関係構築につながる戦略は多々あります。
戦略的なターゲットの絞り込み

「すべてのお客様と会うのは難しい」という問題を解決するために、樋口様は大胆な作戦に打って出ました。顧客リストに目を通し、400社から100社への大胆な絞り込みを実施したのです。当時のMMB・エンタープライズ顧客は接触も困難で、パーソナルジムオーナーは店舗にいないことが多く、現状を鑑みての決断でした。
樋口様は「1回会っても商談につながらない」との判断から、3ヶ月で3回接触する戦略で関係性構築を重視する方針に切り替えました。営業対お客様という関係ではなく「仲の良い先輩と後輩」レベルの距離感を目指し、電話営業だけでなく対面での接触も活用した手法を導入したのです。
ISとFSが連携してお客様と会う機会を増やしたことで、パートナーセールスの機会創出につながりました。
メディアとイベントを活用した関係構築
hacomonoでは、自社メディアでの取材を通じた自然な接触機会の創出にも力を入れてきました。取材ではあえてサービスの売り込みをしませんが、「実はhacomonoが気になっている」と商談につながった事例もあります。

その他にも、懇親会やクローズドイベントでの業界関係者ネットワーク構築にも力を入れています。普段は競合関係にあるパーソナルジムのオーナー同士を集めたイベントで付加価値を提供し、既存顧客によるリファラル営業も活用しているとのこと。
「イベントや取材などによって接点を持つことで、従来の営業アプローチでは会えなかった方々とも関係を築けるようになりました」と樋口様は振り返っています。
SNSとパートナーセールスの戦略的活用
樋口様はInstagramを活用して契約につなげた事例も紹介しました。取材を通じて出会ったお客様とInstagramで相互フォローの関係になり、先方の投稿にリアクションすることでキープインタッチを実施。地道な努力を続けた結果、DMで「hacomonoの導入を検討したい」と連絡があり、商談から契約に至りました。
既存顧客を介した紹介営業の手法も効果的です。Xの投稿からクライアント同士が交流している様子を知り、紹介を依頼するといった取り組みも実施しています。『よければ繋いでいただけませんか?』と樋口様から紹介を依頼することで、新たな接点を創出した事例のひとつです。
SNSから得られる情報は、ときにビジネスを動かすきっかけとなります。樋口様は「うまく使うことで、タイミングを見計らったアプローチが可能です」とおっしゃっていました。
限られたリソースで最大の成果を生む仕組み
スタートアップ企業にとって、限られたリソースで高い目標を達成することは最大の課題といっても過言ではありません。hacomonoでは、受注金額・受注率・商談化率の高い顧客に社員リソースを集中的に投下する体制を構築しました。
社内独自の「期待MRR指標」の導入、営業代行をとり入れた二次架電モデル、派遣社員との効果的連携など、あらゆる方法を駆使。商談品質を担保しながらの効率的なリソース活用により、少ない人員で成果を生み出しています。
「期待MRR指標」によるKGI設定
「期待MRR」とは、hacomonoの社内で使われている独自の指標です。リードソース・顧客の業種・事業形態の3つを組み合わせて算出されます。

この期待MRRが設定された背景には、FSの目標達成率とISの受注目標の乖離がありました。
具体的にはリード数の増加率と商談数の伸びが合致せず、樋口様は「なぜこういう状況になるのか?」と悩んだそうです。原因を分析したところ、商談化率の低いホワイトペーパーリードにアプローチが集中していたことが判明。そこで期待MRRを設定し、商談化率が高そうな顧客にリソースを統括したのです。
業種に関しては、フィットネス業界内でもPMFの度合いや単価の違いを考慮するとのこと。事業規模は基本的に店舗数で判断しており、系列の店舗が多いほどMRRを期待できるという考え方です。
電話アポと二次架電モデルで品質と効率を両立
電話アポの活用も、hacomonoにおけるインサイドセールスの特徴です。
「資料請求したけど商談するほどではない」「料金や機能について簡単に聞きたい」というケースはよくあります。そこで資料請求から商談につながっていない顧客に対して、電話アポを打診する仕組みを導入しました。
事前に指定した日時に連絡するためコンタクト率が非常に高く、事前アンケートによる準備も万全です。営業代行による商談品質の向上には限界があると判断し、商談の成立ではなく電話アポへとコンバージョンポイントを変更しました。
営業代行にFSのアポ取りを任せ、社内のIS担当が商談化するという二次架電の流れを構築することで、商談の品質担保と社員ISのリソース確保の両立を図っています。
社外の人材と連携した戦略的チーム体制

hacomonoでは、社員1人に派遣社員1人がつくペア体制をとり入れました。社員だけで捌ききれないWebリードに対応するため、社外の人材を積極的に活用。その他の営業代行の担当者を対象に、勝ちパターンとされるトークスプリクトに絞った徹底的なロープレ研修を実施しています。
なお、慎重な対応が求められるケースは、以前と同様に社員が直接対応します。一方、SMB(Small and Medium Business)顧客は派遣社員が担当することで、適切なリソース配分を実現しました。
樋口様は「外部の方々との連携では、役割分担を明確にすることが重要です。期待MRR指標を活用することで、どの顧客にどのレベルのリソースを投入すべきかが明確になりました」と振り返ります。
質疑応答

講演後の質疑応答では、参加者から実践的な質問が寄せられました。
Q1. チームマネジメントと採用戦略について
【参加者からの質問】
営業チームのマネジメントや教育で一番大事なのは人だと思います。カルチャーフィットや教育、採用面接でどのような人材を選ぶか、またどのようにマネジメントしているか教えてください。
【樋口様の回答】
入社時点で伸びしろがあれば良いと考えています。スキルよりも「素直で元気で気持ちいい人」かどうかが評価ポイントですね。負けず嫌いな特性も重要で、スポーツで結果を出してきた体育会系の人材が多い傾向にあります。
チームマネジメントで重要視しているのは、リーダーやマネージャーがしっかりとチームの旗を掲げることです。インサイドセールスは単調な業務の繰り返しになりがちなため、メンバーに対して「半年後までにこういう状態を目指そう」という目標を、月に1回程度の頻度で共有していますね。チームの目指している方向性を作っていくモメンタムを高めることを意識しています。
【荻原様の回答】
過去の経験からお答えすると、前職で新卒の受け皿的な役割を担っており、最終的には独り立ちしてトップセールスになってくれた若手が2人ほどいました。
意識していたのは、彼らの将来や人としての部分をしっかり見てあげることです。「上司やマネージャーが本当に仕事を楽しんでやっているか」「言わされてやっているのでは?」というのは周囲に伝わりがちです。対仕事・対会社・対社会人としての熱量をオープンにしていくことで、部下との良好な関係性を築けるのだと思います。
Q2. 人事評価制度の工夫について
【参加者からの質問】
人事評価で工夫していることはありますか?定量的な基準をどう設定しているか、評価の透明性をどう担保しているかもお聞かせください。
【樋口様の回答】
特殊なツールは導入していませんが、グレードと年収に応じてメンバーに求める能力を定義しようと試みています。たとえば年収が400万円の人と600万円の人では、同じ役割でも期待値が違ってきます。そういった差を明確にする取り組みが必要です。
またサプライズ評価にならないよう、期初・期中・期末だけでなく、月に1回程度は定期的に振り返りの時間を設けることも心がけています。
【荻原様の回答】
hacomonoに入って評価制度で面白いと思った点は、社員自身が目標を決めることです。前職では数字が評価の基準で、上司から指示された業務で結果を出す形でした。
hacomonoでは基本的に、みんな「100%やりきりました」と自己評価を出してきます。そのうえで、上司がグレードや年収に対して期待に見合った成果を出せたか最終的に判断する仕組みです。
個人的な意見として、上司の好みも評価の一部だと認識しています。チームのリーダーは上司なので、上司がイエスを出さない限りチームに貢献していないという判断になります。コミュニケーションで信頼を積みながら、納得感のある目標を設定することが大事ではないでしょうか。
Q3. 事業課題訴求の使い分けについて
【参加者からの質問】
訴求のポイントを実務課題から事業課題に変えたお話がありましたが、事業課題は相手にとって身近ではなく、わかりにくい部分もあると思います。商品の認知度がある前提での切り替えなのでしょうか?あまり事業内容が知られていなくても、事業課題に振り切るべきでしょうか?
【樋口様の回答】
結論として、提案する金額によると考えます。5万円の提案と50万円の提案では、解決する課題や価値が違うはずです。私が担当しているスイミングスクールやスポーツジムなどは1店舗で2000人という大きな規模なので、現場の問題解決だけではサービスを買ってもらえません。
また、相手の立場も重要です。フィットネスクラブのアルバイトスタッフに店舗展開の話をしても、おそらく効果が薄いですよね。基本的には目の前にいる人の課題を解決する必要がありますが、クライアントの企業に対する最終的な提案では、金額に応じた価値提案と商談相手を見極める視点が必要だと考えています。
【荻原様の回答】
私はSMB領域を担当していますが、電話をすると「何の会社ですか?」から始まることも多いです。それでも構わないと思っていて、そこから雑談を始めます。メンバーの中には1時間くらい電話する人もいて、電話がほぼ商談の状態になることもあります。
「よくわからないけど、良い人だから話を聞いてあげよう」という関係から商談につながるケースも珍しくありません。横のつながりが強い業界なので、「あの会社の人は良い人だからシステムも良いんだろう」という口コミで導入いただくケースもあります。そういうアプローチも一つの方法ですね。
交流会の様子

講演後の交流会では、バーティカルSaaSの事業課題訴求手法に対する高い関心が寄せられました。名刺交換の際には「PMFからキャズム突破への具体的アプローチが参考になった」という声が多数聞かれ、「弊社もバーティカル展開を検討しているので参考にしたい」との意見も寄せられました。
参加者の反応では「期待MRR指標の考え方が目から鱗だった」「メディア取材を営業手法として活用する発想が新鮮」「二次架電モデルで営業代行の課題を解決するアプローチが実践的」といった感想が多く聞かれました。
人事評価制度についての質疑応答では「自己目標設定型評価」にも注目が集まり、熱心に質問する参加者がいらっしゃいました。
インサイドセールス研究会の交流会では、毎回「新しい体験を提供する」というテーマのもと、参加者に特典としてちょっとした品物やサービスをプレゼントしています。今回は参加者の皆様へのお土産として、カヌチュロをご用意しました。「外はサクサク、中はとろっとしていて病みつきになりそう」「Z世代のトレンドを体験できて興味深かった」など、参加者の皆様から好評でした。

最後に
今回のインサイドセールス研究会では、バーティカルSaaSという特殊な事業環境における「リードの壁」と「リソースの壁」への対処法について、具体的な事例とともに学ぶことができました。
なかでも印象的だったのは、樋口様が示された「現場課題から事業課題への訴求転換」というアプローチです。PMF後のキャズム突破において、単なるソリューション提案から顧客の勝ち筋実現支援へとレベルを上げることで潜在層へのアプローチを可能にした事例は、業界を問わず応用できる貴重な知見でした。
期待MRR指標によるリソース配分や多様なチャネルを組み合わせた接触戦略、営業代行や派遣社員との効果的な連携モデルなど、限られたリソースで最大の成果を生み出すための工夫の数々は、多くの参加者にとって実践的なヒントとなったことでしょう。
本イベントの内容が、ご参加いただいた皆様の今後のインサイドセールス活動に少しでもお役に立てば幸いです。
次回のインサイドセールス研究会で、多くの参加者とお会いできることを楽しみにしております。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから