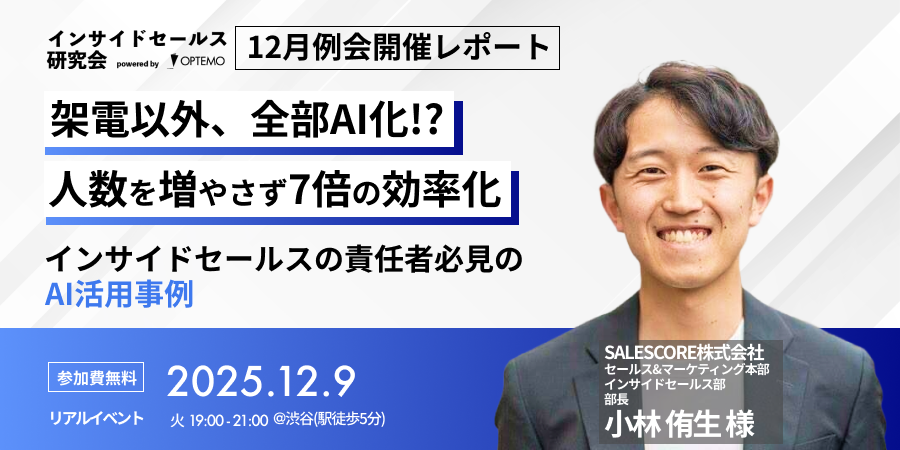サイトの離脱率を下げるツールとは?フォーム離脱を防ぎ確実にCVを積み上げるためのサービス9選

Webサイトに訪問したユーザーが、資料請求・購入・登録といったアクションに至る前に離脱してしまう…こうしたもったいない瞬間を見逃さないために、業種を問わず多くの企業が導入を進めているのが「離脱率を下げるツール」です。
本記事では、離脱率が高いことで起きる問題や、改善に向けたアプローチ、そして2025年に注目すべきツールを厳選して紹介します。
目次
離脱率が高いことで起きる問題

Webサイトにアクセスしたユーザーの多くは、訪問してすぐに離脱してしまうケースが少なくありません。これは「目的の情報にたどり着けなかった」「導線が分かりづらかった」など、初期段階でのUX上の課題が原因であることが多いです。
一方で、ページをしっかりと閲覧し、ある程度の関心を持った状態にもかかわらず、資料請求や問い合わせなどのコンバージョンに至る直前で離脱してしまうケースもあります。こうしたユーザーの取りこぼしは、明確なニーズがあったにもかかわらず逃してしまう大きな機会損失につながります。
コンバージョン直前のユーザーでも離脱が発生している
Webサイトに訪問して情報をしっかりと読み込んでいるユーザーの中には、商品やサービスに高い関心を持ちながらも、最終的な行動を起こす前に離脱してしまうケースがあります。
例えば、「資料請求」「問い合わせフォームの入力」「無料トライアルの申し込み」といった、CV(コンバージョン)の直前での離脱は、大きな機会損失につながります。
特にBtoB領域や高単価商材を扱う企業では、1件のリード獲得がそのまま数十万〜数百万円の契約に結びつくこともあるため、CV率の底上げに取り組むことが、事業成果の最大化に直結します。
離脱率が高いと継続的な訪問につながりにくい
ユーザーが最初に訪れたときに「わかりにくい」「目的の情報にたどり着けない」といった体験をしてしまうと、次回以降に再訪してもらえる可能性は低くなります。
離脱率の高さは、単にその場のCVを逃しているだけでなく、「次に期待される接点」すら失っている状態です。
ユーザーに問い合わせなどの具体的なアクションを起こしてもらうためには、初回訪問時の体験で不安や疑問を解消し、スムーズな導線と有益な情報提供ができているかどうかが重要です。
離脱ユーザーの声を拾えず、改善施策が場当たり的に
離脱率が高いにもかかわらず、その原因が把握できていない場合、改善施策は勘と経験に頼らざるを得ません。例えば「ここが問題かもしれない」と仮説を立ててページを修正しても、実際には的外れな対応となり、成果が出ずに終わることもあります。
ユーザーがどこでつまずき、なぜ離脱したのかを定量的・定性的に捉えられていない状態では、PDCAも回らず、場当たり的な改修を繰り返す悪循環に陥ってしまいます。
ABテストの検証データが集まらず、PDCAが回らない
Webサイトの改善では、ABテストによって複数のパターンを比較・検証し、効果の高いものを採用していくのが理想的なアプローチです。
しかし、離脱率が高すぎるとテストに必要なサンプル数が確保できず、統計的に有意な差を見極めるのが困難になります。
その結果、「結局どちらが良かったのか判断できないまま」「改善効果が曖昧なままリリースしてしまう」といった課題が発生し、PDCAの精度やスピードが大きく損なわれてしまいます。
離脱率を下げるための主なアプローチとは

Webサイトの離脱率を下げるためには、ユーザーの行動や心理を正しく理解し、的確な対策を講じることが欠かせません。
ここでは、実際の改善施策として効果の高い4つのアプローチを紹介します。
EFO(入力フォーム最適化)で入力完了率を改善
離脱の多くは「フォーム入力時」に発生しています。住所や電話番号などの項目が多すぎたり、入力エラーがわかりにくいと、ユーザーは途中で離脱してしまいます。
EFO(Entry Form Optimization)は、こうした課題を解決するための取り組みです。例えば次のような工夫が挙げられます。
- 入力項目の最小化(本当に必要な情報だけを求める)
- ステップ形式での分割(一度に全項目を出さず、段階的に進める)
- 郵便番号からの住所自動補完
- リアルタイムのエラー表示やアシストメッセージの表示
これにより、ユーザーが迷わずスムーズに入力を完了でき、離脱を防ぐ効果が期待できます。
チャットやポップアップによるリアルタイム接客
ユーザーがサイト訪問していてアプローチ可能なタイミングで接点を持てれば、CVにつながる可能性は大きく高まります。この瞬間に機能するのが、Webチャットやポップアップによるリアルタイム接客です。
例えば以下のようなケースが効果的です。
- 滞在時間が長いページでのチャット表示(迷っている証拠)
- 離脱直前のカーソル移動を検知してポップアップ表示(「離れますか?」という最終確認)
- FAQ表示や有人チャットでの質問受付(不安を即時解消)
特に、チャットボットだけでなく有人チャットによる対応ができる場合は、ユーザーのニーズに応じた柔軟なやり取りが可能となり、商談化の確率も高まります。
ヒートマップで課題を「見える化」
ユーザーが「どこで止まり」「どこを見ていないか」を感覚ではなくデータで把握するために役立つのが、ヒートマップツールです。
ヒートマップを使うと、次のような視点でページ改善のヒントが得られます。
- スクロール率が急激に下がる位置(情報の分断や離脱の兆候)
- クリックが集中しているエリア/されていないCTA
- 滞在時間が長い箇所=関心がある部分の発見
こうしたデータをもとに、導線やボタン配置、ページの構成を見直すことで、ユーザーの離脱を防ぐ設計がしやすくなります。
LPOやA/Bテストでページ構成を最適化
離脱率が高い場合、そもそもランディングページ(LP)自体の内容がユーザーの期待とずれていることも多くあります。そこで重要なのが、LPO(Landing Page Optimization)とA/Bテストの活用です。
LPOでは、訪問ユーザーの属性や流入元に応じてページ内容を最適化します。
例えば、
- 広告経由で訪れたユーザーには訴求点を明確に表示
- スマホユーザーにはCTAボタンを目立つ位置に配置
- 業種別にヘッダーやファーストビューを出し分け
さらにA/Bテストを重ねることで、コピーやCTAの文言、色、ボタン配置などを検証し、効果の高い構成へと改善を積み重ねていくことが可能です。
失敗しないツール選びのポイント

離脱率改善のためにツールを導入する際は、「とにかく機能が多ければ良い」というわけではありません。自社の課題や運用体制に合ったものを見極めることが大切です。
ここでは、ツール選びで押さえておきたい3つの視点を紹介します。
目的と課題に合った機能を備えているか
ツールによって得意とする領域は異なります。例えば、フォームの途中離脱を防ぎたいならEFO特化型、ユーザーとの対話でCVに導きたいならチャットツール、行動データを活用した改善を重視するならヒートマップやLPOツールなどが候補に上がります。
また、同じチャットツールでも「問い合わせ対応に強いボット型」と「商談化に向けた接客ができる有人型」では役割がまったく異なるため、自社が解決したい課題にピンポイントで対応できるかどうかを必ず確認しましょう。
導入・運用のハードルは高すぎないか
「良い機能が揃っていても、導入に時間がかかる」「設定が複雑で社内に運用できる人がいない」といった状態では、ツールを持て余してしまいます。
例えば以下の点は、事前にチェックしておくと安心です。
- タグを埋め込むだけで導入できるか
- 初期設定や運用フローをサポートしてくれる体制があるか
- 運用を内製化したいのか、外部に頼りたいのか
担当者の工数をどこまで割けるかに応じて、無理なく継続できるツールかどうかを見極めることが、失敗を避けるカギです。
既存のマーケティングツールと連携可能か
すでにCRMやSFA、MAツールなどを活用している場合は、そのツールと連携できるかどうかも大切な判断基準です。
例えば、チャットツールで得た会話データをSalesforceに自動で記録できれば、営業チームとの連携がスムーズになり、リードの取りこぼしを防げます。逆に、連携ができないとデータが分断され、運用の手間やミスが発生する可能性も。
導入時には、自社のマーケティング基盤との親和性を必ずチェックしましょう。
離脱率を下げるツールおすすめ9選【2025年版】

離脱率改善に取り組むうえで重要なのは、自社の課題やサイトの構造に合ったツールを選ぶことです。
ここでは、フォーム離脱や途中離脱を防ぐために役立つ、注目のツールを9つ厳選して紹介します。
KARTE(カルテ)
ユーザーの行動や属性に合わせて、より良いタイミング・方法でアプローチできるWeb接客ツールです。
KARTEは、Webサイト訪問者の行動データをもとに、ポップアップやバナーなどの要素をリアルタイムで出し分けることが可能です。ページの閲覧状況やスクロールの深さ、滞在時間などを活用してユーザーをセグメント化し、パーソナライズされた接客ができます。
- ページ遷移・滞在データに基づく精度の高い出し分け
- 離脱直前のアクションをトリガーにしたポップアップ配信
- ECやSaaS企業を中心に導入実績が豊富
向いている企業: 高度なユーザー行動分析とセグメント配信にこだわりたい企業
SATORI(サトリ)
匿名ユーザーにもアプローチできる、国産のマーケティングオートメーションツールです。
SATORIは、まだフォーム入力をしていない匿名ユーザーに対しても、ポップアップなどを通じてアプローチできる点が大きな特徴です。サイト訪問者の行動履歴に応じたシナリオ設計により、段階的なリード育成(ナーチャリング)も可能です。
- 見込み顧客の離脱を防ぐポップアップ施策
- 顧客の状態に応じた多段階シナリオの構築
- 1,000社を超える導入実績
向いている企業: 匿名ユーザーを獲得し、リードに育てたい企業
HubSpot(ハブスポット)Live Chat
CRMと連携しながら、無料で使えるチャットツールです。
HubSpotのLive Chat機能は、見込み客がサイト上で疑問を持ったタイミングで、チャットを通じて即時に対応する仕組みを提供します。取得したデータはHubSpot CRMに自動で蓄積され、そのまま営業プロセスへ連携できます。
- 自動メッセージでフォーム送信前の離脱を防止
- CRM・セールス機能とシームレスに連携
- 無料プランから始められ、小規模チームでも使いやすい
向いている企業: すでにHubSpotを活用している、またはCRM一体型で運用したい企業
Salesforce(セールスフォース)Experience Cloud
顧客接点全体のUXを改善できる、SalesforceのCMS/コミュニティ機能搭載プラットフォームです。
SalesforceのExperience Cloudは、CRMで蓄積されたデータをもとに、サイト訪問者ごとに最適化されたコンテンツやナビゲーションを提供できる点が特徴です。問い合わせ前の情報提供やセルフサービス型サポートを充実させることで、離脱防止やCVR改善につながります。
- CRMデータを活用した動的コンテンツ出し分け
- サイト構築・コミュニティ構築がノーコードでも可能
- Salesforce Marketing CloudやSales Cloudとの連携で営業・マーケを一元化
向いている企業: Salesforce環境を活かし、顧客体験を統合的に設計したい中〜大規模企業
Zendesk Chat(旧Zopim)
カスタマーサポートに強みを持つチャットツールで、UX改善や離脱防止にも活用できます。
Zendesk Chatは、ユーザーがページ上で迷ったときに質問しやすいUIが特長です。FAQ的なやりとりに加えて、担当者との有人対応への切り替えも可能。多言語・グローバル対応も進んでおり、サポート領域を強化したい企業に適しています。
- 会話型UIでUXを改善し、離脱を抑止
- ボット対応との組み合わせで柔軟に活用可能
- 多言語対応による海外ユーザーサポートにも
向いている企業: サポート重視の企業や、UX改善を狙う中〜大規模サイト
TETORI(テトリ)
サイト訪問者の行動データを活用し、離脱前に訴求できる軽量Web接客ツールです。
TETORIは、訪問者のスクロール率や滞在時間などをもとに、チャットボックスやバナー、ポップアップなどを表示して行動を促します。導入が比較的手軽で、マーケティングに不慣れなチームでも始めやすい点も魅力です。
- 離脱直前のアクションに反応する施策設計
- クーポン表示やキャンペーン連動も柔軟に対応
- ノーコードで操作しやすく、中小企業でも使いやすい
向いている企業: 費用を抑えて、キャンペーンや販促でCVRを改善したい企業
Chat Plus(チャットプラス)
低コストでスタートできる国産チャットツール。有人・自動対応の切り替えも可能です。
Chat Plusは、導入しやすさと柔軟性を兼ね備えたチャットツールです。必要な機能を選べる料金体系で、スモールスタートしやすい点が特長。AIチャットボットだけでなく、オペレーターによる対応も簡単に切り替え可能です。
- 最小構成なら月額1,500円から利用可能
- Salesforceなど外部ツールとの連携も対応
- チャットウィンドウのカスタマイズ性も高い
向いている企業: 初めてチャットを導入する中小企業や、コスト重視の企業
QUALTRICS(クアルトリクス)Webサイトフィードバック
UX改善やサイトリニューアル前のリサーチに活用できる定量調査ツールです。
QUALTRICSは、ユーザーがサイトから離脱する直前にアンケートを表示するなどして、「なぜ離れたのか?」という定性的な声を拾うことができます。顧客体験の可視化に役立ち、仮説に基づく施策ではなく、根拠のある改善が可能になります。
- 離脱前アンケートで“理由”を取得できる
- 回答データをもとにUX改善の方向性を明確化
- リニューアル時のベースデータ収集にも活用
向いている企業: UX部門を持つ大手企業や、CXに力を入れたい組織
OPTEMO(オプテモ)
問い合わせ前に今すぐ接客できる、BtoBをはじめとしたさまざまな業種に対応可能なリアルタイムWeb接客ツールです。
OPTEMOは、サイトに訪問した見込み客の行動をリアルタイムに可視化し、その場でチャットや音声通話によるアプローチを可能にする、有人型のWeb接客ツールです。
フォーム送信や予約不要で、営業担当が即時対応できる仕組みが最大の強みです。
- ページ閲覧中のユーザーにその場で話しかけてCVを創出
- CRM(Salesforce・HubSpot等)と連携し営業効率を最大化
- 導入後は専任担当が伴走し、効果改善まで支援
向いている企業: フォーム離脱率やCVRに課題を感じている企業(業種・業態問わず)/BtoB・BtoCを問わず高温度のリードを取りこぼしたくない企業
OPTEMOが選ばれる理由とは?
OPTEMOは、従来の問い合わせを待つ型の営業スタイルから脱却し、サイト訪問中のユーザーに今すぐアプローチできるという強みを持ったWeb接客ツールです。
特にBtoB企業や高単価商材を扱う企業で、確度の高いリードを逃さず獲得できる点が、多くの支持を集めています。
問い合わせを待たないWeb接客でリードを逃さない
OPTEMO最大の特徴は、Webサイト上で「誰が」「どのページを」「どのくらいの時間見ているか」をリアルタイムで把握し、フォーム送信前の段階でこちらから声をかけられることです。
従来のように、資料請求や問い合わせフォームをユーザーが見つけてくれるのを待つのではなく、関心が高まっているその瞬間にチャットや音声通話を通じてコンタクトを取ることで、リードの取りこぼしをできる限り抑えられます。
特に競合サイトが多い領域では、このワンテンポ早い接点が、CV獲得に大きく影響します。
チャットボットでは対応しきれない営業現場に強い
よくあるチャットボットのように、あらかじめ用意されたシナリオに沿って機械的な対応をするのではなく、OPTEMOは有人による柔軟な対応が可能です。
「担当者によるヒアリング→即ヒント提示→必要に応じて商談設定」といった、人ならではの判断・提案力を活かした対応ができるため、BtoB営業においても信頼を得やすく、商談化率を高めることにつながります。
これにより、「温度感の高いリード」を見極めながら、無駄な接客や工数を抑えつつ効率的な営業活動が実現できます。
専任担当が伴走し、PDCA改善まで支援
OPTEMOは単なるツール提供にとどまらず、導入企業ごとに専任の担当者がつき、継続的な効果改善を支援します。
ツールの初期設定やシナリオ設計はもちろんのこと、接客データの分析、改善施策の提案、運用の見直しに至るまで、導入企業の状況に応じて柔軟にサポートが受けられるため、「ツールを入れたけど使いこなせなかった」というよくある失敗を防げます。
特に社内にWeb接客やマーケティングの専任担当がいない企業にとっては、成果が出るまで伴走してくれる安心感が高く評価されています。
まとめ|ユーザーを理解し、すぐに動ける体制づくりが重要

離脱率の改善は、単にページデザインやコンテンツを見直すだけでは不十分です。特に、フォーム送信まで到達しないユーザーにどう接点を持つかが、CVR(コンバージョン率)や商談獲得数に大きく影響します。
その点で、OPTEMOのように「リアルタイム × 有人対応」を組み合わせたWeb接客ツールは、あらゆる業種で離脱前の接点を創出する手段として、これからのWebマーケティングにおいて大きな武器となるでしょう。
なお、以下の資料では、OPTEMOの具体的な機能や活用事例、導入企業の声などを詳しく紹介しています。「問い合わせが来る前に接客できる仕組み」とはどのようなものか?ご興味のある方は、ぜひお気軽に資料をご請求ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから