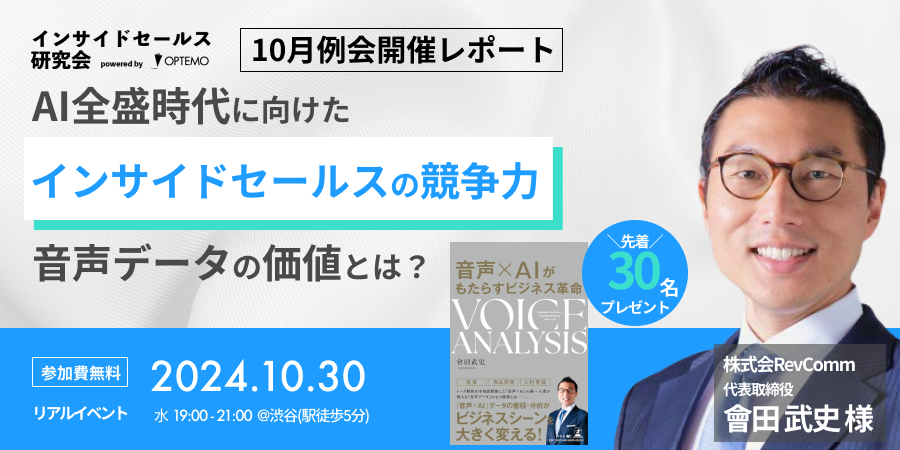チャットボットの種類|特徴と自社に合わせて選ぶ方法を解説

チャットボットには、AIを搭載した高機能なものから、決まったルールに沿って応答するシンプルなものまで、さまざまな種類があります。
種類ごとに得意なことが異なるため、自社の目的に合わないものを選んでしまうと、期待した効果が得られない可能性があります。
本記事では、チャットボットの種類を「AIの有無」で分類した上で、それぞれの種類を解説します。自社に適したチャットボットの種類を探す際の参考にしてみてください。
目次
チャットボットの種類【AIの有無】
チャットボットは、まずAIの有無によって次の3種類に分けられます。
- AIチャットボット
- 非AIチャットボット(ルールベース型)
- 有人型
それぞれの特徴を詳しく解説します。
AIチャットボット
AIチャットボットは、ユーザーが入力した自由記述を解析し、自動で回答を導き出すタイプです。入力の意図をくみ取って返答できるため、定型文に縛られない対話が可能になります。
例えば「資料が欲しい」「導入費用を知りたい」など、ユーザーによって表現にバラつきがあっても、AIが共通の意図を理解し、適切な回答へ導けます。また、対話データを蓄積・活用することで、徐々に回答の精度が高まっていくのも特徴です。
ただし、導入時には回答のベースとなるデータの整備やAIの学習が必要で、その分コストや工数がやや大きめになる点には留意しましょう。人間のような柔軟さには及ばない場面もあるため、得意・不得意を見極めて活用する必要があります。
非AIチャットボット(ルールベース型)
非AIチャットボットは、あらかじめ決めたルールや選択肢に沿って返答するタイプです。キーワードやフローに従ってやり取りが進むため、想定外の質問には対応できませんが、決まった範囲で安定的に対応できます。
FAQ対応や資料請求、簡単なナビゲーションなど、目的が明確なケースでは特に使いやすく、短期間かつ低コストで導入できるのが魅力です。 また、シナリオの修正や管理もしやすいため、社内で調整しながら運用したい企業にも向いています。回答内容を限定する分、誤回答のリスクも少なく、運用負荷を抑えやすいでしょう。
有人型
有人型は、チャットボットによる自動対応と、オペレーターによる有人対応を組み合わせた運用形態です。シンプルな質問はボットでスピーディに対応し、対応が難しい場合や高度な判断が必要な場面は、人の手に引き継ぐことでスムーズな対応ができるようになります。
すべてを自動化するのではなく、人の介入を前提とすることで、顧客満足度と業務効率をバランスよく両立することが可能です。特に商談化やトラブル対応といった「あと一押し」が重要な場面では、効果的に働く場合があります。
AIチャットボットの種類
AIチャットボットは、大きく3つの種類に分けられます。
- 検索型
- 生成型
- RAG型
それぞれの仕組みと特徴を理解し、自社の目的に合った種類を選びましょう。
検索型
検索型AIチャットボットは、AIがユーザーの質問の意図を理解した上で、データベース内から最適な回答を探し出して提示するタイプです。
あらかじめ登録された情報のみを回答するため、企業側で回答内容を完全にコントロールでき、誤った情報を提示するリスクがないのが特徴です。比較的、導入コストを抑えやすい点もメリットといえるでしょう。
生成型
生成型チャットボットは、ChatGPTのように、AIがその場で新しい回答を文章として生成するタイプです。
データベースにない未知の質問に対しても、文脈を読み取って柔軟に回答を生成できるため、より人間に近い自然な対話を実現します。要約やアイデア出しといった、多様なタスクに対応できるのも大きな強みです。ただし、AIが事実にもとづかない回答を生成する「ハルシネーション」のリスクには注意が必要です。
RAG型
RAG型チャットボットは、「検索型」と「生成AI型」を組み合わせた最新のタイプです。そもそもRAGとは、生成AIが回答を作成するとき、社内マニュアルや企業のデータベースなど指定した情報源のみを参照させる技術です。
厳密にいうと、生成型のAIチャットボットにRAGを搭載したというほうが正しいですが、独立した種類として紹介されることも多くなっています。
RAGを活用することで、生成AIの弱点であるハルシネーションのリスクを軽減し、回答の正確性を高めることが可能です。
ルールベース型チャットボットの種類
非AIチャットボットの一種であるルールベース型チャットボットは、あらかじめ設計されたシナリオ(対話の台本)に沿って、ユーザーとの会話を進めるのが基本です。
そのシナリオをどのように分岐させていくかの仕組みとして、主に次の2種類があります。
- キーワードマッチ型
- ボタン選択型
どちらかを選ぶというよりは、組み合わせたり使い分けたりすることで、チャットボットの導入効果を向上させることが可能です。
キーワードマッチ型
キーワードマッチ型は、ユーザーが入力した文章に含まれる、特定の単語(キーワード)を認識して、あらかじめ用意された回答を提示する仕組みです。
「〇〇の料金」といった、ユーザーの質問が予測しやすい場合に役立ちますが、キーワードが含まれていない質問や、意図しない文脈でキーワードが使われた場合は、的確な応答が難しくなります。
ボタン選択型
ボタン選択型は、ユーザーに選択肢をボタンとして提示し、それを押してもらうことで対話を進める、最もシンプルな仕組みです。
ユーザーは文字を入力する必要がないため、迷わず直感的に操作できるのが最大のメリットです。ただし、提供できる情報が選択肢に限定されるため、複雑な問い合わせには向きません。
【目的別】チャットボットのおすすめの種類
本記事で紹介したチャットボットの種類をもとに、目的別におすすめの種類を紹介します。
- 顧客対応(カスタマーサポート)
- 販売・予約・申し込み支援
- マーケティング・リード獲得
目的に合わせた種類を選ぶときの参考にしてみてください。
顧客対応(カスタマーサポート)
カスタマーサポートでは「正確かつ迅速な問題解決」を実現するために、自動応答と有人対応を組み合わせた「有人型」が効果的です。
一次対応として「検索型のAIチャットボット」が、よくある質問に24時間体制で回答し、自己解決を促進します。ボットでは解決できない複雑な問い合わせに対しては、オペレーターの有人チャットへ切り替えます。
チャットボットと有人チャットを使い分けることで、サポート業務の効率化と、質の高い顧客体験を両立させることが可能です。
販売・予約・申し込み支援
商品購入やサービス予約、資料請求といった「CV(コンバージョン)につながるアクションの支援」には、非AI型のチャットボットがおすすめです。事前に定義されたシナリオに沿って案内を進めることで、誤入力や離脱を防ぎ、予約完了率や購入率の向上につなげることが可能です。
例えば、宿泊施設や美容室の予約では、チャットボットの会話内で「希望日時を選んでください」「ご希望のメニューをお選びください」といった選択肢を段階的に提示することで、ユーザーは迷わず対話を進められます。
フォーム入力よりもストレスが少なく、スムーズに予約完了へ誘導できるのが特徴です。
マーケティング・リード獲得
マーケティングやリード獲得では、ユーザーとの対話を通じて関心や課題を引き出し、有益な情報を取得することが重要です。そのため、自由な対話ができる「生成型」や「RAG型」のAIチャットボットが適しています。
例えば、製品に興味を持った見込み顧客に対して、自然な会話でニーズを把握し、関連サービスや資料を案内できます。自由入力に対応できるため、ユーザーごとの多様な質問や関心にも柔軟に対応でき、エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。
また、RAG型であれば、自社データに基づいた正確な回答が可能になり、信頼性の高い対話を通じて、CV数の増加にもつながります。
自社に合ったチャットボットの種類を選ぶ方法
自社に合ったチャットボットの種類を選ぶときは、次の方法を試してみてください。
- 導入目的を明確化する
- 必要な機能を洗い出す
- ユーザーの使いやすさを考慮する
- 運用・更新のしやすさを考慮する
- 費用対効果をシミュレーションする
丁寧に現状を整理することで、自社に合ったツールが見えてくるはずです。
導入目的を明確化する
チャットボットを導入する際は、まず「何を達成したいか」を明確にする必要があります。目的がぼんやりしたままだと、選ぶべき種類も曖昧になり、運用後に「思ったほど効果が出ない」という事態につながりかねません。
例えば、問い合わせ対応の効率化が狙いなら、FAQへの自動応答に向いている非AI型が適切です。一方で、会話のなかで相手のニーズを引き出したい場合は、柔軟な応対ができるAI型のが適しています。
目的が整理されていれば、その後の機能選定や運用方針も見えやすくなります。
必要な機能を洗い出す
目的が定まったら、その目的を実現するために必要な機能を明らかにしていきます。目的が曖昧なまま「何となく機能が多い」という理由で選んでしまえば、結局使いこなせないといった事態に陥るためです。
以下に、目的と機能、適したチャットボットの種類の対応関係を整理しました。
| 導入目的 | 必要な機能 | 適したチャットボットの種類 |
| FAQ対応を自動化したい | シナリオ設計、選択肢提示 | ルールベース型 |
| 顧客からの自由な質問に答えたい | 自然言語処理、生成応答 | 生成型AIチャットボット |
| 社内マニュアルに基づいた回答を行いたい | 外部データ連携、検索精度 | RAG型チャットボット |
| リード情報を収集したい | 入力フォーム連携、ログ保存 | CRM連携機能があるチャットボット |
| 多言語で対応がしたい | 多言語対応設定 | ・多言語対応可能なAI型・ルールベース型 |
| 複雑な問い合わせにも対応したい | 有人切替機能、履歴共有 | 有人型 |
複数の目的がある場合は、優先度をつけて順に実現する方法もあります。一つのツールですべてを叶えるのではなく、必要に応じて段階的に合った機能を導入することも大切です。
ユーザーの使いやすさを考慮する
社内の要望だけでツールを選んでしまうと、ユーザーにとって使いにくいチャットボットになるリスクがあります。特にBtoCサイトやスマホユーザーが多い場合は、操作のしやすさが成果につながるため留意が必要です。
選択式でやり取りを進める非AI型は、入力に不慣れな人でも迷わず使えます。また、自由記述ができるAI型は、複雑な質問や細かい要望への対応力が高いのが特徴です。
ユーザーの属性や使用環境に合ったチャット体験を設計することが、継続利用にもつながります。
運用・更新のしやすさを考慮する
どんなに魅力的なチャットボットでも、導入後の運用・更新がおざなりになると、効果が減退するおそれがあります。導入後もメンテナンスを継続するためには、運用体制や更新のしやすさを考慮したツール選定が大切です。
例えば、AIチャットボットのなかでもRAG型は高度な情報連携が可能ですが、社内データの更新や内容の精査といった作業が欠かせません。こうした作業が難しい場合は、構成変更が比較的容易で、現場主導でも調整しやすい非AI型を選択肢として考えるとよいでしょう。
自社の体制でどこまで対応できるかを見極め、無理のない運用を前提に選ぶことが大切です。
費用対効果をシミュレーションする
チャットボットの種類によって、コスト構造と期待できる効果は大きく異なります。そのため、料金だけで判断せず、目的達成に対して適切な投資かどうかを考える必要があります。
生成型やRAG型のように高機能なタイプは、拡張性や応答精度に優れる分、費用が高くなる傾向があります。特定業務に限定した導入であれば、シンプルな非AI型でも十分な効果を得られるケースも少なくありません。
コストだけではなく費用対効果をシミュレーションすることが、失敗しないポイントです。
チャットボットでは対応しきれない領域をどう補うか?
チャットボットは業務の効率化につながる便利なツールですが、すべてのユーザー対応を任せられるわけではありません。
ユーザーの疑問が深かったり、状況が複雑だったりする場合にチャットボットで自動応答すると、ユーザーの満足度が低下するおそれがあります。また、的外れな返答が続くことで、不信感を与えてしまうリスクもあります。
こうしたリスクを回避するには、チャットボット単体ではなく、有人対応と組み合わせた運用が効果的です。OPTEMOのような有人チャットツールを活用すれば、訪問者の行動をリアルタイムで把握し、迷っているタイミングを逃さずに有人チャットへ切り替えられます。
ユーザーの離脱や取りこぼしを防ぎ、リード獲得や商談化につなげるには、「人の関与をどう設計するか」という視点も欠かせません。
まとめ:自社に合ったチャットボットの種類を選ぼう
チャットボットには、AI型やルールベース型、有人型などの種類があり、それぞれ得意分野や特徴が異なります。自社の導入目的や運用体制に応じて、必要な機能が備わった種類を選ぶことが、成果につながる第一歩です。
ただし、どの種類を選んでも、すべての問い合わせに対応できるわけではありません。複雑な質問や感情的な問い合わせなどは、チャットボットだけではカバーしきれないケースもあります。
その場合は、有人型チャットサービスや、リアルタイムにユーザーの行動を検知してオペレーターから声をかけられるOPTEMOのようなツールが適しています。
OPTEMOは、Webサイト訪問者の行動をもとに、最適なタイミングで有人チャットを開始できる接客支援ツールです。問い合わせフォームでは拾いきれないようなユーザーの「困っている瞬間」を逃さず、CV改善や顧客満足度の向上につなげることが可能です。
「チャットボットで解決できる領域」と「人が介在すべき領域」を見極めながら、自社に最適な体制を構築していきましょう。
OPTEMOの機能や導入事例は以下の資料で紹介しているので、あわせてご覧ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから