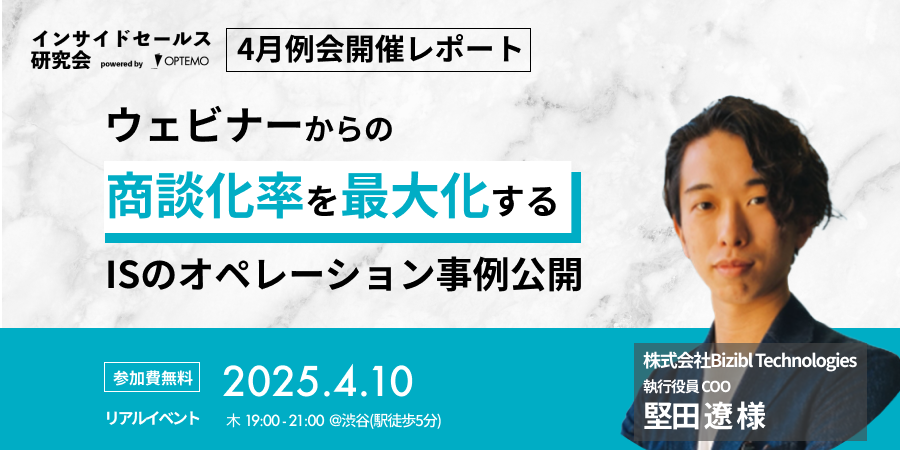チャットボットの選び方|おすすめのツール5選も紹介

「自社サイト経由のリードや商談が思うように増えない」「問い合わせ対応にも手間がかかっている」といった悩みは、チャットボットの導入によって解決できる可能性があります。
とはいえ、チャットボットにはさまざまな種類があり、ツールごとの機能や使い勝手も異なるため、自社に合ったものをどう選べばいいか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、チャットボットの選び方のポイントを解説した上で、自社サイト改善に役立つおすすめツールを5つ紹介します。チャットボットの導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
チャットボットとは
チャットボットとは、ユーザーの質問に自動で応答するプログラムです。企業では、よくある質問への回答や予約受付、資料の案内などで活用されています。
人のオペレーターが対応するのが難しい24時間対応を可能にし、これまで担当者がかけていた時間を減らせることから注目されています。
チャットボットの種類
チャットボットには、以下の種類があります。
- AIチャットボット
- ルールベース型
- 有人対応型
それぞれのタイプの特徴と活用シーンを押さえた上で、自社に合った方向性を考えていきましょう。
AIチャットボット
AIチャットボットとは、ユーザーの入力内容をAIが理解し、柔軟に応答できるチャットボットです。
学習によって応用が効くため、FAQ対応だけではなく、資料案内や製品選定のサポートなど幅広い用途に活用できます。
「◯◯プランと△△プランの違いは?」といった曖昧な質問も、意図を汲んだ上で案内することが可能です。対応回数を重ねるごとに、対応精度が向上する特徴もあります。
問い合わせ内容が多岐にわたる業務や、一次対応の品質を高めたい場合におすすめです。
非AIチャットボット(ルールベース型)
非AIチャットボット(ルールベース型)とは、あらかじめ設定したシナリオや選択肢に沿って自動で回答する仕組みをもつチャットボットです。
「営業時間を知りたい」「料金表を確認したい」などと定型的な質問に対し、あらかじめ用意した回答を返します。問い合わせ内容が想定の範囲内であれば、安定した応答が可能です。ただし、想定外の質問には対応できないため、用途を絞って運用することが大切です。
運用もシンプルなので、まずは基本的な業務対応を自動化したいと考える企業におすすめです。
有人型
有人型とは、ユーザーからの問い合わせに対し、人間の担当者がチャットツールを使ってリアルタイムに対応するタイプです。
「このケースでどのプランが向いているか教えてほしい」といった複雑な判断が必要な問い合わせに対しても、状況に応じて柔軟に提案できます。言い回しやテンポから相手の温度感を読み取れるのも強みです。有人型は、無人のチャットボットでは拾いきれないニーズをフォローしたいときに欠かせない手段だといえます。
ユーザーとの信頼関係を築きやすいため、高単価の商材やBtoBの提案型営業におすすめです。
チャットボットの種類については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
・チャットボットの種類|特徴と自社に合わせて選ぶ方法を解説
チャットボットの選び方
チャットボットは、次のステップに沿って選びます。
- 導入目的を明確にする
- 自社に合った種類を選ぶ
- 必要な機能を洗い出す
- セキュリティ要件を確認する
- サポート体制を確認する
- 費用対効果を検証する
- 無料トライアルで使いやすさを試す
選定時の視点を明確化すると、導入後の運用トラブルやミスマッチも防げます。
導入目的を明確にする
チャットボットを導入するときは、目的をはっきりさせておかないと選定基準が曖昧になり、自社に合わないツールを選ぶことになりかねません。必要な機能を見落としたり、逆に過剰なスペックにコストをかけてしまうリスクがあります。
「問い合わせ対応の自動化」を目的とする場合、重要なのはFAQの管理や、定型パターンに沿ったスムーズな案内です。リード獲得や営業支援を狙うケースとは、求められる機能や設計がまったく異なります。
自社に合ったツールを選定するために、まずは「何のために導入するのか」を明確にするところから始めましょう。
自社に合った種類を選ぶ
チャットボットは、種類によって得意分野や使い勝手が異なります。社内FAQのような定型対応であれば非AIチャットボット(ルールベース型)が適していますが、複雑な質問や自由入力への対応が求められる場面ではAIチャットボットのほうが柔軟に対応できます。
自社の目的やチャットボットに担わせたい業務に合った種類を見極めることが、スムーズな活用につながるでしょう。
必要な機能を洗い出す
チャットボットごとに備えている機能が異なるため、あらかじめ必要な機能を整理しておくことが必要です。機能要件が曖昧だと比較が難しくなり、導入後に「必要な機能がなかった」と後悔するケースもあります。
多言語対応や営業時間外の無人対応、CRMやSFAとの連携など、業務に直結する項目は優先順位を高くつけてリストアップしましょう。必要性の高いものと妥協できるものを切り分けることで、選定がスムーズになります。
セキュリティ要件を確認する
チャットボットが個人情報を扱う場合もあるため、導入前にセキュリティ要件を確認することが大切です。セキュリティが脆弱だと、情報漏洩リスクや社内規定違反につながるおそれがあります。
リスクを抑えるためには、暗号化の有無や認証の仕組み、データの保存期間・管理方法など、自社のセキュリティポリシーと照らし合わせることが大切です。特に、法令や業界ガイドラインが厳しい業種では、要件を明確にした上で、要件を満たすツールの選定が重要です。
サポート体制を確認する
チャットボットの導入・運用にはつまずきやすいポイントも多いため、丁寧なサポートを受けられるかどうかはツールの重要な選定ポイントです。特に、社内で初めてチャットボットを導入するときや、ITに詳しい担当者がいない場合は、十分なサポートが受けられるかは重要になってきます。
問い合わせ対応の範囲やスピード、初期設定やシナリオ作成にどこまで関与してくれるのかは、提供元によって差があります。長期運用を見据えるのであれば、導入後の改善提案や活用支援までカバーされているかどうかもチェックしましょう。
費用対効果を検証する
チャットボットは導入費や運用費、チャットボットを運用する社内の人的コストも含めて費用対効果を検証する必要があります。ツールの価格だけを見て導入した結果、シナリオの改善に多くの時間と人手が割かれ、業務の効率化にならないといったケースもあるので注意しましょう。
どれくらいの業務削減やリード獲得につながるのかを事前に見積もっておくと、判断しやすくなります。費用と得られる効果のバランスを整理することで、納得感のある選定が可能です。
無料トライアルで使いやすさを試す
導入前には、ツールの使い心地をしっかり確認するために、無料トライアルを活用するのがおすすめです。実際に触ってみることで、「思っていたより使いにくい」といった導入後のギャップを減らせます。
無料トライアルでは、チャット画面の見やすさやシナリオ設計の操作性、カスタマイズの自由度など、実際の運用を想定しながらチェックしてみましょう。このとき、複数人で試すと、さまざまな視点からツールを評価できます。
おすすめのチャットボットツール5選
ここからは、おすすめのチャットボットツールを5つ紹介します。
- ChatPlus
- PKSHA Chatbot
- DECA カスタマーサポート
- OfficeBot
- sinclo
主な特徴と活用シーンを解説するので、自社の目的に照らしながら、比較検討の参考にしてください。
ChatPlus
ChatPlusは、テンプレート型のシナリオをベースに自動応答を行うAIチャットボットです。質問ごとに細かく分岐を設計できるため、対応範囲をコントロールしやすいのが特徴です。多言語対応や外部ツールとの連携機能も備えているほか、必要に応じて有人チャットと連携できます。
想定される質問パターンがある程度決まっている場合、高精度な無人対応を構築しやすいため、有人対応の負荷を軽減したい企業におすすめです。:PKSHA Chatbot
PKSHA Chatbotは、ユーザーの曖昧な表現や言い換えも理解して回答できるAIチャットボットです。曖昧な表現や言い回しの違いからユーザーの意図を正確に捉え、自由入力にも適切に応答できます。
一方で、選択肢によるシナリオ分岐も併用できるため、対応の自由度と誘導性を両立できます。
これらの特徴から、問い合わせの内容が幅広く、定型的な質問と柔軟な対応がどちらも求められる企業におすすめです。
DECA カスタマーサポート
DECA カスタマーサポートは、FAQ対応や問い合わせの自動応答を通じて、カスタマーサポート業務を効率化するAIチャットボットです。過去の対応データをもとに、質問の意図に沿った回答を返す設計が特徴で、複数チャネルからの問い合わせにも対応できます。
サポート業務の自動化を進めたい一方で、問い合わせ件数が多く対応が属人化しがちな企業におすすめです。
OfficeBot
OfficeBotは、社内の問い合わせ対応や業務手続きを自動化するAIチャットボットです。申請やマニュアル確認など、社内で繰り返される定型業務をチャットで完結できるように設計されています。質問の意図を自然言語で理解し、業務ごとのシナリオも柔軟に設定可能です。
総務・人事・情報システムなど、問い合わせが集中しやすい部門での対応負荷を減らし、業務効率化と社内ナレッジの活用を両立したい企業におすすめです。
sinclo
sincloは、Webサイト上の訪問者に対して自動でアプローチできるチャットボットです。AI型ではなく、あらかじめ設定したシナリオに沿って会話を進めるルールベース型で、初期設定や設置がシンプルな点が特徴です。有人チャットとの切り替えも可能で、問い合わせ対応の柔軟性も備えています。
あらかじめ設定したシナリオに沿って安定した対応ができるため、Webサイト上のよくある質問に素早く対応したい企業や、有人対応の負担を軽減したい企業におすすめです。
チャットボットでは不十分な場合におすすめのツール
チャットボットは即時対応に優れており、定型的な問い合わせや、よくある質問への対応には非常に効果的です。
一方で、「何を聞けばいいのかまだ分からない」といった検討初期のユーザーには利用されにくく、チャット画面すら開かれずに離脱してしまうケースも少なくありません。
こうした「検討中層」へのアプローチには、チャットボットだけでなく、リアルタイムの会話が可能なツールの活用が効果的です。
チャットボットでは拾いきれない「検討中層」に対しては、リアルタイムの有人チャットや音声通話でアプローチできるOPTEMOが効果的です。
株式会社ユーザベース様の導入事例
画像出典:株式会社ユーザベース 導入事例ページ(https://optemo.co.jp//case/ub-initial/)
BtoBサービスを展開する株式会社ユーザベース様のINITIAL事業では、問い合わせフォームに入力しない潜在顧客と接点が持てないことが課題でした。
従来のチャットボットでは、「聞きたいことがまだ明確でない」検討初期のユーザーに利用されにくく、チャット画面すら開かれずに離脱してしまうケースが多く見られたといいます。
そこで、電話番号を知らなくてもWEB上で音声通話ができるOPTEMOを導入。ユーザーは電話番号の入力や発信作業なしに、ワンクリックでインサイドセールス担当者と直接会話できるようになりました。
これにより、従来は接点を持てなかった「検討中層」との会話が実現。インサイドセールスがリアルタイムでユーザーの温度感を把握しながら、柔軟にニーズを引き出せる体制を構築しました。
その結果、新規リード数が増加し、インサイドセールスのやりがいも向上。マーケティング部門との連携も強まり、顧客体験の質が高まっています。OPTEMOは「ゼロ」だった顧客接点を「1」に変える、新たなインサイドセールスの武器として活躍しています。
OPTEMOの機能や活用例は以下の資料で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
まとめ:自社に合ったチャットボットを選ぼう
チャットボットは、業務の自動化や顧客対応の効率化に欠かせないツールです。
しかし、自社の目的や課題に合っていないチャットボットを選んでしまうと、十分な効果が得られないばかりか、かえって運用の負担が増えてしまう可能性もあります。
選定にあたっては、「なぜ導入するのか」「どのような問い合わせに対応したいのか」といった目的を明確にし、必要な機能や種類を整理したうえで、費用対効果やサポート体制も含めて検討しましょう。
また、無料トライアルなどを活用し、実際の使い勝手を事前に確認することも大切です。
さらに、チャットボットだけでは対応しきれないユーザー層への接点づくりが課題であれば、OPTEMOのような有人チャット・通話ツールとの併用も検討する価値があります。
目的に応じた最適なツールの組み合わせで、自社にとって本当に成果につながる体制を構築していきましょう。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから