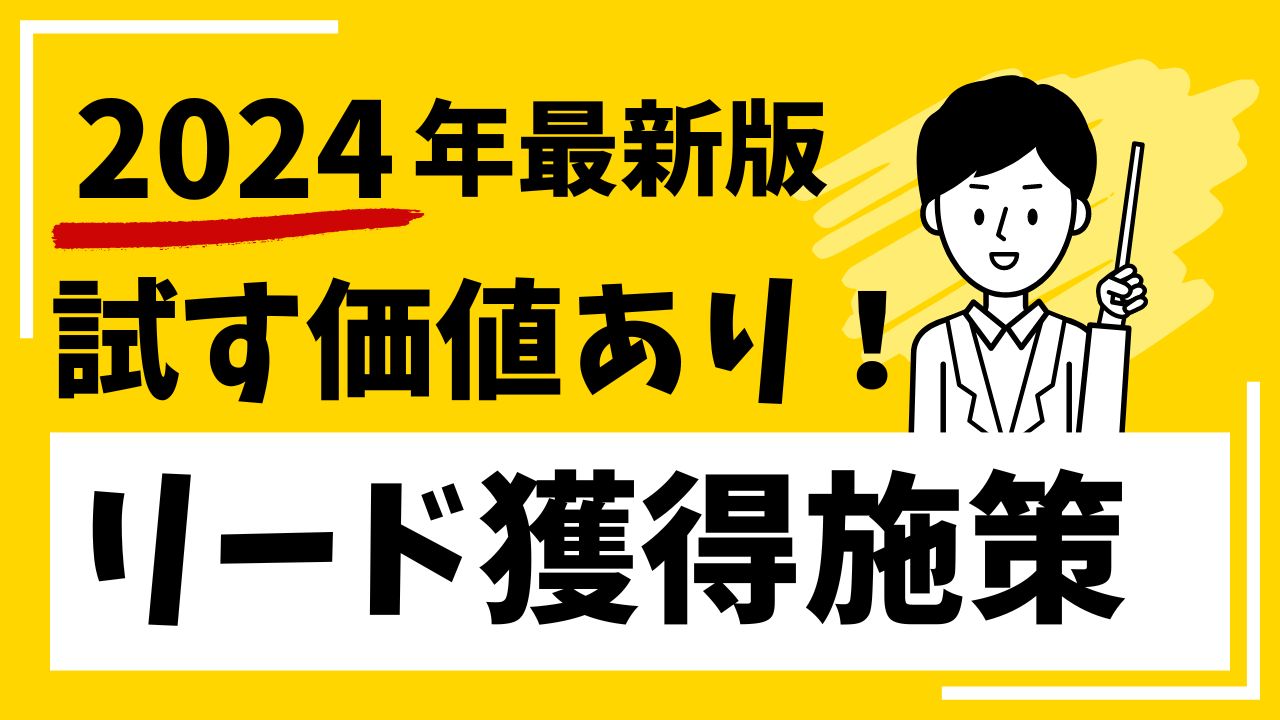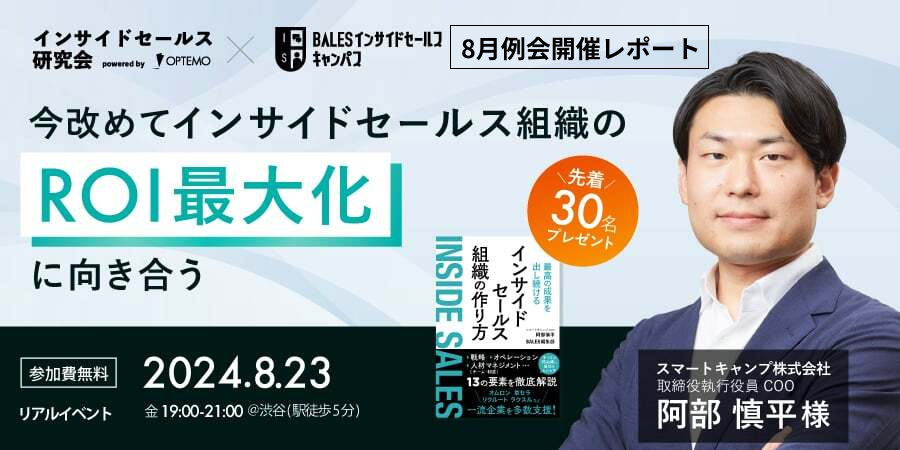EFOで入力完了率は上がる?成果を最大化するための施策とは

EFO(エントリーフォーム最適化)は、入力完了率の改善に直結する重要な取り組みです。
しかし、「EFO対策をしているのに思ったほどCVが伸びない」という悩みを抱える担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、EFOの基本から、成果を最大化するための効果的な施策、さらにはフォームに到達する前の段階で取りこぼさないための考え方までを整理してご紹介します。
目次
そもそもEFOとは?入力完了率を上げるための基本施策

フォームの最適化に取り組む企業は増えていますが、「具体的に何から手をつければいいのかわからない」という声も少なくありません。
まずは、EFOの基本的な考え方から押さえていきましょう。
EFO(入力フォーム最適化)の概要
EFOとは「Entry Form Optimization」の略で、日本語では「入力フォーム最適化」と訳されます。Webサイトの入力フォームにおけるユーザーの離脱を防ぎ、完了率を高めるための改善施策を指します。
たとえば、資料請求や問い合わせ、会員登録などの入力フォームは、項目が多かったり、入力エラーがわかりづらかったりすると、ユーザーが途中で離脱してしまう大きな原因になります。
EFOは、こうした離脱リスクを減らし、スムーズに送信完了まで誘導するための取り組みです。
入力完了率を上げるためのEFO施策とは?
EFOにはさまざまなアプローチがありますが、以下に代表的な施策を6つ紹介します。
入力欄の最小化・自動補完
ユーザーにとって「面倒くさい」と感じる最大のポイントは、入力項目が多すぎることです。
必要最低限の項目に絞り込んだり、名前のフリガナや住所を自動で補完したりすることで、入力負担を減らし、完了までのストレスを軽減できます。
リアルタイムバリデーション
送信ボタンを押したあとに「エラーがあります」と表示されると、ユーザーの意欲は一気に下がります。
リアルタイムバリデーションとは、入力中にその場でエラーを知らせる仕組みのこと。
たとえば、メールアドレスの形式が間違っている場合は、入力した瞬間にエラーメッセージが表示されることで、やり直しの手間が省けます。
フリガナ自動入力・郵便番号検索
入力を手間に感じるユーザーをサポートするために、補助機能の導入は非常に効果的です。
たとえば、名前の「フリガナ」欄は、氏名を入力した時点で自動で表示されるようにする、また郵便番号を入力すれば住所が自動入力されるといった機能は、ユーザーの「面倒」を解消します。
スマートフォン対応・UI改善
現在では、フォームの多くがスマートフォンからアクセスされています。
スマートフォンで操作しづらいフォームは、どんなに内容が良くても離脱率が上がります。
タップしやすいボタン配置や、スクロールを最小限にする設計、適切なキーボードの切り替えなど、モバイル端末に最適化されたUIを設計することは必須です。
ステップフォーム化
入力項目が多く、一度にすべてを表示すると「量が多い」「面倒そう」と感じてしまうユーザーも少なくありません。そこで有効なのが、1ページ内で項目を段階的に表示していく「ステップフォーム」形式です。
たとえば、「STEP1:基本情報の入力」が完了すると、「STEP2:連絡先情報」へと画面内で切り替わるように設計します。これは複数ページに分割するのではなく、1ページ内で小分けに表示して心理的負担を軽減する設計です。
「いきなり10項目が並ぶ」のではなく、「3項目ずつ、順を追って表示される」ことで、ユーザーはスムーズに入力を進めやすくなり、結果として離脱率の低減にもつながります。
離脱防止ポップアップ
ユーザーがブラウザの戻るボタンや閉じるボタンにカーソルを当てたときに、確認メッセージや限定オファーなどを表示するポップアップを出す施策です。
「入力途中ですが、内容を破棄してもよろしいですか?」といった呼びかけで、入力の継続を促したり、再訪時の再入力を防ぐ仕掛けとして活用されます。
これらの施策は、どれか一つだけで劇的に改善するというよりも、複数を組み合わせて最適化していくことが大切です。
また、効果測定やABテストを繰り返しながら、ユーザーにとってよりストレスのないフォームを目指すことが、CV率改善への近道となります。
EFO対策を成功させるにはツールの導入が不可欠な3つの理由

EFOは、感覚や見た目だけで改善を進めるよりも、専用のツールを活用して定量的に課題を把握し、効果検証しながら運用していくことが成功の近道です。
ここでは、EFO対策にツールを導入することで得られる代表的なメリットを3つご紹介します。
①ユーザーの離脱原因をデータで可視化できる
どの項目でユーザーが離脱したのか、どこで時間がかかっているのか──これらを正確に把握できなければ、適切な対策はできません。
EFOツールを使えば、フォームの各項目ごとの入力完了率や滞在時間、離脱率などをデータとして収集・分析できます。
これにより、「どの項目がボトルネックになっているのか」が一目瞭然になり、感覚ではなく実態に基づいた改善が可能になります。
②最小限の工数で導入・運用できる
「ツールを導入するのは大変そう」と感じる方もいるかもしれませんが、最近のEFOツールは簡易なタグの設置だけで利用開始できるものが主流です。
また、UI改善やバリデーション機能の追加なども、ノーコードまたはローコードで対応できるツールが増えており、開発リソースに負担をかけず運用を始められる点も魅力です。
もちろん、全くのゼロ工数というわけではありませんが、汎用的なテンプレートやガイドが用意されているツールを選べば、最小限の準備で現場に導入できるケースが多いのが実情です。
③改善施策をテスト・検証しやすい(ABテスト・ヒートマップ連携)
EFOツールには、改善の効果を検証するための機能が標準で備わっていることが多くあります。
たとえば、入力欄の並び順や文言の違いによるABテスト、ユーザーの視線や操作を可視化できるヒートマップとの連携などが挙げられます。
これにより、単発の変更で終わらずに、「変更によってどのような成果があったのか」を継続的に計測・改善していくことができ、EFOの精度を高め続けることが可能です。
EFO対策でフォームに含めるべき効果的な施策7選

EFO(入力フォーム最適化)を効果的に進めるには、ユーザーが「面倒」「分かりづらい」と感じる要因を一つずつ取り除いていく必要があります。
ここでは、フォームに実装すべき代表的な7つの施策をご紹介します。
1. 項目の削減とグルーピング
入力項目が多ければ多いほど、ユーザーの離脱率は高まります。特に初めての訪問者にとって、長いフォームは心理的なハードルになります。
たとえば、「会社名」「部署名」「役職名」などは必要最低限に絞る、または後からヒアリングする形に切り替えるのも一つの方法です。
さらに、関連項目を「グルーピング」して視覚的に区切ることで、全体の印象がシンプルになり、ユーザーのストレスを軽減できます。
2. 入力補助(フリガナ・郵便番号・候補表示など)
ユーザーが一つひとつ手入力しなければならないフォームは、入力負担が大きくなります。
たとえば、「名前を入力するとフリガナが自動入力される」「郵便番号を入れると住所が自動入力される」といった補助機能があるだけで、入力作業は格段に楽になります。
また、会社名や製品名など候補をサジェストする機能を導入すれば、ミスの防止にもつながり、フォーム完了率の向上が期待できます。
3. エラーメッセージの即時表示
送信ボタンを押してから「入力エラーがあります」と表示されると、ユーザーは戸惑い、離脱する可能性が高まります。
これを防ぐには、入力中にその場でエラーを知らせるリアルタイムバリデーションが有効です。
たとえば、メールアドレスの形式が誤っていた場合や、必須項目が未入力だった場合にすぐに表示されることで、ユーザーが迷わず修正でき、離脱リスクを下げることができます。
4. スマートフォン向けUIの最適化
現在、フォームへのアクセスの多くがスマートフォン経由です。
PCで快適に使えるフォームも、スマートフォンでは操作しづらくなってしまうことがあります。
タップしやすいボタン配置、入力欄ごとに適切なキーボードの自動切り替え(例:数字入力欄ではテンキー表示)、余白の確保など、モバイルに最適化されたデザインが重要です。
5. 離脱検知&リマインドポップアップ
入力途中でページを閉じたり、他のタブに移動しようとするユーザーに対して、リマインドを促すポップアップを表示することで、離脱を防止できます。
たとえば、「入力はあと少しで完了です」「何かご不明な点があればサポートします」などのメッセージを出すことで、その場で不安や迷いを解消し、完了へと導くことが可能です。
6. サンクスページ最適化(次アクションへ導線)
フォーム送信後に表示されるサンクスページ(完了画面)は、次のアクションを促す絶好のタイミングです。
「資料ダウンロードはこちら」「担当者からの連絡を希望する方はLINE登録」など、ユーザーの熱が冷めないうちに導線を示すことで、CV後の接点強化やリードナーチャリングにもつながります。
7. 入力中のユーザーへのリアルタイムサポート連携
ユーザーがフォームを入力している最中に「ここがよくわからない」「この項目の意味は?」といった疑問を感じたとき、そのまま離脱してしまうケースも多くあります。
これを防ぐために、OPTEMOのようなリアルタイムでのチャット・音声通話対応が可能なツールと連携することで、その場で疑問を解消し、完了率を高めることができます。
フォーム改善と接客支援ツールを掛け合わせることで、「入力→完了」までの導線がより強固になるのです。
実はフォームの前段階での離脱が最も大きな損失

EFO対策に取り組む企業は増えていますが、それでも「思うようにCV率が上がらない」と感じるケースは少なくありません。その原因のひとつに、フォームそのものではなく、フォームにたどり着く前の段階での離脱を見落としていることがあります。
ユーザーの動線をフォーム到達前までさかのぼって見直すことが、CV率を根本から改善する鍵になるのです。
EFOはあくまで「フォームに来た後」の対策
EFOは非常に有効な施策ですが、その適用範囲は「入力フォームにたどり着いたユーザー」に限られます。
つまり、フォームに来た人をいかにスムーズに完了まで導くかという「後工程」に対する最適化です。
もちろん、ここを丁寧に改善することで完了率は上がりますが、そもそもフォームにたどり着かないユーザーが多いままでは、CVの最大化にはつながりません。
「フォームに来た人」だけを対象にしていては、CV改善の打ち手が限定的になってしまいます。
「少し気になるけど迷っている」ユーザーはそもそもフォームに来ない
Webサイトの訪問者の中には、「気になってはいるけれど、まだ申し込むほどではない」「少し情報を見てみたいだけ」という段階のユーザーが多く存在します。こうしたユーザーは、興味がある状態ではあるものの、フォームには進まずに離脱してしまうことがほとんどです。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- サービス内容は気になるが、自社に合うのか判断できない
- 料金体系や導入ハードルがよく分からない
- 「今すぐ問い合わせる」ほどではないが、少し話を聞いてみたい
このような迷っている層に対して、従来型のEFO施策だけではアプローチできないのが現状です。
その層にアプローチできる仕組みがないとCV率は頭打ちに
「迷っている段階のユーザー」をフォローする仕組みがなければ、せっかくWebサイトに訪問してくれた見込み顧客を、何もせずに逃してしまうことになります。
つまり、CV率の改善余地が残っていても、その層にリーチできなければ頭打ちのように感じてしまうのです。
実際、「フォーム最適化には取り組んでいるのにCV率が伸び悩む…」という企業は、このフォーム前の離脱層へのアプローチ不足が根本原因である場合が多くあります。
この課題を解決するには、フォーム以前の段階でユーザーと接点を持ち、疑問や不安を解消するための手段が必要になります。そこで活用されるのが、次に紹介する「リアルタイム接客ツール」のような仕組みです。
EFOツールと相性抜群!OPTEMOのフォーム前アプローチとは

EFOはあくまで「フォームに来た後」の施策であり、それ以前に離脱してしまうユーザーには効果が届きません。
そんなフォーム前段階での機会損失を減らし、EFO施策を最大限に活かす導線を整えてくれるのが、OPTEMO(オプテモ)です。
OPTEMOは、Webサイトに訪れたユーザーの行動をリアルタイムに把握し、「今、話しかけるべき瞬間」を逃さずアプローチできる有人型チャット・商談支援ツールです。
Webサイト訪問者の行動をリアルタイムで可視化
OPTEMOの大きな特徴のひとつが、サイト訪問者の行動をリアルタイムで見える化できることです。
- どのページを閲覧しているか
- どのくらいスクロールしているか
- 画面サイズや滞在時間はどれくらいか
こうした情報をもとに、ユーザーの「関心度(温度感)」をリアルタイムで把握できます。
たとえば、料金ページをじっくり見ているユーザーや、サービス詳細ページを何度も行き来しているユーザーは、「今、何かを迷っている」可能性が高いと判断できます。
このような行動データに基づいて、最適なタイミングでアプローチできるのが、OPTEMOならではの強みです。
温度感が高まったタイミングでチャット・音声通話を即スタート
OPTEMOでは、ユーザーの温度感が高まった瞬間に、ワンクリックでチャットや音声通話を開始することができます。しかも、ユーザー側には事前準備やアカウント登録などの手間が一切ありません。
たとえば、次のような場面で活用できます。
- サービス内容を読んだあとにページ内で止まっているユーザーに、チャットで声をかける
- フォームページに何度も戻ってきているユーザーに、音声通話を提案する
- 商品比較ページで迷っているユーザーに、その場で説明を加える
こうした「今、聞きたい」タイミングに寄り添った対応は、チャットボットではなく人の対応(有人型)だからこそできるアプローチです。
疑問を解消→フォーム到達→EFO施策の効果を最大化できる導線設計
ユーザーの多くは、「ちょっと気になるけど不安がある」「誰かに聞けたら進めるのに」という段階で止まってしまいます。OPTEMOを活用することで、その不安や疑問をリアルタイムで解消し、スムーズにフォームへと誘導することができます。
そして、フォームに到達したあとは、これまで紹介してきたEFO施策で入力完了率をさらに引き上げることが可能です。
つまり、OPTEMOは単独で成果を出すだけでなく、EFOと連携することで「フォームに来てもらう→完了してもらう」までの導線を一貫して強化できるツールなのです。
まとめ|EFO×OPTEMOでCV率の最大化を目指す

EFOによる入力フォームの最適化は、入力完了率を高める上で非常に重要な施策です。特に、EFOツールを活用することで、ユーザーの離脱ポイントをデータで可視化し、定量的に改善を進めていくことが可能になります。
しかし、本質的にCV率を底上げするためには、フォームに来る前の接客アプローチがより重要になります。そこで活用したいのが、リアルタイムで有人対応ができるチャットツール「OPTEMO」です。
OPTEMOなら、Webサイト上でユーザーの行動をリアルタイムに把握し、システムにより検知することで、「ユーザーの温度が高い瞬間に」自然に声がけすることが可能です。この即時対応のユーザー体験こそが、CV率全体を引き上げる大きな要因となります。
有人型チャットツール「OPTEMO」を導入すれば、匿名ユーザーにもその場でアプローチでき、商談獲得単価の削減や営業効率の向上にもつながります。
以下の資料では、OPTEMOの具体的な機能や活用事例についてご紹介しています。詳細はぜひこちらからご確認ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから