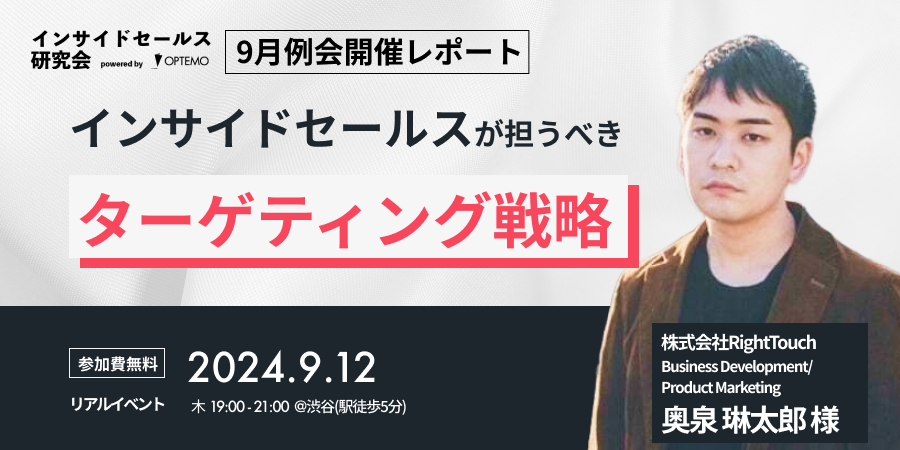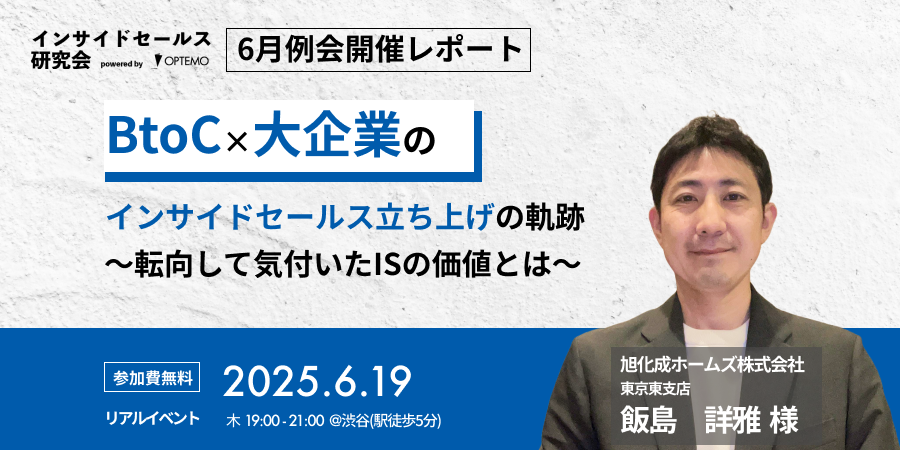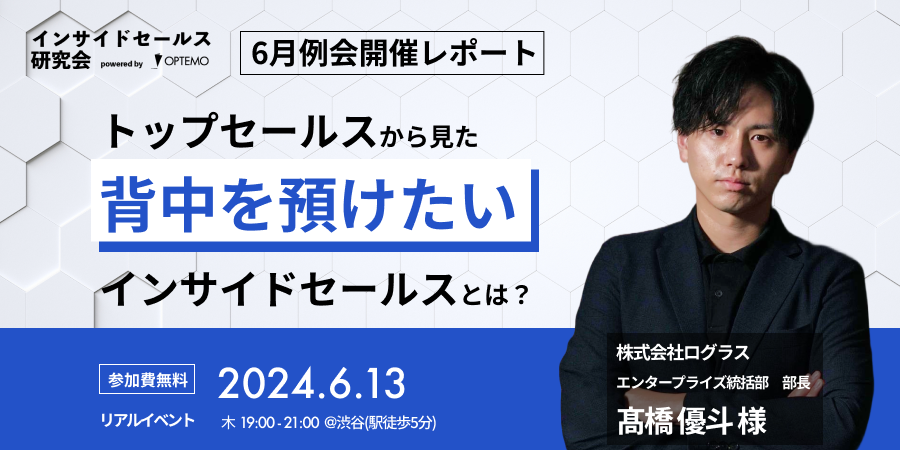インサイドセールス研究会2025年2月例会レポート
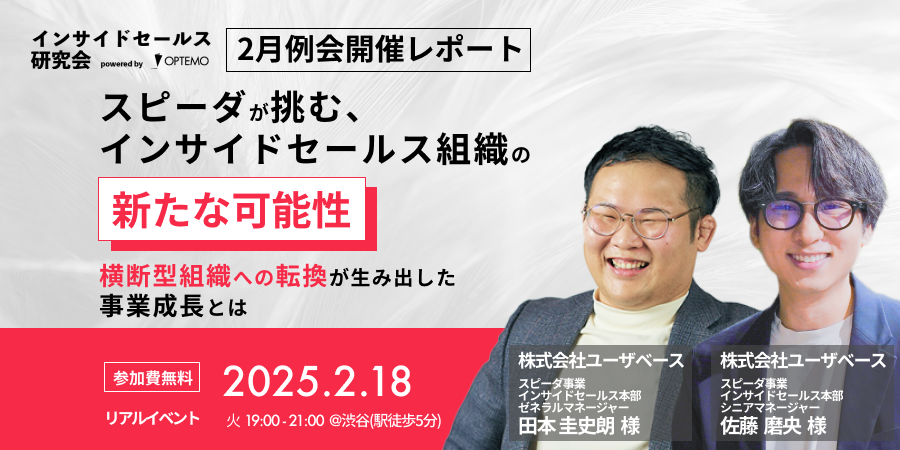
株式会社OPTEMOが運営しているインサイドセールス研究会というコミュニティでは毎月オフラインイベントを開催しております。2月に開催されたイベントの内容について、より多くの皆様に知っていただく機会となることを願い、イベントレポートを作成しました。
今回のレポートは、2025年2月18日(火)に開催されましたインサイドセールス研究会の内容をまとめておりますので、ぜひご覧ください。
インサイドセールス研究会について
インサイドセールス研究会は、『会社を超えてインサイドセールス同士が繋がり「師と友」を作れる場』として株式会社OPTEMOが運営しているコミュニティです。
インサイドセールスという業務の性質上、社外での横の繋がりが少ないという声を受け、2023年3月からこのコミュニティの運営を始めました。毎月1回、特別なゲストを迎えて実践的なノウハウを提供しています。また、Facebookのグループで情報発信もしており、誰でも無料で参加できます。
https://optemo.co.jp//lp/is_ken
今回のテーマ
今回のイベントでは、株式会社ユーザーベースのスピーダ事業から田本圭史郎様(インサイドセールス本部ゼネラルマネージャー)と佐藤磨央様(インサイドセールス本部シニアマネージャー)、昨年までインサイドセールス業務を担当していた堤建太様をゲストにお迎えし、「スピーダが挑むインサイドセールス組織の新たな可能性~横断型組織への転換が生み出した事業成長とは~」というテーマで公演いただきました。モデレーターはOPTEMO代表の小池桃太郎(@MomotaroKOIKE)が務めました。
昨年ユーザーベースでは複数の国内SaaSプロダクト(「INITIAL」「FORCAS」「SPEEDA」など)をすべて「スピーダ」ブランドにリブランディングし、組織も一体化させる変革に取り組みました。今回は、その組織立ち上げの苦労や得られた成果を共有していただく形でこのテーマが設定されています。ここからはその具体的な内容についてお伝えしていきます。

組織変革の全体像について
田本様からは、インサイドセールス組織変革の全体像について紹介していただきました。統合前の組織体制ではプロダクトごとに独立したインサイドセールスチームを抱えるカンパニー制で、それぞれが事業を最速で追いかける分業体制となっていました。
しかし、このカンパニー制には大きく2つの課題が存在したといいます。1つ目はクロスセルのインセンティブが弱いということ。営業担当者は自分の担当プロダクトの販売に専念せざるを得ないため、顧客にとって最適なソリューション提案ができていなかったのです。
2つ目は営業活動のバッティングです。同一顧客に複数製品の担当者が別々にアプローチすることで顧客体験が損なわれ、営業効率も低下していたといいます。このような課題を解決すべく、インサイドセールス組織の統合案の話が進んで行きました。統合の目的として掲げられたのは、「ユーザーの理想実現」と「顧客課題・ニーズ中心の営業戦略へのシフト」という2点でした。
田本様は、1年分の全案件を確認し、クロスセルの可能性がある案件を精査しました。その結果、例えばスタートアップ領域の顧客の約40%には新たにSPEEDAの価値が提供可能であることが分かり、もしクロスセルを実行できればどの程度売上を伸ばせるか試算して具体的な数字を提示しました。この定量的な根拠は組織統合を社内調整する上で強力な説得材料となったそうです。
その上で、実際の組織統合は段階的に進められました。いきなり全チームを融合すると大きなハレーション(摩擦)が生じる恐れがあるため、まず親和性の高いチーム同士から順次統合を開始します。

具体的には、まず2023年第1四半期に市場リサーチ系サービスのSPEEDAチームとスタートアップ情報サービスのINITIALチームを統合しました。続く第3四半期には全プロダクトのブランド名称を「スピーダ」に統一し、顧客から見ても一つの提案窓口に見えるよう再編しました。そして第4四半期までに関連する全てのインサイドセールス部隊を一本化し、複数プロダクトを連携させて顧客体験を最大化できる体制を整えています。
この統合によって、平均受注単価が約120%向上し、部門をまたいだ他部署紹介案件は前年の約5倍に増加するといった明確な成果も得られています。組織横断により営業担当者が単一の顧客に対して複数商材を組み合わせた提案をワンストップで行えるようになり、クロスセル機会の拡大と顧客満足度向上に大きく寄与したことが数字にも表れました。
超エンタープライズ組織の立ち上げについて
佐藤様からは、スピーダのインサイドセールス組織内で超エンタープライズ(超大手顧客)を担当する組織やチームの戦略について具体的にお話いただきました。ユーザーベースでは既に契約のあるNTTや三菱電機といったビッグネームの大企業に対して契約規模をさらに拡大していくことを重視しており、こうした超大手顧客を対象にインサイドセールスが「ビッグディール」を創出することがミッションとなっています。
佐藤様のチームではそのための取り組みとして「もくもく会」と呼ばれる施策を導入しました。これはエンジニアの世界で使われる「黙々と作業する会」という言葉に由来する名称で、1時間という限られた時間内にターゲット企業のキーパーソンを見つけ出し、アプローチ方法を検討して実際にコンタクトまで行ってしまう集中ワークセッションです。
チーム全体で定期的にもくもく会を実施し、そこから何件のリードを創出し何件の商談を獲得できたかを追跡することで、メンバーの営業活動を大型案件志向へと変化させています。短時間に集中して取り組むことで効率的に新規アプローチ先を洗い出せる上、メンバー同士で知見を共有し合う場にもなっており、実際にこの場をきっかけに有望な大型商談が生まれるケースも出てきています。

また、佐藤様はキーパーソンの特定と攻略の重要性についても強調されました。ただリスト上の見込み客に漫然とアプローチするのではなく、まず「この案件のキーパーソンは誰か」を見極めることに注力します。例えばある有力人物にアプローチできたら、その人物を起点に組織内の関係図を広げていき、最終的に誰が真の決裁者でありビッグディール成立のカギを握る人物なのかを探っていくのです。必要に応じて顧問など外部のネットワークも活用しながら接点を作り、社内外のリソースを総動員してキーパーソンにアプローチすることを最重要ミッションとして推進しているとのことでした。こうした綿密なターゲッティング戦略により、トップ商談を獲得し、成果創出に向けた組織を創り上げたそうです。
組織統合における組織文化の融合

堤様からは、組織統合における組織文化の融合と評価制度の変更について語っていただきました。インサイドセールス組織の統合では人や文化の面で様々な課題が生じます。組織再編の際には一部のメンバーが「統合前の方が良かった」と感じてモチベーションや主体性を失ってしまう恐れがあると言います。そうした抵抗感によって組織全体の成長が停滞しないようにするため、統合のタイミングでメンバーに成功体験を積ませる仕掛けを用意することが重要だと述べました。
具体的には、組織横断直後に短期間で達成できる明確な目標を設定することです。例えば、2週間で商談15件獲得を目指す「アポ取る15」という社内キャンペーンを行いました。メンバーが早期に達成感を得られるようにするための工夫だといいます。成功体験を重ねることで、「言われたことだけをこなす」受け身の姿勢に陥ることを防ぎ、統合後の新しい体制への適応をスムーズにしました。
また、旧来の組織の壁を取り払いメンバー同士の相互理解を深めるために、交流の場を設けて意図的にコミュニケーションを促進する施策も取られました。例えば分割前の各チームから数名ずつを混成した3~4名のグループでディスカッションや情報交換を行う場を設け、部門を超えた横の繋がり、文化を醸成したのです。このように、人材面では「モチベーション維持」と「文化融合」に重点を置きながら統合を進めていきました。
評価制度の変更について
次に評価制度の見直しについてです。従来の体制では、インサイドセールス個々人の評価指標が商談数やパイプライン数など短期的な活動量に偏っており、その結果メンバーは目先の件数目標の達成ばかりに注力しがちでした。これでは組織として狙うべき大型案件の創出につながる行動が起きにくいため、評価基準とインセンティブの仕組みを抜本的に見直したと言います。堤様は「評価はリーダーの主観によるのではなく、明確な基準に基づき公平で納得感のあるものにすべき」と指摘し、統合後の新たな戦略に沿った形で評価基準を再設計したといいます。
具体的には、これまで大小問わず案件1件を一律にカウントしていた評価方法を改め、案件規模(契約金額やID数など)に応じて重み付けして評価するように変更しました。例えば5ID規模の提案案件も100ID規模の提案案件も同じ「1件」として扱われていたものを是正し、大型案件に取り組めば取り組むほど高い評価が得られる仕組みにしたのです。これによりメンバーは単に件数を追うのではなく、大きな案件ほど積極的に狙うインセンティブが働くようになりました。
さらに、評価基準自体も透明性の高い数値ベースに統一し、誰もが納得できる形でパフォーマンスを評価することを重視したといいます。以上のように、人事評価の面からも組織横断の効果を最大化すべく環境整備を整えることで成果のでる組織を創り上げていきました。
交流会の様子
講演終了後には参加者同士のネットワーキングとなる交流会が行われました。田本様、佐藤様、堤様もその場に残って参加者からの質問対応や名刺交換をされていました。限られた時間ではありましたが、会場の各所で活発な意見交換が行われ、初対面同士でも積極的に話しかけ合い情報共有や人脈づくりに励む参加者の姿が見られました。インサイドセールスという共通のテーマを持つ者同士が会社の垣根を超えて交流できる貴重な機会となり、大いに盛り上がりを見せました。

インサイドセールス研究会の交流会では、毎回「新たな体験を提供する」ことをテーマに掲げ、参加者特典として小さなギフトやサービスをお渡ししています。今回の交流会では、ご参加いただいた皆様へのお土産として、カフェイン量を選びながらコーヒーを飲むことができる「CHOOZE COFFEE」をご用意しました。

最後に
今回のインサイドセールス研究会では、インサイドセールス組織の新たな可能性と横断型組織への転換が生み出した事業成長についてご紹介いただきました。さまざまな議題についてディスカッションができた有意義な会になったのではないでしょうか。
本イベントの内容が、ご参加いただいた皆さんのこれからの活動に少しでもお役に立てれば幸いです。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから