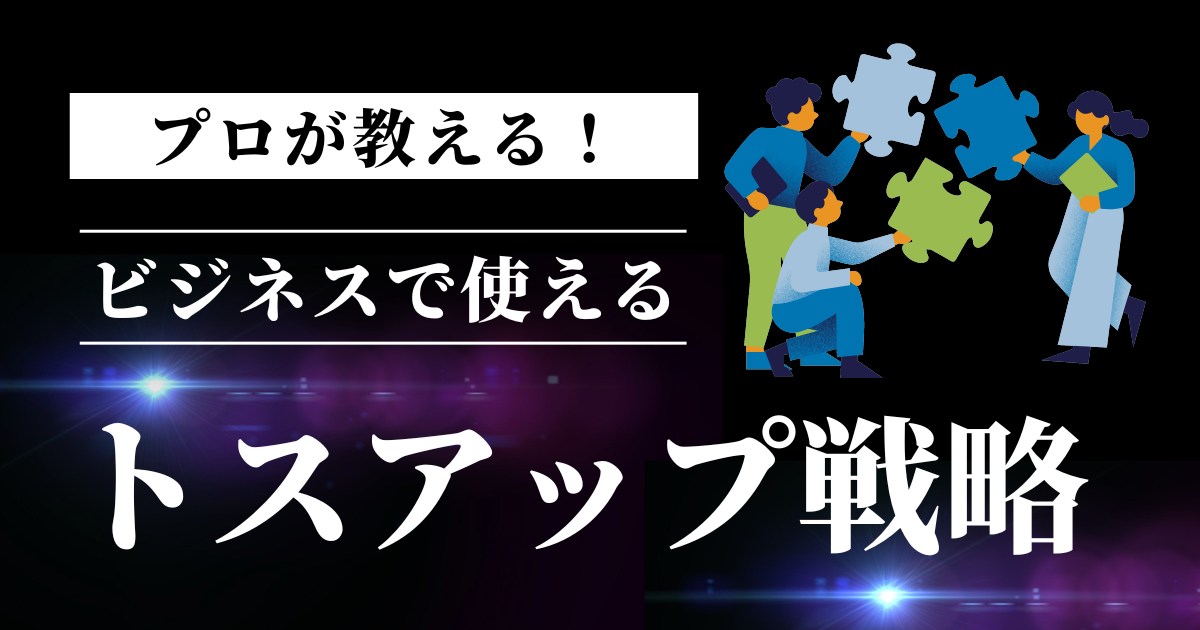インサイドセールスとは?役割やメリット、リード獲得の成功事例を紹介

営業活動の効率化や新規顧客獲得の手段として注目されている「インサイドセールス」。近年ではSaaS企業から製造業まで幅広い業界で導入が進み、リード獲得や商談化率の向上に成果を上げています。しかし、「そもそもインサイドセールスとは何か」「フィールドセールスとどう違うのか」「具体的にどのような成果が出ているのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、インサイドセールスの定義や役割、リード獲得におけるメリットを整理しながら、実際の成功事例を交えてわかりやすく解説します。最後には、インサイドセールスをさらに強化する手法として、リアルタイムに顧客とつながるWeb接客ツールの活用方法も紹介します。
目次
インサイドセールスとは?

営業活動の効率化や分業体制の中で、近年ますます重要性を増しているのがインサイドセールスです。
インサイドセールスの定義
インサイドセールスとは、電話・メール・オンライン会議システムなどを用いて非対面で行う営業活動のことを指します。従来の訪問型営業(フィールドセールス)とは異なり、営業担当が顧客先へ足を運ぶことなく、自社のオフィスやリモート環境から顧客対応を行えるのが特徴です。
リード(見込み顧客)との初期接点を作り、ニーズを丁寧にヒアリングしながら育成していく役割を担うため、「リードナーチャリング」とも密接に関わっています。
フィールドセールスとの違い
フィールドセールスは、商談のクロージングや契約交渉といった最終段階を担当するケースが多く、一件あたりの商談規模が大きいのが特徴です。一方、インサイドセールスは商談前の顧客を幅広くカバーし、リードの温度感を高めたうえでフィールドセールスへと引き渡します。
つまり、インサイドセールス=顧客接点の土台を築く役割、フィールドセールス=受注獲得の最前線 と整理でき、両者は補完関係にあります。
注目される背景と導入企業が増えている理由
インサイドセールスが注目を集める背景には、次のような要因があります。
- 技術の進化による営業手法の変化:オンライン会議システムやWeb接客ツール、CRMの高度化により、対面に頼らずに商談や顧客対応を行える環境が整いました。これにより、非対面でも効果的な営業活動が可能になっています。
- 営業効率の向上ニーズ:移動時間や日程調整の負担を減らし、より多くの顧客と効率的に接点を持てる体制が求められています。
- マーケティングとの連携強化:MA(マーケティングオートメーション)やCRMとの組み合わせにより、顧客データを活用した精度の高いアプローチが実現できるようになりました。
こうした背景から、SaaS企業をはじめ製造業や人材業界など、業種を問わずインサイドセールスを導入する企業が増えています。
インサイドセールスがリード獲得で果たす役割

インサイドセールスは単なる「顧客対応の省力化」ではなく、リードを効率的に育成し、営業成果を最大化するための重要な仕組みです。
見込み顧客を育成し商談化率を高める
リードを獲得しても、すぐに商談や契約につながるケースは多くありません。インサイドセールスは、顧客の検討段階に応じて適切な情報提供を行い、徐々に関心度を高めていく役割を担います。
たとえば、導入事例やホワイトペーパーを紹介することで顧客の理解を深め、将来的な商談化につなげます。これにより、ただの「リスト」から「有望な商談」へと育てるプロセスを実現できるのです。
営業とマーケティングの橋渡し
マーケティング部門が獲得したリードをそのまま営業部門に渡すと、温度感が低く、受注に結びつかないことが多々あります。そこで重要なのがインサイドセールスです。マーケティングから渡されたリードを精査し、接点を持ちながら温度感を把握したうえで、営業部門に引き渡します。
これにより、営業担当は成約可能性の高い顧客に集中できるため、営業効率の向上に直結します。
効率的にアプローチできる仕組み
インサイドセールスは、電話やオンラインミーティング、チャットなどのツールを活用し、短時間で多くの顧客と接触できます。
フィールドセールスが1日に数件しか訪問できないのに対し、インサイドセールスはその数倍以上の顧客と会話できるのが強みです。これにより、母数を広げながら効率的にリードを育成できる体制を構築できます。
リード獲得におけるインサイドセールスのメリット

インサイドセールスを導入することで、単にリード対応の効率が上がるだけでなく、組織全体の営業活動に大きな変化をもたらします。特に、以下のようなメリットが挙げられます。
効率的なリード対応で営業リソースを最適化
フィールドセールスだけでリードに対応しようとすると、移動や日程調整に時間がかかり、限られたリソースを十分に活用できません。
インサイドセールスを導入すれば、非対面で効率的にリードへアプローチでき、営業リソースを成約見込みの高い顧客に集中させることが可能になります。
顧客データに基づく戦略的アプローチ
インサイドセールスは、MA(マーケティングオートメーション)やCRMとの連携によって、顧客の属性や行動履歴を把握しながらアプローチできます。
たとえば、「資料をダウンロードした顧客」や「特定ページを複数回訪問した顧客」など、関心度が高いリードを優先してフォローできるため、戦略的かつ無駄のない営業活動が実現します。
有人対応による信頼感の向上
メールやチャットボットだけでは伝わりにくいニュアンスや疑問点も、インサイドセールスが有人で対応することで解消できます。
特にBtoB商材は高額かつ導入ハードルが高いため、「人が直接対応してくれる安心感」が信頼関係構築につながります。これが最終的にリード獲得から商談化、受注率の向上へと結びつきます。
インサイドセールスの成功事例

インサイドセールスの重要性や効果は理解していても、実際にどのような成果を生み出しているのか気になる方も多いでしょう。
ここでは、SaaS企業と製造業の2つの事例を取り上げ、インサイドセールスがどのようにリード獲得や商談化率向上に寄与しているのかを具体的に紹介します。
SaaS企業におけるインサイドセールス成功例(FORCAS)
ユーザベースが提供するBtoB SaaSプロダクト「FORCAS」では、営業体制の立ち上げ期にインサイドセールスを積極的に導入しました。
従来はフィールドセールスが中心で、マーケティングが獲得したリードに十分なフォローを行えず、商談化につながらないケースが課題でした。
インサイドセールスチームを立ち上げ、資料請求やセミナー参加などで得たリードに対して早期接点を持ち、顧客の課題感や検討度合いをヒアリング。段階的にナーチャリングを行う仕組みを構築しました。
その結果、営業体制立ち上げからわずか3か月で案件数は約2.5倍に増加。営業部門が有望なリードに集中できるようになり、効率的な商談創出に成功しました。
製造業での新規開拓に成功したケース(イトーキ)
オフィス家具大手の株式会社イトーキは、従来から展示会や既存顧客への営業が中心で、新規顧客開拓の効率化が課題となっていました。
営業DXの一環としてインサイドセールスを導入し、Webからの問い合わせや資料請求を起点に専任チームがフォローを開始。潜在顧客への電話・オンラインでの継続的なアプローチに加え、フィールドセールスとの役割分担を明確にしたことで、対応スピードと精度が向上しました。
その結果、新規顧客獲得数が大幅に増加。さらに既存顧客に対しても継続的な接点を持ち続けることで、関係性の強化にもつながりました。イトーキの取り組みは、伝統的な製造業においてもインサイドセールスが新規開拓の有効な手段となり得ることを示しています。
インサイドセールス導入でよくある課題と解決策

インサイドセールスは多くの企業で成果を上げていますが、導入すれば自動的に成果が出るわけではありません。実際の現場では、仕組みづくりや運用の中でさまざまな壁に直面するケースもあります。
ここでは代表的な課題とその解決策を紹介します。
リードの質が低く成果につながらない
マーケティング活動で数多くのリードを獲得できても、その多くが商談や成約に至らないケースは少なくありません。特に情報収集目的の段階にあるリードばかりでは、インサイドセールスがどれだけ接触しても成果が出にくくなります。
解決策としては、リードスコアリングを導入し、行動履歴や属性情報に基づいて優先度をつけることが有効です。これにより、成約可能性の高いリードから順にアプローチでき、効率的に成果を積み重ねられます。
アプローチのタイミングが合わない
顧客が関心を持っているタイミングを逃してしまうと、せっかくのリードも離脱してしまいます。特にBtoBでは検討期間が長いため、タイミングの見極めが難しいのが実情です。
解決策としては、Web行動データやメール開封率などをもとに「関心が高まった瞬間」を捉える仕組みを導入することが重要です。タイムリーに接点を持つことで、商談化につながる確率を大幅に高められます。
営業部門との情報共有不足
インサイドセールスが得た顧客情報が営業部門にうまく引き継がれないと、せっかく育成したリードも成果に結びつきません。逆に営業部門からのフィードバックがないと、インサイドセールス側も改善の方向性を見失います。
解決策としては、CRMやSFAを活用して情報を一元管理し、両部門で同じデータを参照できる体制を整えることが不可欠です。加えて、定期的なミーティングを設けて認識をすり合わせることで、部門間の分断を解消できます。
リード獲得を強化する具体的な方法

リード獲得の成果を安定的に高めるには、複数の施策を組み合わせて顧客接点を増やしていくことが重要です。
特にオンラインを起点とした取り組みは、短期間で効果が見えるものも多く、インサイドセールスの活動を支える基盤となります。
コンテンツマーケティングや広告との連動
ホワイトペーパーや導入事例記事などのコンテンツは、リード獲得に直結する代表的な施策です。特にBtoBでは、見込み顧客が課題解決のために情報収集を行うケースが多いため、課題に即した有益なコンテンツを用意することで自然な接点を生み出せます。
加えて、リスティング広告やSNS広告と組み合わせることで、課題意識が高まった顧客を自社サイトへ誘導し、コンテンツとセットでリードを効率的に獲得することが可能です。
ウェビナーやイベントでのリード創出
ウェビナーやオンラインイベントは、潜在層・顕在層の両方にアプローチできる強力なチャネルです。参加申し込み時に得られる属性情報に加え、イベント中のアンケート回答や質疑応答の内容からも、リードの温度感を把握できます。
また、イベント終了後に資料提供や個別相談につなげることで、商談化の確度を高めることができます。特に昨今はオンライン開催の普及により、地理的な制約なく幅広いリード獲得が可能となっています。
Web接客ツールを活用したリアルタイム対応
近年は、インサイドセールスの効率をさらに高める手段として、Web接客ツールの導入が進んでいます。特に、有人型のチャットや音声通話ができるツールは、サイト訪問者が関心を持った瞬間にアプローチできるのが強みです。問い合わせフォームや資料請求に至る前の段階で対話を始められるため、従来では取りこぼしていたリードを商談化につなげやすくなります。
実際に、株式会社OPTEMOが提供する「OPTEMO」は、インサイドセールスの現場で活用され、大きな成果を上げています。
- ユーザベース(INITIAL事業):従来はフォーム入力後にしか接点を持てなかった顧客に、CV前からアプローチ可能となり、インサイドセールスが能動的にリードを獲得できる体制を実現。マーケティングとの連携も進み、KPI達成にも貢献しました。
- KiteRa:Slack通知機能やページごとの最適化を活用し、従来は「待ち」の姿勢だったインサイドセールスが「攻め」のリード獲得へと転換。OPTEMO経由のリードは商談化率75%という高い成果を残しました。
このように、Web接客ツールは単なるサポート機能ではなく、インサイドセールスが成果を出すための「リアルタイム接点」を提供する存在となっています。
まとめ|インサイドセールスでリード獲得を加速させるために

インサイドセールスは、営業リソースの効率化とリードの質向上を両立できる手法として、多くの企業で導入が進んでいます。見込み顧客を育成し、商談化率を高めるだけでなく、マーケティングとの連携によって一貫した顧客体験を提供できる点が大きな強みです。
さらに、有人対応を取り入れることで「課題がまだ明確でない顧客」にも寄り添うことができ、問い合わせや商談に至る可能性を広げられます。これまで接点を持てなかった層にもアプローチできることは、企業にとって大きな収益機会の拡大につながります。
有人型チャットツール「OPTEMO」を導入すれば、匿名ユーザーにもリアルタイムで声をかけられ、商談獲得単価の削減や営業効率の向上を実現できます。フォーム入力や日程調整を待つのではなく、関心が高まった瞬間を逃さずアプローチできる点が、これまでの施策にはなかった新しい価値です。
以下の資料では、OPTEMOの具体的な機能や活用事例を紹介しています。今後のリード獲得施策を強化する参考として、ぜひご確認ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから