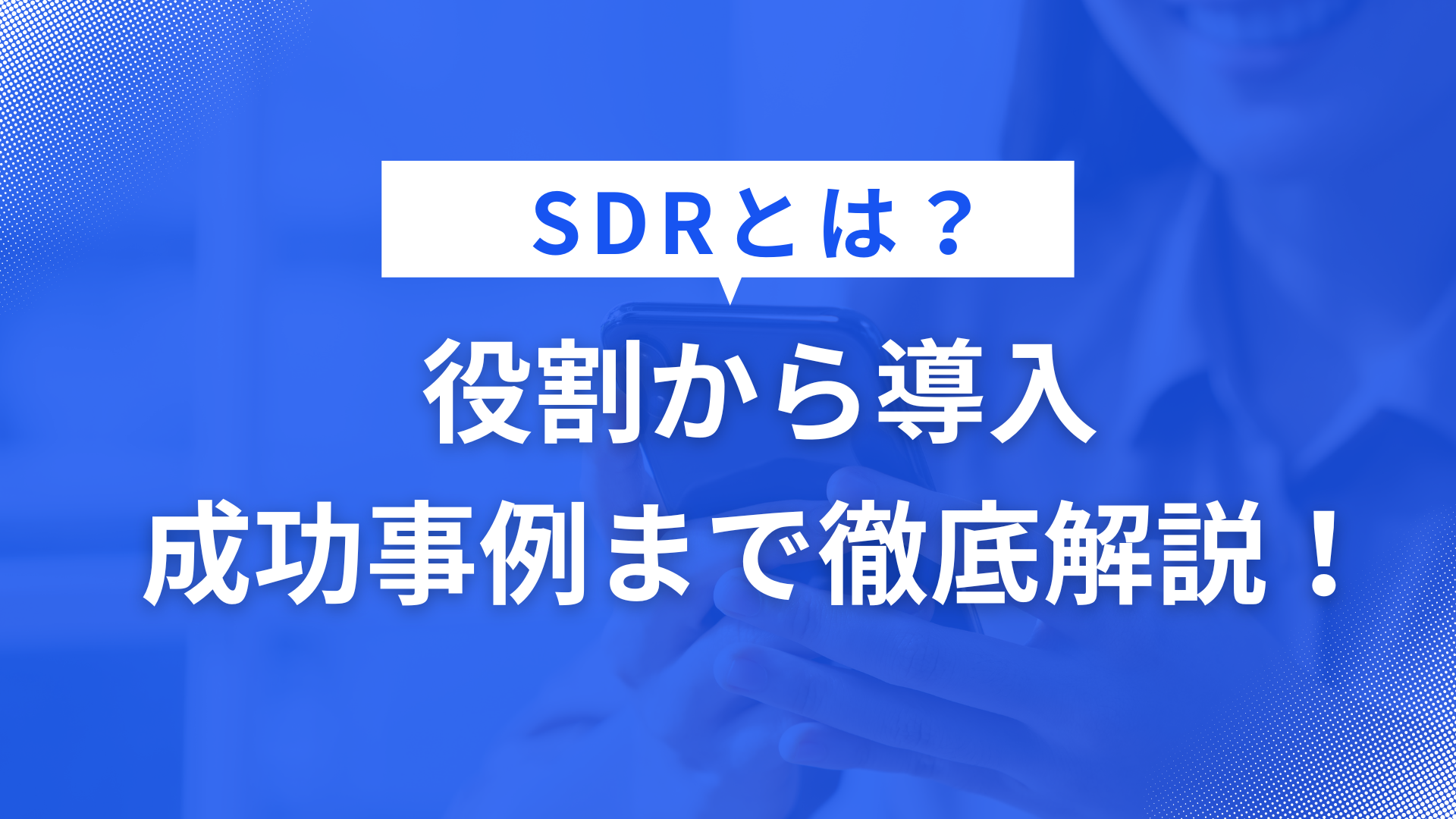リード獲得の課題とは?よくある失敗と解決のポイントを解説

企業の成長において欠かせないのが新規顧客の開拓。その入口となるのが「リード獲得」です。しかし、多くの企業がリード獲得施策に取り組むものの、成果が思うように出ず課題を抱えるケースは少なくありません。
本記事では、リード獲得施策の基本を整理し、よくある課題とその解決の考え方、さらに最新のアプローチについて解説します。
リード獲得施策とは?

リードという言葉はよく耳にするものの、その定義や段階を正しく理解していないと、施策や部門間の連携がちぐはぐになり、思うような成果につながりません。まずはリードの基本的な意味と分類を押さえておくことが重要です。
リードの定義と種類(MAL・MQL・SAL・SQLなど)
リードとは、将来的に顧客になる可能性を持つ「見込み顧客」を指します。たとえば、資料請求、セミナー参加、ホワイトペーパーのダウンロード、Webサイト訪問などのデジタル接点を含め、何らかの形で企業と接点を持った時点でリードと見なされます。
リードにはいくつかの段階があり、マーケティング活動から営業活動へと移行する過程で次のように分類されます。まず、マーケティング部門が初期段階で受け入れる MAL(Marketing Accepted Lead)。その中から、関心度や行動スコアなどを基準に 商談化見込みが高い と判断されるのが MQL(Marketing Qualified Lead) です。次に、営業部門がそのリードを精査し、アプローチ対象として受け入れたものを SAL(Sales Accepted Lead) と呼び、さらに受注確度が高いと判断されたリードが SQL(Sales Qualified Lead) に分類されます。
要点として、MQL=商談化見込みが高いリード、SQL=受注確度が高いリード と整理しておくと分かりやすいでしょう。これらの段階を明確に区別し、マーケティングと営業が共通認識を持つことで、より効率的なリード育成と商談化が可能になります。
営業・マーケティング活動における役割
リードは営業活動の出発点であり、新規顧客を生み出す源泉です。同時に、マーケティング施策が効果を発揮しているかどうかを測定する指標でもあります。
たとえば、広告やコンテンツマーケティングによってどれだけリードが獲得できたか、そのリードが営業の商談にどれくらい進んだか、といった流れを追うことで、施策全体の改善が可能になります。
つまり、リードは「営業とマーケティングの両方にとっての共通財産」であり、その扱い方次第で企業の成長スピードが大きく変わるのです。
なぜ多くの企業でリード獲得施策が重視されるのか
デジタル化が進んだ今、顧客は企業の営業担当に話を聞く前に、自らWebサイトやSNSで情報を集め、比較検討を行っています。
そのため、企業にとっては「問い合わせが来るのを待つ」のではなく、顧客が関心を示した段階で適切に接点を作ることが重要になりました。
たとえば、ある製品ページをじっくり読んでいる顧客は、その瞬間に強い関心を抱いている可能性があります。そのタイミングで接点を持てれば商談化につながりますが、逆に数日経ってからでは熱が冷め、他社に流れてしまうリスクもあります。
このように、リード獲得施策は「企業が顧客に選ばれる最初のチャンス」であり、今や事業成長のボトルネックになりやすい領域といえるのです。
リード獲得施策でよくある課題

リード獲得施策は多くの企業が力を入れる分野ですが、実際の現場では思うように成果が出ず、さまざまな壁に直面します。ここでは特によく見られる代表的な課題を整理してみましょう。
商談化までのリードタイムが長い
広告やコンテンツ施策によって一定数のリードを獲得できても、実際に商談へ進むまでに時間がかかるケースは少なくありません。リードが情報収集段階にとどまっている場合、関心度が高まるまでの期間が長く、営業が早い段階でアプローチしても成果につながりにくくなります。
こうした「リードタイムの長さ」は、商談化率の低下や営業リソースの分散を招く要因です。購買プロセスに合わせてリードを育成し、温度感に応じたタイミングで接点を持つ仕組みを整えることが求められます。
商談化率・成約率が低い
リードは集まっているのに、商談や受注につながらないという課題も多くの企業が抱えています。リードの優先度を判断できていなかったり、初期対応に時間がかかってしまったりすることが原因です。
せっかく関心を持ってくれたリードも、適切にフォローできなければ他社に流れてしまいます。
アプローチのタイミングがずれる
顧客が「詳しく知りたい」と思った瞬間を逃すと、関心は急速に冷めてしまいます。
たとえば、問い合わせから数日後にようやく営業が連絡しても、すでに競合に相談をしているケースは珍しくありません。適切なタイミングでのアプローチができるかどうかが、成果を大きく左右します。
マーケティングと営業が分断されている
マーケティング部門と営業部門の間でリードの定義や評価基準が異なると、獲得したリードが放置されるリスクが高まります。
マーケティングは「数を増やす」ことを重視し、営業は「質」を求めるため、両者のギャップが成果を妨げることもあります。部門間でリードに関する共通認識を持つことが不可欠です。
そもそも問い合わせされない
サイトへの訪問者数はあるのに、フォームの入力や問い合わせに至らないケースも少なくありません。
入力項目が多すぎる、ボタンの位置がわかりにくい、信頼感を持たせる情報が不足しているなど、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザー体験)の改善が必要な場合もあります。
結果として、「気になっていたけれど途中でやめた」という訪問者を多数生んでしまうことにつながります。
課題を解決するための考え方

検討顧客からリードになってもらうためには、ただ数を増やすのではなく、「どの顧客に・いつ・どのようにアプローチするか」を見極めることが欠かせません。
ここでは、実践的に役立つ3つの視点を紹介します。
見込み顧客の温度感を正しく把握する
単に「リードがあるかどうか」ではなく、その関心度や購買意欲を測ることが重要です。
たとえば、資料を請求しただけの人と、価格ページを何度も閲覧している人とでは、温度感が大きく異なります。こうした違いをスコアリングなどで数値化し、営業リソースを優先度の高いリードに集中させることで、商談化の確率を高められます。
顧客の行動データを営業に活かす
「どのページを見たか」「どのコンテンツをどのくらい読んだか」といった情報は、営業にとって貴重なヒントになります。
たとえば、製品比較ページを閲覧しているなら競合との違いを説明する、導入事例を見ているなら具体的な活用方法を紹介する、といった具合に相手の関心に合わせた提案が可能です。行動データをリアルタイムで共有できれば、営業の精度は一気に高まります。
最適なタイミングでアプローチする仕組みづくり
顧客が「もっと詳しく知りたい」と思った瞬間に声をかけられるかどうかで成果は大きく変わります。
たとえば、資料請求直後にフォローの連絡をすれば商談化率は上がりますが、数日経つと関心が薄れてしまうことも珍しくありません。マーケティング部門と営業部門が連携し、温度感が高まったタイミングを逃さずアプローチできる仕組みを整えることが不可欠です。
リード獲得施策を支援する最新の方法

リード獲得施策における課題を乗り越えるには、従来の施策を強化しつつ、新しいアプローチを取り入れることが求められます。
ここでは、現在多くの企業が取り組んでいる代表的な方法を整理してみましょう。
デジタル広告・SEO・コンテンツマーケティング
リード獲得施策の代表的な手法として、Web広告や検索エンジン最適化(SEO)、オウンドメディアによるコンテンツ発信は今も有効です。
検索キーワードに沿った記事や資料を用意することで、情報収集をしている潜在顧客と接点を持つことが可能です。ただし競合も同じように取り組んでいるため、差別化や継続的な改善が欠かせません。
MA(マーケティングオートメーション)やCRMの活用
リード獲得後に有効なのが、MAツールやCRMです。これらを活用すれば、顧客情報を蓄積・管理し、メール配信やスコアリングでリードを段階的に育成できます。
営業に引き渡す前に温度感を高められるため、商談化率の向上に寄与します。とはいえ、MAやCRMは「すでにフォーム入力を終えた後」のリードが中心となるため、それ以前の段階で接点を作ることはできません。
有人型のWeb接客ツールによるリアルタイム対応(チャット・音声通話)
従来の広告やSEOなどが流入前の施策だとすれば、有人型のWeb接客ツールは「流入後」に商談化を後押しする施策 です。
Webサイトを訪れたユーザーに対して、リアルタイムでアプローチできる点が特徴です。従来のチャットボットは定型的な回答に限定され、深いコミュニケーションや商談には発展しづらいものでした。
これに対し、有人型ツールは「特定のページを見ている」「長時間サイトに滞在している」といった行動を検知し、営業担当者に通知できます。
たとえばOPTEMOでは、ユーザーの行動データをもとにアラートを出し、その場でチャットや音声通話を開始できます。ユーザーは面倒な登録や日程調整をせずに担当者と会話できるため、フォーム入力前で離脱しそうな層を商談に導けるのが強みです。
EFO(フォーム入力最適化)が「入力完了率を上げる」ことに焦点を当てているのに対し、OPTEMOのような有人型ツールは入力前の段階で離脱を防ぎ、商談化を後押しする役割を担います。
他のマーケティング施策と組み合わせることで、リード獲得後のプロセスを最適化し、商談率を高めることが可能です。
まとめ|リード獲得の課題を乗り越えるポイント

リード獲得施策は企業成長の土台ですが、数や質、アプローチのタイミング、部門連携など、多くの課題に直面します。これらを解消するには、顧客の温度感を把握し、リアルタイムに接点を持てる仕組みを整えることが重要です。
従来の施策に加えて、有人型のWeb接客ツールを組み合わせれば、フォーム入力前の段階で離脱を防ぎ、商談化率を高めることが可能になります。
以下の資料では、OPTEMOの具体的な機能や活用事例について紹介しています。詳細はぜひこちらからご確認ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから