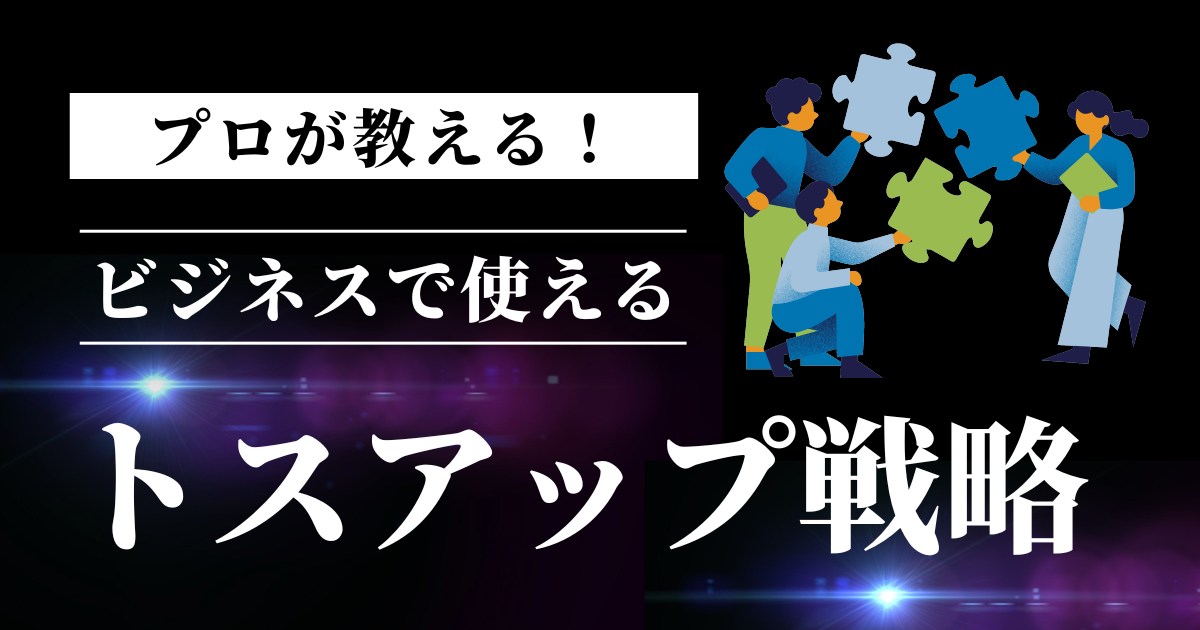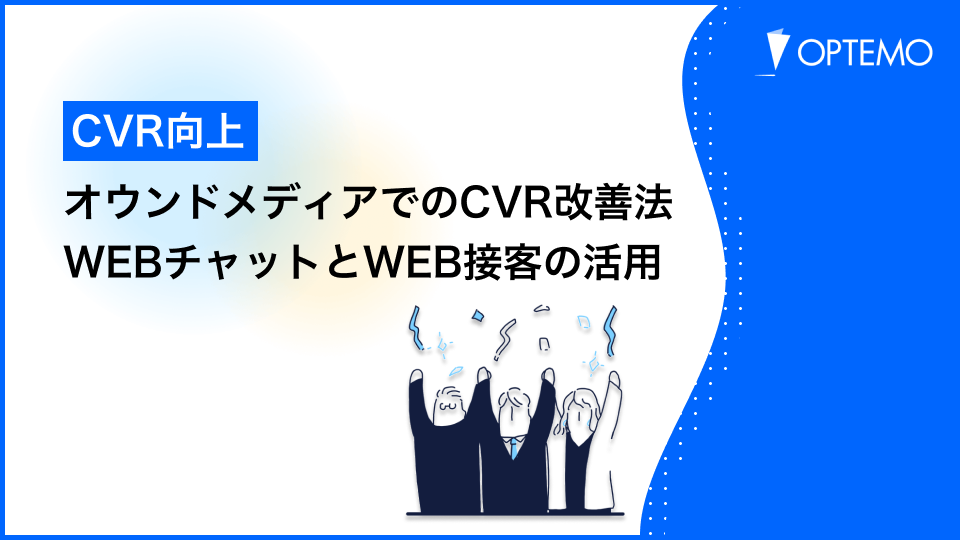リード獲得とは?マーケティングで使える具体的な方法と成功のポイント

オンラインでの顧客接点が当たり前となった今、企業にとっていかに確度の高いリードを効率よく獲得するかは欠かせないテーマとなっています。広告やSEOを駆使して集客をしても、見込み顧客を逃してしまえば商談や成約にはつながりません。
そこで本記事では、リード獲得施策の基本から具体的な方法、さらに成果につなげるためのポイントを整理します。
目次
リード獲得施策とは?

リード獲得とは、自社の商品やサービスに興味を持つ人を見つけ出し、将来的な顧客候補として接点をつくる取り組みを指します。単なるアクセス数の増加ではなく、成約につながる可能性のある相手との関係づくりが目的となります。
リード(見込み顧客)の意味
リードとは、将来的に顧客になる可能性を持つ「見込み顧客」を指します。まだ購入や契約には至っていないものの、自社の商品やサービスに何らかの関心を示している段階です。
たとえば、次のような行動をとった人は「リード」とみなされます。
- 資料請求やホワイトペーパーのダウンロードをした
- メルマガやニュースレターに登録した
- ウェビナーやセミナーに申し込んだ
- お問い合わせフォームに入力を始めた
つまりリードとは「ただの訪問者」ではなく、すでに自社に興味を持ち、なんらかの個人情報を企業に送っている将来顧客になり得る層のことを指します。
リード獲得が企業の成長に直結する理由
新規顧客の獲得には、広告費や営業工数など大きなコストがかかります。一方、すでに自社に関心を持っている検討顧客は、ゼロから顧客を探すよりも契約につながる可能性が高いため、効率的に売上を拡大できる対象です。
リードは関心度によって「コールドリード」「ウォームリード」「ホットリード」に分類されます。コールドリードは認知段階にあり、今すぐの購買意欲は低いものの、将来的に顧客化する可能性を持つ層。ウォームリードは、すでに興味・関心を持ち情報収集を始めている層。そしてホットリードは、比較検討段階にいて、近い将来購買・契約に至る可能性が高い層を指します。
このように、ホットリードにどれだけ効率的に接触し、ウォームリードやコールドリードを段階的に育成できるかが、企業の成長を大きく左右します。
マーケティングと営業での役割の違い
リード獲得においては、マーケティングと営業がそれぞれ異なる役割を担います。
- マーケティング:広告、SEO、コンテンツなどを活用して、自社に興味を持つリードを集める段階を担当。より多く、かつ質の高いリードを継続的に獲得することがミッションです。
- 営業:マーケティングが集めたリードに対して商談を行い、契約や受注へと進める段階を担当。信頼関係を築き、最終的な意思決定を後押しする役割を担います。
両部門が連携しないと、せっかく獲得したリードも「営業に渡されないまま放置される」「営業から質が低いと不満が出る」といったミスマッチが発生し、成約機会を逃してしまいます。マーケティングと営業をシームレスにつなぐ仕組みづくりこそが、リード獲得を成果に変える最大のポイントです。
リード獲得のための具体的な方法

リードを集めるにはひとつの手段に頼るのではなく、複数の施策を組み合わせることが重要です。オンラインとオフライン、短期的な成果につながる方法と長期的に効いてくる方法をバランスよく活用することで、安定したリード獲得が実現できます。
コンテンツマーケティング(記事・ホワイトペーパーなど)
見込み顧客にとって役立つ情報を記事や資料として発信し、信頼を積み重ねながら興味を高めていく方法です。検索ユーザーの課題を解決する記事や業界の最新動向をまとめたホワイトペーパーは、検討段階の手前にいる潜在層に有効です。
たとえば「初心者向けの記事」や「入門的なホワイトペーパー」で関心を持ってもらい、興味が高まった層にはSEO記事などの自社オウンドメディアでより専門的な情報を提供する──そんな段階的なコミュニケーション設計が効果的です。
SEOやリスティング広告での流入施策
GoogleやYahoo!といった検索エンジンの結果画面に露出することで、商品やサービスを探している顕在層に直接アプローチできます。SEOは、自社が作成するコンテンツ記事を特定のキーワードで上位表示させる中長期的な施策です。一方、リスティング広告は同じく特定キーワードの検索時に即時で表示される短期的な施策で、即効性があります。
特にBtoBでは「サービス名+比較」「導入 事例」などの検索が多く、情報収集中の企業を逃さず捉えることが可能です。SEOとリスティング広告を組み合わせることで、長期的な流入基盤の構築と短期的なリード獲得の両立が期待できます。
フォーム設置やホワイトペーパーDLによる情報収集
自社サイトに問い合わせフォームやダウンロード資料を設置し、ユーザーに連絡先や会社名を入力してもらうことでリード情報を得る方法です。
基本的な項目(氏名・会社名・メールアドレス)に絞れば入力ハードルが低く、離脱を防げます。逆に、詳細情報を求めすぎると「面倒そう」と感じられ、入力途中で離脱する可能性が高まります。入力項目は「最小限」を意識することがポイントです。
ウェビナーや展示会などのオフライン施策
顧客とリアルタイムで接点を持ち、直接質問や相談を受けられる場は、信頼構築に大きく貢献します。ウェビナー(オンラインセミナー)はコストを抑えつつ幅広い層にリーチでき、展示会や対面セミナーは少数でも濃い関係づくりにつながります。
製品デモや事例紹介を通じて、顧客が「自分ごと」として具体的に利用シーンをイメージしやすくなるのが特徴です。
リードマーケティングを成功させるためのポイント5つ

リード獲得の施策は数多く存在しますが、ただ闇雲に取り組むだけでは効果が限定的になってしまいます。成果につなげるためには、共通して押さえておくべき基本的なポイントがあります。
ここでは特に重要な5つを紹介します。
量だけでなく「質の高いリード」を意識する
単純にリスト数を増やすだけでは売上には直結しません。たとえば、幅広く集めた100件のリードのうち、実際に商談につながるのが数件であれば、営業リソースが分散してしまいます。
重要なのは、自社の商品やサービスにフィットしやすい「質の高いリード」を見極めて集めることです。そのためには、ターゲットを明確に定義し、課題解決に直結する情報を提供することが欠かせません。
顧客の関心が高い瞬間を逃さない仕組みを作る
ユーザーがフォーム入力を始める直前や資料請求を検討しているタイミングは、最も温度感が高まっている瞬間です。この時に接点を持てれば、商談化の可能性がぐっと高まります。
逆にこの瞬間を逃すと、比較検討の段階で競合に流れてしまうこともあります。行動データをもとに、滞在時間や閲覧ページ数から「今まさに検討している」と判断できる仕組みを備えておくことが重要です。
チャットボットを活用しつつ、柔軟な対応を意識する
Web上で顧客対応を効率化するうえで、チャットボットは有効な手段のひとつです。FAQ対応や定型的な質問に即時で答えられるため、ユーザーの疑問をその場で解消し、離脱を防ぐ効果が期待できます。
ただし、営業や導入相談といった領域では、より柔軟な会話が求められます。たとえば「このサービスを自社の規模で導入できるのか」「料金体系はどうなるのか」といった踏み込んだ質問には、定型回答だけでは十分に対応できません。
チャットボットに加えて有人対応を組み合わせることで、相手の温度感に合わせたコミュニケーションが可能となり、信頼関係を築きながら商談化のチャンスを最大化できます。
営業とマーケティングのデータを統合して活用
マーケティングが集めたリード情報と、営業が持つ商談・契約の情報が分断されていると、成果に結びつきにくくなります。CRMやSFAを活用して両部門のデータを一元管理すれば、たとえば「どの施策で獲得したリードが商談化しやすいか」「成約に至るまでの接点は何だったか」といった分析が可能です。
これにより、マーケティングはより精度の高い施策を打ち出せ、営業は見込み度の高いリードに集中できます。
簡単に導入・運用できる体制を整える
マーケティング施策は短期間で結果が出るものではなく、継続して改善を重ねることで成果が積み上がります。そのためには、現場で無理なく運用できるシンプルな仕組みが必要です。
設定や運用が複雑なツールは定着しにくく、結局使われなくなるケースも少なくありません。シンプルに導入でき、日常業務に組み込みやすい体制を整えることで、長期的に安定したリード獲得が可能になります。
リード獲得とマーケティング施策の課題

リードを集めるための取り組みは年々多様化していますが、その分だけ思うように成果につながらないケースも少なくありません。
どのような場面でつまずきやすいのかを理解しておくことが、改善の第一歩になります。
チャネルを増やすだけでは十分ではない
広告、SEO、展示会やウェビナーなど、新しいチャネルを開拓すること自体は有効な施策です。しかし、ただ流入経路を増やすだけでは商談には直結しません。
チャネルごとにリードの質や温度感は異なるため、獲得後に適切なアプローチや育成施策を組み合わせなければ、せっかくのリードが活かしきれないまま終わってしまいます。
チャットボットでは顧客の温度感を掴みにくい
チャットボットは定型的な問い合わせに即時で対応できるため、カスタマーサポートの領域では効果を発揮します。しかし営業領域になると「相手がどの程度関心を持っているのか」「今まさに話を聞きたいと思っているのか」といった温度感を判断するのは難しいのが実情です。
結果として、リードの見極めや商談化につなげる段階では限界が生じます。
CVに至らず離脱してしまうリードが多い
多くのユーザーは、問い合わせフォームの入力や資料請求といったCV(コンバージョン)に到達する前にサイトを離脱しています。興味を持って訪問したものの、「入力項目が多くて面倒」「疑問が解消されないまま不安になった」といった理由で途中離脱してしまうのです。
つまり、営業に引き渡す前の段階でリードが失われているのではなく、そもそもCVに至る前に機会損失となっているケースが非常に多いのが課題です。
有人型チャットツールによるリード獲得の強化

従来のフォームやチャットボットでは拾いきれなかった関心度の高い瞬間を捉えられるのが、有人型チャットツールの大きな特徴です。
ユーザーの行動を見極め、より良いタイミングでアプローチできる仕組みがリード獲得の成功率を高めます。
訪問者の行動をリアルタイムで可視化できる
OPTEMOでは、Webサイトを訪れているユーザーが「どのページを見ているのか」「どのくらいの時間滞在しているのか」といった行動をリアルタイムで確認できます。
たとえば、製品ページを長時間閲覧しているユーザーや、料金プランの比較ページを行き来しているユーザーは、関心度が高いと判断できます。こうした行動をいち早く把握することで、営業担当者が「今この瞬間に声をかけるべき相手」を見極め、タイムリーに接点を持つことが可能になります。
より良いタイミングでチャットや通話を開始できる
ユーザーがフォーム入力を完了する前の段階では、ちょっとした疑問や不安がきっかけで離脱してしまうことがあります。たとえば「入力項目が多すぎて負担に感じる」「費用感がわからないまま迷っている」といったケースです。
OPTEMOは「長時間滞在している」「特定のページを繰り返し見ている」といった行動をトリガーにアラートを通知できます。その結果、担当者がリアルタイムでチャットや通話を立ち上げ、訪問者の疑問をその場で解消することができ、離脱を防いでCV(コンバージョン)につなげやすくなります。
CRM/SFAとの連携で営業活動を加速させる
さらに、OPTEMOはSalesforceやHubSpotなどのCRM、あるいはSFAツールと連携できます。これにより、訪問者とのやりとりや行動履歴を顧客データとして蓄積し、マーケティングから営業への引き継ぎをスムーズに行うことが可能です。
たとえば「料金ページを何度も閲覧し、チャットで見積もりの話をしたリード」がそのまま営業に渡れば、担当者は高い確度の商談として優先的に対応できます。入力完了後の顧客対応はこれまでどおりインサイドセールスが担いますが、その前段階でCVを最大化する仕組みを補強できるのがOPTEMOの強みです。
まとめ|リード獲得の成果を高めるには有人型マーケティングが鍵

リード獲得の施策は多様化していますが、従来の広告やSEO、フォーム施策だけでは「関心度の高い瞬間」を逃してしまい、商談化につながらないケースが少なくありません。有人型チャットツールを組み合わせることで、この限界を補い、効率的にリードを商談へと導くことが可能になります。
また、訪問者の行動をリアルタイムで把握し、より良いタイミングで声をかけられる仕組みは、マーケティングと営業をシームレスにつなぐ新しい流れを生み出します。営業は「温度感の高いリード」に集中でき、マーケティングは施策の成果をより正確に分析・改善できるようになります。
OPTEMOは、こうした有人型マーケティングを実現するための支援ツールです。フォーム入力前の訪問者に寄り添い、離脱を防いでそのままCVにつなげることができる点が大きな強みです。
以下の資料では、OPTEMOの具体的な機能や活用事例について詳しく紹介しています。より深く知りたい方は、ぜひこちらからご確認ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから