EFO(入力フォーム最適化)とは?改善方法・メリット・フォーム後の成果を伸ばす次の一手
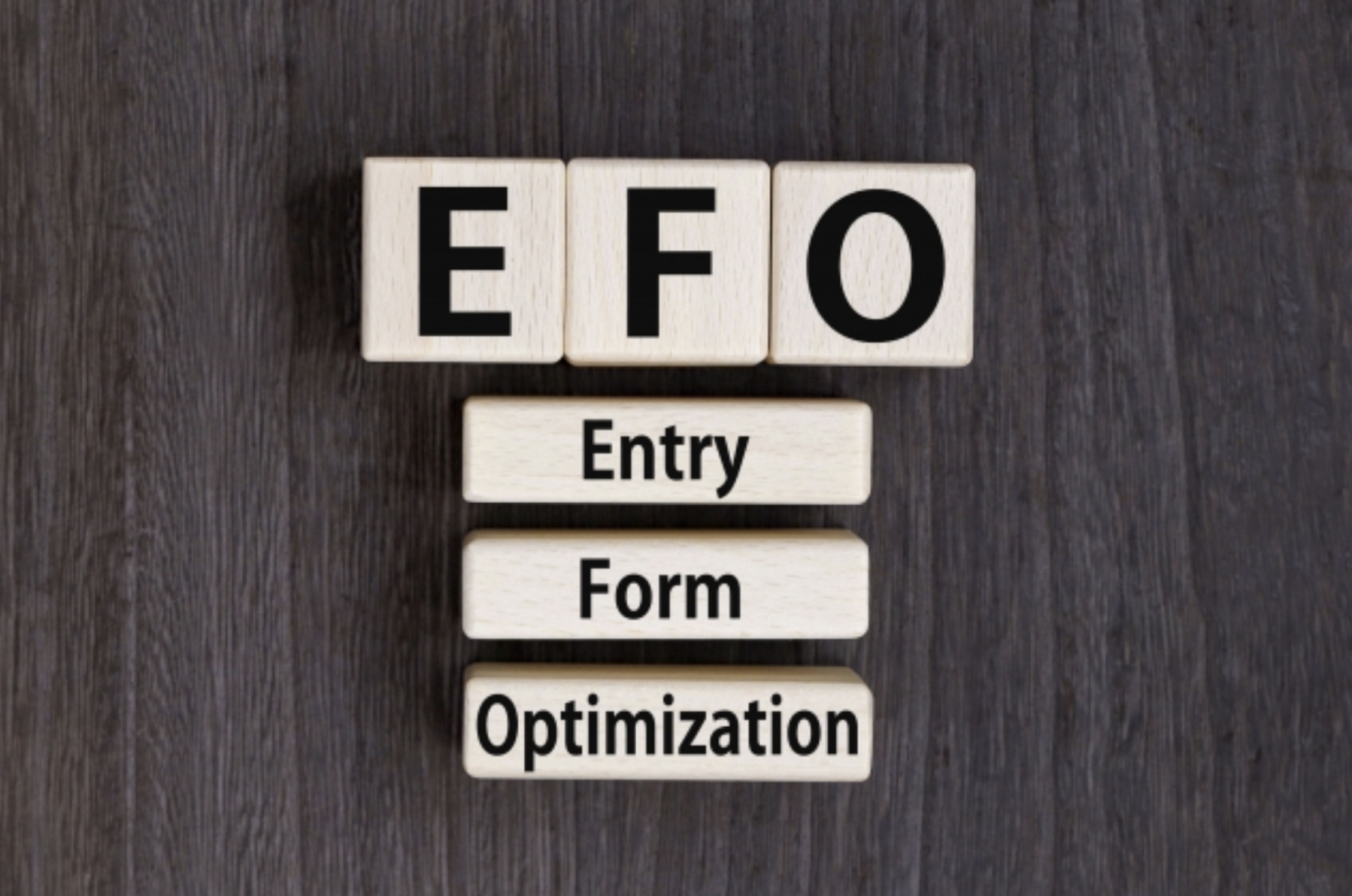
成果を上げるWebサイトを作るには、アクセス数やデザインだけでなく、「入力フォームの最適化(EFO)」にも注目が集まっています。どれだけ優れたコンテンツや広告施策を講じても、フォーム入力が完了されなければ、リード獲得にはつながりません。
本記事では、EFOの基本的な考え方と具体的な改善方法、得られるメリットを解説したうえで、「フォーム完了後のアプローチ設計」という次のステップにもフォーカス。EFOだけでは改善しきれない商談化率の壁をどう乗り越えるか、実際の企業事例を交えてご紹介します。
目次
EFO(入力フォーム最適化)対策とは

「Webからの資料請求や問い合わせを増やしたいのに、なかなかコンバージョンにつながらない」──そう悩む企業は少なくありません。
その原因の一端として、実は入力フォームの設計にある場合があります。
EFOとは?なぜ注目されているのか
EFOとは、「Entry Form Optimization(エントリーフォーム最適化)」の略で、Webサイト上の入力フォームをより使いやすく・入力しやすく整える施策を指します。
多くの企業が広告やSEOに力を入れてWebサイトへの訪問者を増やしていますが、最終的なコンバージョン(CV)を決めるのは入力フォームの完成です。つまり、どれだけページの内容に興味を持ってもらっても、フォームが分かりづらかったり入力項目が必要以上に多いとと、ユーザーはそこで離脱につながります。
特にBtoBサイトでは、「資料請求」「お問い合わせ」「サービス申込」などのアクションを取ってもらうことがビジネス成果に直結するため、フォーム改善=収益改善といっても過言ではありません。
近年では、広告費や集客施策の費用対効果を高めるためにも、入力フォームというコンバージョン直前の体験の最適化に注目が集まっています。
よくある入力フォームの課題例
入力フォームで離脱が起きる原因は、ちょっとした使いにくさ”やわかりにくさ”です。ここでは、代表的な課題をいくつか紹介します。
項目が多すぎる
「会社名」「部署名」「電話番号」「予算感」など、情報をたくさん集めたい気持ちは分かりますが、入力項目が多すぎるとユーザーの心理的ハードルが一気に上がります。
特に初回接触の段階では、最低限の情報だけで完了できるようにするのが理想です。
モバイルフレンドリーではない
スマートフォンユーザーが主流となった今、PCと同じフォームをそのままスマートフォンに表示していると離脱につながります。
入力欄が小さかったり、タップしづらい位置に配置されていたりすると、ユーザーは途中で入力を諦めてしまうことも。
入力エラーがわかりにくい
郵便番号や電話番号などで形式ミスをしても「どこが間違っているか分からない」というフォームは、ユーザーにとって大きなストレスです。
エラー時には、その場でリアルタイムにメッセージを表示する、間違った欄を赤くするなど、視覚的にわかりやすく改善することが求められます。
EFO対策のメリット

入力フォームの最適化は、地味に見えて実は非常に効果的な改善施策です。広告やコンテンツ施策と比べて少ない工数で取り組めるうえに、コンバージョン(CV)に直結する成果が出やすい領域として注目されています。
以下では、EFOによって得られる代表的なメリットを見ていきましょう。
離脱率の改善によるCVR向上
入力フォームを最適化することで、途中での離脱を防ぎ、CVR(コンバージョン率)の改善につなげることができます。
たとえば、入力項目を最小限に絞ったり、エラー表示をわかりやすくしたりといった小さな改善でも、成果が目に見えて現れるケースは少なくありません。
また、広告やSEOなどで集客施策に注力している場合でも、その流入を確実に成果へつなげるためには、フォームの最適化が欠かせません。
フォーム改善は、コンテンツを増やしたりキャンペーンを打つよりもスピーディかつ低コストで実行でき、早期に成果が期待できる点が大きなメリットです。
ユーザー体験(UX)の向上
EFOのもう一つの大きな価値は、ユーザー体験(UX)の改善です。
たとえば、スマートフォンで操作しやすいデザインや、入力ミスをすぐに指摘してくれるフォームは、「この会社は丁寧に作られているな」という安心感や信頼感をユーザーに与えます。
特にBtoBのWebサイトでは、最初の接点がこのフォームになるケースも少なくありません。つまり、入力のしやすさ=企業の第一印象になることもあるのです。
「問い合わせしづらい」「何を入力すればいいのか迷う」といったストレスを与えるフォームでは、いくらサービスが魅力的でもチャンスを逃してしまう可能性があります。
見た目の派手さではなく、使いやすさにこだわることこそ、成果につながるフォーム改善の本質といえるでしょう。
EFOの限界とその先にある課題

フォームの設計を改善することで、離脱率を下げることができます。しかし、どれだけフォームの構造やUIを最適化しても、最終的に入力するかどうかを決めるのはユーザー自身の心理です。
つまり、EFOだけでは拾いきれない迷いやためらいが、フォーム画面の中には確かに存在しているのです。
フォーム画面までたどり着いたユーザーが最大の機会損失ポイント
資料請求や問い合わせページまで遷移したものの、そのまま離脱してしまうユーザーは想像以上に多いと言われています。
実際、フォーム画面に到達したということは、ユーザーの関心はかなり高い状態です。しかし、
- 項目数が多くて入力をためらう
- 自分が対象になるか不安
- もっと情報を見てから判断したい
といった心理的なハードルから、入力を開始する前にページを離れてしまうのです。
この「フォーム入力直前の迷い」を取りこぼしてしまえば、せっかくの有望なリードをCVにつなげられないまま終わってしまう可能性があります。
EFOだけでは届かない迷っているユーザーに、声をかけられるかがカギ
EFOでフォームの設計を改善すれば、操作性や視認性といったUXのハード面は向上します。しかし、ユーザーの「これで申し込んでいいのかな?」「わからないことがある」という心理的な不安まで完全に解消できるわけではありません。
このような場面で効果を発揮するのが、リアルタイムでユーザーに声をかけられる接客ツールです。
たとえば、
- 一定時間ページに滞在している
- スクロールを繰り返している
- 入力フォームに手をつけないまま停止している
といった行動をトリガーに、チャットやポップアップで「お困りですか?」とアプローチすることで、迷っていたユーザーの不安を解消し、フォーム入力への一歩を後押しできます。
フォーム完了よりも直前にアプローチできる体制が、CVR改善の要に
フォームを完了した後のアプローチは他の多くの企業でも整備されていますが、フォーム入力前〜途中の「離脱リスクの高いタイミング」で対話できる体制は、まだ差別化ポイントになり得ます。
OPTEMOのようなツールを活用すれば、Webサイト訪問者の動きをリアルタイムで把握し、「今まさに迷っている」ユーザーに対してチャットや音声でサポートを開始できます。
CVRを底上げしたい場合、フォーム完了後ではなく、直前でのサポート設計が鍵となるのです。
フォーム入力直前のアプローチ改善で成果を伸ばす方法

EFO(入力フォーム最適化)によって、フォームの構造やUIを改善することで、離脱率を抑えることは可能です。
しかし実際には、「入力するかどうか迷っているユーザー」への一押しがなければ、CVには至らないケースも多くあります。
特にフォーム画面に到達してから、入力に至らず離脱するユーザーは少なくありません。
ここでは、フォーム入力直前の“迷い”をチャンスに変えるリアルタイム接客の方法と、その実現手段についてご紹介します。
①:リアルタイム接客で迷っているユーザーの背中を押す
フォーム画面まで進んだということは、ユーザーの関心はすでに高い状態です。
しかし、以下のような不安や迷いから、入力を始める前に離脱してしまうユーザーも多く存在します。
- このサービスは自分にも使えるのだろうか
- 費用や契約条件がまだわからない
- 問い合わせるほどではないが、少し聞いてみたいことがある
こうした心理的なハードルは、フォームの設計だけでは取り除けません。
そこで効果的なのが、リアルタイムでユーザーに声をかけられる接客設計です。
たとえば、
- ページ滞在時間が長い
- フォームまで進んでいるが入力が始まっていない
- スクロールやマウス操作を繰り返している
といった行動をトリガーに、チャットで「何かお困りですか?」と自然に声をかけることで、ユーザーの迷いをその場で解消し、フォーム入力を後押しできます。
②:OPTEMOの特徴|リアルタイムで迷いに寄り添う設計
リアルタイム接客ツール「OPTEMO(オプテモ)」は、まさにフォーム入力直前のユーザー心理に応える設計がなされています。
ワンクリックで会話スタート、事前準備は不要
訪問者が特定の行動を取った瞬間に、チャットや音声通話をワンクリックで開始できるため、ユーザーの「今、ちょっと聞きたい」に即座に応えられます。
面倒なURL発行や個人情報の入力、日程調整も不要です。
Webサイトにコードを埋め込むだけで導入完了
既存のフォームやCMSを変更せず、スピーディに運用をスタートできます。SalesforceやHubSpotなどのCRM/MAツールとも連携可能で、マーケティングチームやIS部隊との連携もスムーズです。
「迷っている瞬間」を逃さない接客体制を構築
EFOでフォームの完成度を高めたうえで、OPTEMOを併用することで、CVに踏み出す最後の一押しをサポートできます。チャットボットでは難しい「有人対応」によって、迷っているユーザーと人間らしい対話を築けるのも大きなポイントです。
CVR(コンバージョン率)をさらに底上げしたいと考えるなら、フォーム入力後ではなく、前の迷いにアプローチできる設計がカギとなります。OPTEMOのようなリアルタイム接客ツールは、EFOだけでは拾いきれない“心理的離脱”を防ぎ、CVへとつなげる強力な武器になるでしょう。
問い合わせ対応をOPTEMOに切り替え、成果を上げた事例2選

EFOなどの施策でフォームの完了率が改善しても、その後の問い合わせ対応が属人的・非効率であれば、せっかくの顧客体験を損ねてしまうことがあります。
ここでは、従来はメールや電話で対応していた問い合わせを、OPTEMOのリアルタイム接客に切り替えたことで、大幅な効率化と体験向上を実現した2社の事例を紹介します。
事例①:毎月160時間のリソース削減と即時サポートの両立

株式会社パートナープロップでは、PRM(パートナーリレーションマネジメント)ツールを提供する中で、ベンダー・パートナー・エンドユーザーからの問い合わせ対応が大きな業務負荷となっていました。
サポートは1名体制で、数千人規模のユーザーからの日々の問い合わせをメール中心に対応していたため、リードタイムの長さや対応の属人化が課題でした。
そこで導入されたのがOPTEMO。従来メールで受けていた問い合わせをチャット形式のリアルタイム対応に置き換えたことで、最短1分・平均3〜10分以内での即時対応が可能に。
結果として、毎月160時間以上の工数を削減しながらも、対応品質とスピードを両立。
CS担当者は本来注力すべき「パートナープログラムの企画・活性化」へ集中できる体制を実現し、「サポートとサクセスの両立」を形にした好事例です。
事例②:問い合わせ対応の効率化から始まり、3か月でROI300%超を達成

株式会社アンドパッドでは、これまでメールや電話を中心に対応していたWeb来訪ユーザーからの問い合わせ業務に課題を抱えていました。
そこでOPTEMOを導入し、フォーム送信を伴わない段階からでもリアルタイムで接客ができる体制へと切り替え。ユーザーと直接チャットで対話することで、潜在層との接点も増加し、結果として商談や受注にもつながる成果が生まれました。
導入後は、LP閲覧中のユーザーとのチャットからそのままCVや商談へつながるケースが続出。導入3か月でROIは300%を突破し、投資対効果の高さが社内でも評価されました。
また、既存ユーザーと新規見込みユーザーを区別したチャット導線の設計により、アップセル・クロスセルにも波及効果が生まれています。
OPTEMOは、問い合わせチャネルのリアルタイム化によって今すぐ聞きたいユーザーにタイムリーに対応できる体制を構築し、対応速度・満足度・業務効率のすべてを底上げした事例といえるでしょう。
まとめ|CVR改善のその一歩手前に寄り添うアプローチを

EFO(入力フォーム最適化)によってフォームの完了率を高めることはできますが、その直前に存在する“迷いやためらい”に対応できていなければ、CVには至りません。
特にBtoBサイトにおいては、「申し込むほどではないけれど、少し相談してみたい」「気になることを聞いてから判断したい」といったユーザーの心理的ハードルが存在しています。
そのような入力前のためらいを察知し、リアルタイムに声をかけて対話へ導ける体制こそが、CVR改善のカギです。
OPTEMOのようなツールを活用すれば、Webサイト上でユーザーの行動を見ながら、最適なタイミングでチャットや音声で話しかけることが可能になります。
また、従来メールや電話で行っていた問い合わせ対応もOPTEMOに置き換えることで、対応スピードの向上と業務効率化を両立できます。
「入力して終わり」ではなく、「入力される前に、寄り添って導く」そんな一歩手前の設計こそ、これからのフォーム改善・接客設計に求められる視点です。
なお、以下の資料では、OPTEMOの具体的な機能や導入事例をご紹介しています。
「CVの前でユーザーが離脱してしまう」「問い合わせ対応に課題がある」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひご覧ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから




