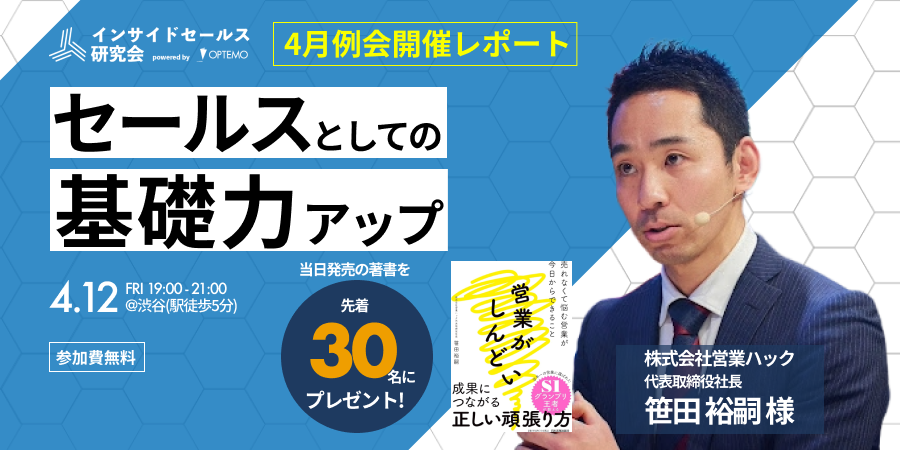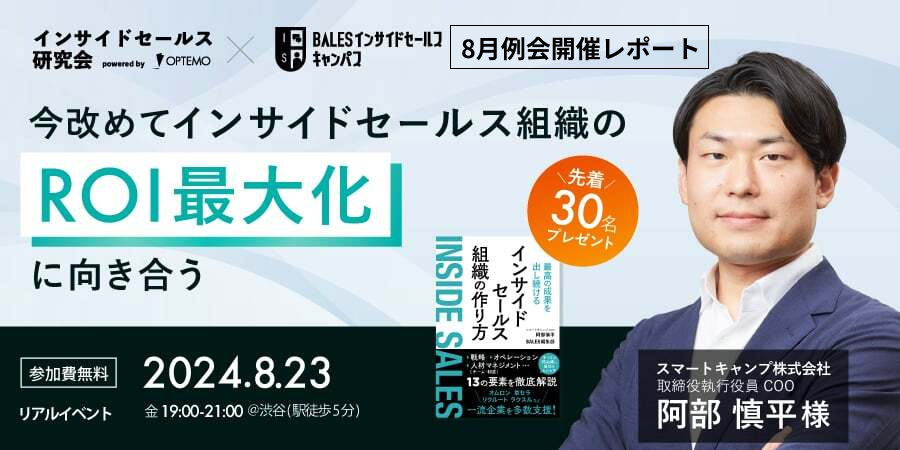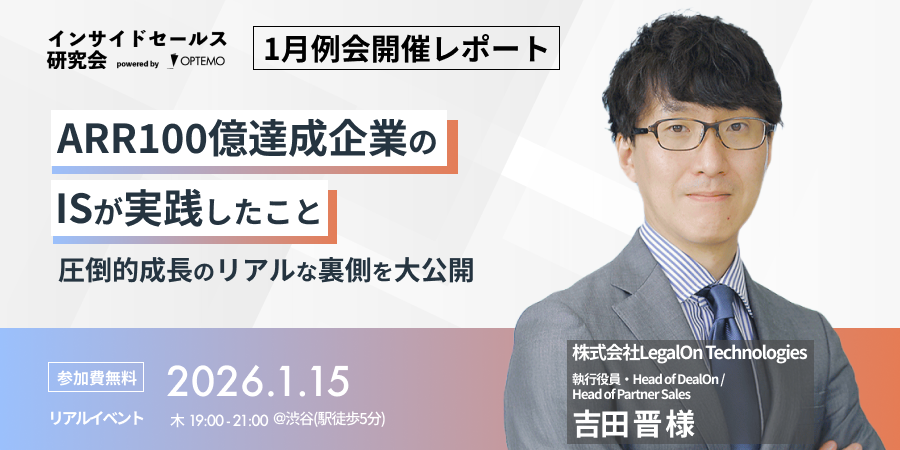インサイドセールス研究会2025年8月例会レポート
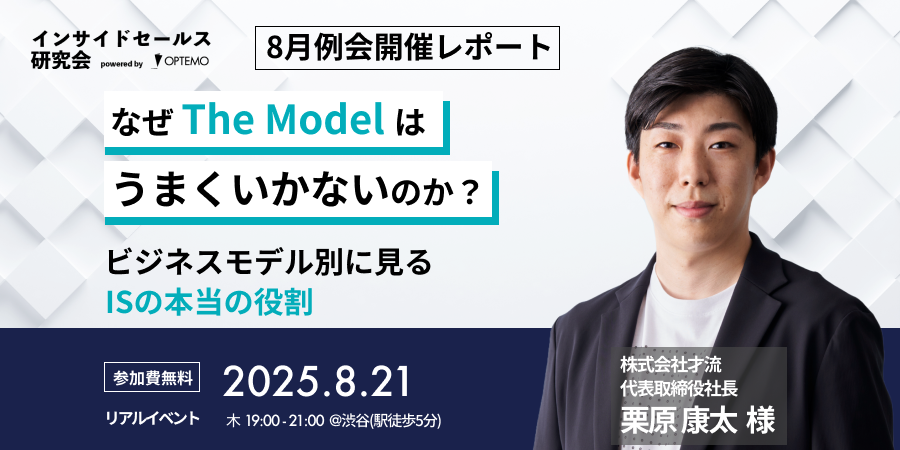
目次
インサイドセールス研究会について
インサイドセールス研究会は、『会社を超えてインサイドセールス同士がつながり「師と友」を作れる場』として株式会社OPTEMOが運営しているコミュニティです。
インサイドセールスという業務の性質上、社外での横のつながりが少ないという声を受け、2023年3月からこのコミュニティの運営を始めました。毎月特別なゲストを迎えて実践的なノウハウを提供しています。また、Facebookのグループで情報発信もしており、誰でも無料で参加できます。
https://optemo.co.jp//lp/is_ken
今回のテーマ
今回のイベントでは、株式会社才流(さいる)の栗原康太様をゲストにお迎えしました。「なぜThe Modelはうまくいかないのか?ビジネスモデル別に見るISの本当の役割」というテーマで登壇していただきました。
モデレーターはOPTEMOの竹田卓生(@Toy_optemo)が務めました。
栗原様ご講演

今回の登壇者である栗原様は株式会社才流(さいる)の代表取締役社長を務めており、コンサルティング会社を経営されています。事業開発・マーケティング・セールス領域のコンサルティングを提供し、多くのBtoB企業の成長支援に取り組まれてきた実績をお持ちです。
栗原様は新卒でガイアックスに入社後、1日150件のテレアポをする営業職からキャリアをスタートされました。その後、マーケティング担当や事業責任者を経て独立。営業・マーケティング・事業開発の現場経験と経営視点の両方を併せ持つエキスパートとして知られています。また、セールスリクエストの原氏と共著で「インサイドセールス実践の教科書」を執筆されており、インサイドセールス領域における第一人者の一人です。
当日のイベントでは、以下のトピックについてお話しいただきました。
・”The Model”批判の実態と本質
・事業フェーズによるインサイドセールスの役割
・ビジネスモデル別のセールス・マーケティング手法
・ABMの3つの分類と戦略
・カスタマーインサイドセールスの概念
“The Model”批判の実態と本質
多くのBtoB営業組織において、「The Model」と呼ばれるマーケティング・IS・FSの分業体制が導入されている一方で、実際の運用においては様々な課題が顕在化しています。栗原様は、こうした課題の根本原因を整理し、フレームワーク自体ではなくその適用方法に問題があることを指摘されました。
部門間で頻発する課題
BtoB営業組織では、各部門で責任の所在があいまいになる傾向が見られます。営業担当者からは「インサイドセールスからあがってくる商談の質が低い」という声が上がり、インサイドセールス担当者は「マーケティングが獲得するリードの質が低い」と反発します。

経営層からは「インサイドセールスが単なるアポ取り係になっている」という懸念が示され、効率性の観点からは架電効率の改善要求が寄せられがちです。
「The Model」への批判と問題点
栗原様は、一般的に指摘される「The Model」の問題点を整理されました。顧客体験の分断では、インサイドセールスからフィールドセールス、そしてカスタマーサクセスへと担当が変わることによる情報共有の不備が発生します。組織的な課題としては、売上未達時の責任所在が不明確になったり、短期的なKPI重視の傾向に偏ったりするケースが見受けられます。

問題はそれらにとどまりません。分業化の弊害によりスキルアップや昇給が難しく、キャリア形成のハードルが上がってしまうのです。結果として社員の離職につながるだけでなく、組織構築の阻害要因となることも挙げられます。
しかし栗原様は、「特定のフレームワークがビジネス成長にそこまで大きな悪影響を与えるのか?」という根本的な疑問を投げかけ、問題の本質は別のところにあると述べました。
事業フェーズによるインサイドセールスの役割
栗原様が特に強調されたのは、PMF(プロダクトマーケットフィット)達成の有無によって、インサイドセールスの必要性と役割が変化するということです。多くの企業が「The Model」の導入に失敗する理由は、自社の事業フェーズを正確に把握せず、一律にフレームワークを適用しているからだと指摘されました。

PMF達成前のフェーズ
PMF達成前のフェーズでは、原則としてインサイドセールスを設置すべきではないと栗原様は指摘されました。この段階では、社長や事業責任者が商談獲得からクロージングまで一貫して担当し、顧客理解と売れるパターンの解明を最優先すべきだからです。
PMF達成前は製品を売りにくいフェーズにあるため、この段階で分業化を進めると、受注率が低下する可能性が高いのです。「自社商品と市場がフィットしていない状態で、営業プロセスを分業化するのは時期尚早です」と栗原様は説明されました。
PMF達成後のフェーズ
PMF達成後は、いかに効率よく市場へ自社商品を売り出せるかが焦点となります。
このタイミングではツール活用やインサイドセールスの人員確保を進め、トレーニングによる生産性向上を図ることが重要です。また、即時フォローが可能なワークフロー構築の重要性も強調されました。
次のPMFを見つけるフェーズ
ひとつの商品でPMFを達成しても、繰り返し新たなPMF先を探さなければなりません。業界や企業規模などを考慮して市場をリサーチし、手ごたえのありそうなセグメントが見つかれば事業責任者・マーケティング部門と連携する必要があります。
この段階では、インサイドセールスによるスピーディーな仮説検証が効果的です。業界・企業規模・部署単位での顧客セグメント洗い出しや多岐にわたるアプローチでの顧客反応分析を通じて、新たな成長機会を見つける段階といえます。
ビジネスモデル別のセールス・マーケティング手法
栗原様は、リードベースドマーケティング(LBM)やアカウントベースドマーケティング(ABM)の特徴に加え、それらを適用すべき場面について解説されました。事業モデルに応じたマーケティング手法の違いを理解することで、より効果的なインサイドセールスが可能になります。

リードベースドマーケティングの特徴と施策
リードベースドマーケティングは、数万社以上の潜在顧客を抱え、かつ商材単価が年間数十万円から数百万円程度の事業に適しています。成長戦略としては新規顧客開拓を重視し、主な施策としてデジタルマーケティング・展示会・セミナー等を行います。
栗原様は「この場合は“焼き畑”と呼ばれることもあるが、次から次へと見込み客にアプローチしていくスタイルになる」と説明され、SMB向けソフトウェア・人材紹介・M&A仲介などが具体例として挙げられました。
アカウントベースドマーケティングの特徴と施策
一方、アカウントベースドマーケティングは、数十から数百社(最大1500社程度)を対象とし、商材単価が年間数百万円以上の事業に適用されます。
成長戦略としては既存顧客との関係深化を重視し、特定顧客との関係構築・取引拡大によるLTV最大化を目指します。コンサルティング会社や大手広告代理店などが具体例として紹介されました。
ABMの3つの分類と戦略
続いて栗原様はLTV(顧客あたりの生涯価値)に基づくABMの詳細分類を紹介し、各モデルでの具体的施策を解説されました。LTVの規模によって、適切な戦略やインサイドセールスの役割が大きく異なることが示されました。
ABMスモールモデル(LTV:500万~1000万円)

ABMスモールモデルでは、顧客セグメントを絞ったセミナー開催や特定業界向け展示会・カンファレンス出展が効果的です。役職限定の少人数セミナーやDM送付も、有効な手法として挙げられました。
営業担当は約100社のショートリスト管理を行い、インサイドセールスとの分業が一般的です。このモデルでは、高度な業界理解と商材理解がインサイドセールスに求められると栗原様は説明されました。
ABMミッドモデル(LTV:1000万~3000万円)

発注金額が数千万円規模となるABMミッドモデルでは、顧客との関係性構築が極めて重要になります。エグゼクティブ向けラウンドテーブル開催や、会食・ゴルフなどによる接点創出が必須です。
役職者限定の手紙送付とフォローアップも効果的で、営業への顧客接点創出がインサイドセールスの主要な役割となります。
ABMラージモデル(LTV:3000万円以上)

最も高額なABMラージモデルでは、役員の定期訪問(年に数回)やゴルフコンペの開催、VIP席での接待なども重要な施策となります。中には体験型施設の建設に数億円から数十億円を投資する企業もあり、継続的なコミュニケーションによる大型取引獲得を目指すモデルです。
この規模になると、ホワイトペーパーのようなコンテンツもリード獲得を目的とするのではなく、特定顧客との接点作りのきっかけとして作成されます。取引金額が極めて大きくなるため、プロジェクトマネジメントの考え方に基づき、慎重に顧客との関係構築をデザイン・推進する必要があります。
カスタマーインサイドセールスの概念
栗原様は、既存顧客向けのインサイドセールス部隊によるアップセル・クロスセル促進のアプローチを提案されました。これは従来の新規客向けインサイドセールスとは異なる概念です。
カスタマーインサイドセールスの必要性

インサイドセールスというと一般的には新規客向けのイメージが強いですが、既存顧客を対象にするケースもあります。中でもABMのスモールモデルからミッドモデルでの有効性が高く、ロイヤル顧客以外の既存顧客(役員訪問対象外、エース営業のアサインなし)へのフォローが手薄になりがちな問題を解決できるのです。
一人の営業担当が抱える会社が100社~150社ほどあると、すでに関係性のある既存顧客へのフォローが追いつかないケースは珍しくありません。結果として、アップセル・クロスセルの機会を逸失している企業は多く見受けられるそうです。
具体的な活動内容
カスタマーインサイドセールスの具体的な活動として、以下の3点が挙げられます。
・既存顧客向けにメールマガジンを配信する
・商談の申し込みがあった顧客を営業担当につなぐ
・MAツールによる行動履歴を検知してフォローアップする
また予算策定時期に合わせて、既存顧客向けのイベントを企画・実行するのも有効です。営業が対応しきれない部分をインサイドセールスが巻き取ることで、営業担当とのWin-Winの関係構築が可能になるからです。
栗原様は「既存顧客への継続的なアプローチは意外に見落とされがちですが、自社の成長を促す貴重な機会です」と強調されました。
質疑応答

Q1. 有形商材と無形商材での違いについて
【参加者からの質問】
インサイドセールスのアプローチにおいて、有形商材と無形商材では戦略や手法に違いがあるのでしょうか。また、カスタマーインサイドセールスの概念についても詳しく教えてください。
栗原様からは、「有形・無形に起因する違いはあまりなく、むしろ対象顧客数や商材単価によって戦略や手法が変わる」との回答がありました。
ただし、有形商材の場合は製品を直接見せることが有効なため、オフライン施策(工場見学やモデルルームへの招待など)がマーケティング施策を打つうえで重要なポイントになるという特徴を挙げています。
また、カスタマーインサイドセールスについては、ABMのスモールからミッドモデルで特に有用な手法として詳しくご解説いただきました。
Q2. ABMスモールモデルでのインサイドセールスの業界理解について
【参加者からの質問】
ABMスモールモデルにおいて、インサイドセールスにはどの程度の業界理解や商材理解が求められるのでしょうか。他のモデルと比較して、専門性の重要度に違いはありますか?
栗原様は、「インサイドセールスに求められる商材・ドメイン理解の深さはABMの3分類によって異なります。スモールモデルではイベント企画も担うため、ドメインエキスパートとしての高い専門性が必要です」と回答されました。
一方で、ラージモデルではCEOや開発部門が深い知見を持つため、インサイドセールスの専門性の重要度は比較的低くなる傾向があることをご説明いただきました。
Q3. LBMからABMへの切り替えタイミングについて
【参加者からの質問】
事業のフェーズによっては、LBMでもまだまだ成果を上げられるケースもあると思います。しかし、どこかでABMに切り替えるべきタイミングが来ると思うのですが、その戦略転換の判断軸はどこに置くべきでしょうか?市場シェア率も含めて、栗原さんのご意見を教えてください。
栗原様は「重要なのは自社が属する市場の構造分析です」と回答されました。市場に独占的な大企業が存在せず、中小・零細企業が多数存在する「多数分散型市場」(例:研修会社、コンサルティング会社など)、特定企業がシェアの7割~8割を占める集中型市場(水道、鉄道、デジタルプラットフォームnあど)など、自社が属する市場がどういう特性を持つのかを見極める必要があります。LBMで大きくなる企業が多い市場であればLBMを継続すべきであるし、ABMで大きくなる企業が多い市場であれば、可能な限りABMを中心に組み立てるべき。そのうえで「先行企業を調査し、自社が将来どのような手法で顧客開拓を行うのかをを判断基準にしてみては?」と提案されました。
交流会の様子
講演後の交流会では、栗原様の体系的なフレームワークに対する高い評価の声が多数聞かれました。とりわけ事業フェーズとビジネスモデルの組み合わせによる戦略設計への関心が高く、PMF達成前後での組織体制変更の具体的手法に関する質問が集中しました。
ABMスモールモデルでのインサイドセールスに求められる業界理解の重要性について活発な議論が行われ、有形商材と無形商材での戦略の違いに関する質疑応答も盛り上がりました。LBMからABMへの移行タイミングの判断軸については詳細な意見交換が行われ、カスタマーインサイドセールス概念への新鮮な驚きや導入検討の声が多数上がっていたようです。

インサイドセールス研究会の交流会では、毎回「新しい体験を提供する」というテーマのもと、参加者に特典としてちょっとした品物やサービスをプレゼントしています。今回は参加者へのお土産として、「#Feel Health CHIPS(フィールヘルスチップス)」をご用意しました。「健康的なお菓子でありながら味がしっかりしている」「ダイエット中でも罪悪感なく食べられそう」など、参加者の皆さまから好評でした。
最後に
今回のインサイドセールス研究会では、「The Model」批判の背景に潜む本質的な課題に迫りました。
具体的な事業フェーズとビジネスモデルという2つの軸で整理することで、インサイドセールスの真の役割を明確化することが可能になります。栗原様の「フレームワーク自体が問題ではなく、自社のビジネスに合わせてモデルを適用・変更できないことが問題の真因」という指摘は、多くの参加者にとって目から鱗の内容でした。
PMF達成の有無による組織設計の違いや、LTV規模に応じたABMの3つのモデル、そして既存顧客へのアプローチを強化する「カスタマーインサイドセールス」の概念は、参加者の今後の活動に大きなヒントを与えるものとなったことでしょう。
本イベントの内容が、ご参加いただいた皆さまの事業成長に少しでもお役に立てば幸いです。
次回のインサイドセールス研究会は、株式会社ログラスの平島 郁巳様をゲストに迎え、2025年9月11日(木)19:00-21:00に渋谷で「SDRでエンプラを開拓するABM戦略とは?〜マーケ×ISで取り組む戦略的挑戦〜」というテーマで開催いたします。
次回のインサイドセールス研究会で、多くの参加者とお会いできることを楽しみにしております。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。
導入検討の初期段階でもご覧いただけます。
導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。
面談予約はこちらから